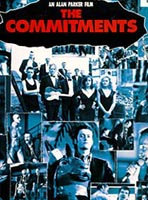![]()
|
1991年/イギリス/118分 ≪みんな、同じひとつの夢に生きていた。 ≫ |
|
■アイルランドはダブリンで”ソウル・バンド”を結成しようと盛り上がる、ジミーと友人。まずはメンバー探しなんですが、ジミーの家にオーディションを受けに来る人たちがケッサクです。私はソウル・バンドって具体的にどんな音楽をやるのか知らなかったのですが、玄関先で「好きなミュージシャンは?」と聞かれ、バリー・マニロウと答えたひとに大ウケ。いくら音楽に疎い私でも、さすがにバリー・マニロウでないことは分かる気がします。他にもたくさんの人がオーディションを受けにくるのですが、その中にカルチャークラブのボーイ・ジョージに激似の人がいたんだけど、あれ本物じゃないよね。(実物はあの1.5倍はあると思うんだけど) ■オーディションやスカウトで集めたメンバーは、どいつもこいつも実にやっかいです。ボーカルのデコは太ってるし。ヴィジュアル系じゃないので別に構わないのですが、それにしても下品です(人間が)。しかし唄は上手い。ものすごく上手いのです。顔さえみなきゃ彼の歌で泣けるかも知れません。トランペット担当のジョーイは、メンバーの平均年齢をひとりで上げているオッサンで、ついでにデヴィッド・シーマンにそっくりです。嫌すぎます。しかもそんなオッサンが“ジョーイ・ザ・リップス(唇のジョーイ)と呼んでくれ”なんてぬかすんですよ!!(誰が呼ぶか)。おまけに、過去に数々の大物ミュージシャンと共演したことがあると言い出したりして大変にうさんくさいのです。他のメンバーも似たり寄ったりのよせ集めで、ジミーのいう「ソウルバンド」の意味がもひとつ分かっていません。もちろん私も。そこでジミーはみんなを集めビデオを見せます。それがジェームス・ブラウン。ゲロッパのおじさんです。非常に分かりやすいのはいいのですが、一様に戸惑いを見せるメンバー。「俺たち、こんなのやるには白すぎやしないか」というメンバーの疑問に、ジミーは答えます。 「アイリッシュは欧州の黒人だ。中でもダブリンっ子は黒人の中の黒人なんだ。だからこういう音楽をやるのに相応しいんだ。」 説得力があるようなないような、なんとも微妙な言葉です。でも分かる気もします。ただ、そういうジミーが一番色白だったりするのですが。 ■寄せ集めで始まったバンドが練習を重ねていくうちにそれっぽくなり、ライブも盛況。しかしバンドとして成功しつつある裏でメンバー間は次第にぎくしゃくしていきます。コーラスの女性3人は1人の男を巡り大喧嘩(しかもそれがジョーイだったり。萎)、デコはレコードを出さないかと誘われたことを自慢気に吹聴し、他のメンバーとこれまた掴み合い。こんなバンド辞めてやるーー!!!と楽屋では一触即発の彼らですが、アンコールの声に応え舞台に上がった途端、活き活きと演奏し歌います。ステージ上のメンバーの楽しそうな笑顔は決して作り物ではないことが伝わってくる、いいライブなのです。しかし、演奏している間は見事にまとまっている彼らもステージを降りればやはりわだかまりの根は深く、デコとドラムの男(名前忘れました)の大喧嘩を機についに解散。マイナーレーベルとはいえ、デビューも決まりかかっていた矢先だっただけに、ジミーの失望は大きく「勝手にしろ」とつぶやき去っていきます。 ■そんなジミーを追いかけてきたジョーイ。傷心のジミーに彼は言います。「バンドの成功がなんだ。お前は何かを成し遂げた。みんなの新たな地平を拓いたんだ。」 トラブルの元のお前が言うなや・・・といまひとつ有難さに欠けますな。ジミーの地平は閉じてるし(この時は)。ですが、その後新たなバンド活動、またはソロ活動を始めたメンバーもいて、それまでなんとなく暮らしていた彼らの事を思えば、たしかに“新たな地平”は開けたのかも知れません。結婚して普通の生活を送っている人、違う職業に就いた人についても同様。決して音楽を忘れていないと思うから。 最後は大団円というわけにはいかなかったけれど、とても後味のいい映画でした。それに細かいシーンでアイルランドを感じられるところも好きです。たとえば、オーディションを受けに来た青年が演奏するバイオリンに合わせてジミーの家族がリバーダンスを踊っていたりとか、パブでもライブでも結婚式でさえも飲むのはやはりギネスだったりとか。小さいシーンががしみじみ楽しい映画でした。 |
|
1987年/イギリス・ジンバブエ/113分
|
|
■反アパルトヘイトの活動家、ダイアナ・ロスのお話。実話です。物語はダイアナの長女、モリーの目を通して進んで行きます。モリーの家は両親ともが熱心な反アパルトヘイトの活動家で、父親はある晩出て行ったきり行方知れず。母親と祖母、二人の妹と暮らしていたところ、母ダイアナも逮捕されてしまいます。刑務所で仲間のことを話せば釈放してやると言われても頑として拒否するダイアナ。モリーも学校でクラスメイトたちに嫌がらせされながらも、休むことなく通いつづけます。二人とも実に立派です。ようやく釈放の日が来たと思ったら、刑務所を出た瞬間に再逮捕。嫌がらせなのですな、ようするに。でもわかっていてもさすがに涙が止まらないダイアナ。いい加減心も弱くなってくるのですが、それでも絶対に仲間のことを話さない彼女に警官どももお手上げ状態。ダイアナは自分の命と引き換えにしてでも仲間を守り通そうとします。彼女たちの活動の意味を考えることさえしない(できない)お馬鹿どもとは腹のくくり方が違うのです。結局、自殺は未遂で終わりダイアナは釈放されるのですが、それでも家は24時間体制で監視され、彼女たちと一緒に闘っていた黒人のソロモンは殺されてしまいます。怒り心頭のモリーは見張りの警官に向かい、「いい加減にしてよ!目障りなのよ!」と絶叫。それを「威勢のいいお嬢ちゃんだな〜」と余裕かましてるつもりの警官たちは、自分達が絶えずモリーの家を見張っていなければならないほど、彼女たち活動家を黒人を恐れていることに正味のとこ気がついていない愚か者なのですな。 ■滅多なことでは泣かないモリーが母親が自殺しようとしていたことを知り、「自分たちを置いて勝手に死ぬつもりだったの!」と感情を爆発させるシーンは切ないです。他の家の子供たちが気楽に生きている中、モリーの両親だけが家族より他人のために一生懸命なのです。いくら大人びてみえるとはいえ、たった13歳のモリーがそれを全て納得して受け止めていたはずがないのに。自分は母親失格だと詫びながら、それでも自分たちの活動の意義を諭すダイアナと静かに母親を許すモリー。家から出ると再び逮捕されるかも知れないダイアナが、ソロモンの葬儀に参列すると言えば、「私も行く。彼の友達だから」と答えるモリー。すでに親子ではなく同志です。 この後、ダイアナは暗殺されてしまうらしいのですが、モリーはどうなったのか分かりません。(←調べろ)母親の跡を継いだのかも知れませんが、いずれにしろしんどい人生だと思いました。 ■反アパルトヘイト仲間、ハロルド役のティムはいつもと違い穏やかです(笑)。いっそ淡々とした印象を受けるのですが、内に秘めたモノの強さを感じさせる顔をしています。母親の釈放を指折り数えて待っていたモリーの元にダイアナが再逮捕されたことを伝えにきたハロルドは、彼女に「自分勝手に生きてはいけないんだよ」と言います。モリーのことを完全に大人扱いしているハロルドですが、中学生といえば自分勝手に生きることが許される最後の年代だと思っている私にはちと厳しいんじゃないかと思えました。ハロルドはダイアナのことをとても尊敬していたと思うし、娘のモリーにも彼女と同じ、なんつうか匂いみたいのを感じていたのかも知れないのですが。 物語に関係なくツボだったのが、母親が逮捕され祖母も倒れ、家に子供たちだけになった時に「うちにおいで」とハロルドが誘いに来るシーン。モリーにあっさり「寄宿舎に入るわ!」と断られてます(笑)。なんてもったいない。私が行きたいよ。 |

 ■なんだかんだあっておっさんの元から逃げ出したあと、陽光がさんさんと降り注ぐ森でうさぎさんや鹿さんたちに見守られながら裸で抱き合う2人(BGMも癒し系)のシーンはあまりに唐突でもはや理解不能。さらにそこへ突如として現れるフランス警察(というよりそのいでたちからして特殊部隊か?)に追われ森の中を逃げる途中、先のおっさんが仕掛けたと思われる罠に嵌り倒れた男の子が『キミだけは逃げてくれ』とかっこよく彼女を逃がしたのはいいけど、結局のとこ問答無用で射殺されてるし・・・。(逃げなきゃ死ななかったのに)
■なんだかんだあっておっさんの元から逃げ出したあと、陽光がさんさんと降り注ぐ森でうさぎさんや鹿さんたちに見守られながら裸で抱き合う2人(BGMも癒し系)のシーンはあまりに唐突でもはや理解不能。さらにそこへ突如として現れるフランス警察(というよりそのいでたちからして特殊部隊か?)に追われ森の中を逃げる途中、先のおっさんが仕掛けたと思われる罠に嵌り倒れた男の子が『キミだけは逃げてくれ』とかっこよく彼女を逃がしたのはいいけど、結局のとこ問答無用で射殺されてるし・・・。(逃げなきゃ死ななかったのに)