ACID RAIN 2011参加報告
大泉 毅(アジア大気汚染研究センター)
初夏の北京は思いの外暑く、時折の激しい雨は東南アジアのようでした。
ACID RAIN 2011 は6月16日から18日の3日間、北京の“中国ナショナルコンベンションセンター北京”で開催されました。
この施設は、全長398m、全幅148m、高さ42mで、日本でいえば幕張メッセのような見本市会場と国際会議場が一体化した施設です。
ただし、北京オリンピック公園の中心に位置し、メインスタジアムである“鳥の巣”、室内プールである“ウォーターキューブ”、
室内競技場に隣接しているという恵まれた?立地にあります。
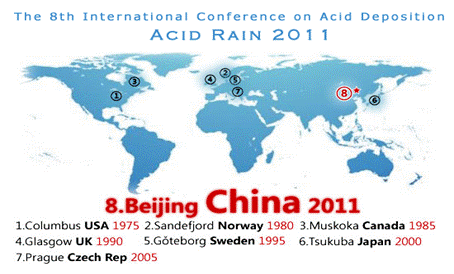


Bird Nest China National Convention Centre
ACID RAINは、
(1)降水酸性度が生態系に与える影響について評価すること、
(2)酸性沈着の程度、範囲、性質、影響について、研究者、企業、政府関係者、興味を持つ一般人が会して協議する場を提供すること、を目的に
5年毎に開催される国際会議であり、1975年を第1回として今回で8回目、アジアでは“つくば”に次いで2回目の開催になります。
会議の全容については、セッションが多くてとても説明不能ですので、
まず、以下に今回の会議の趣旨を開催案内より転記してみます。殆ど直訳ですが、雰囲気は分かって貰えると思います。
「酸性沈着研究は多くの科学的挑戦を提示している。
地球規模の気候変動や地球システムモデルが、植生に関する詳細な情報や植生−土壌−大気の相互作用をこれまで以上に取り込み始めたために、植物の物理的特性に影響する、あるいは最終的には気候に影響を与える栄養分や汚染物質の沈着に、再度、新たな興味がもたれている。微量成分、特に窒素や硫黄やリンの生物地球科学的循環に関する研究は、将来の気候や土地利用の変化の理解に必要な新たな挑戦を提示する。Acid Rain 2011はこれらの分野を強調し、生物地球化学的循環とその地球システムへの適用に着目する科学者の参加を促す。」
全体会での講演、いわゆるPlenary sessionの演題は下記のとおりです。

Plenary session:Mr. Zhang (UNEP)
Shigang Zhang (UNEP): Regional Air Pollution in Asia and
the Pacific: Promoting Regional Cooperation
Jiming Hao (China): Emission and
Controlling of Acid Rain related Chemical Species in China: 1990-2010
Douglas
Burns (USA): Acid Rain in North America: Past, Present, and Future
Tao
Wang (China): Acid deposition in China: An overview of the results from a
5-year national study
Gregory
R. Carmichael (USA): The Globalization of Air Pollution
E. C.
Rowe (UK): Nitrogen and biodiversity
Yuanhang Zhang (China): Air Pollution in Asian Mega-Cities:
Formation and Transport Schemes and Control Strategy on Regional Air Quality
R. C. Helliwell (UK): Long-term record of acidification and
recovery
それほど目新しい演題はありませんが、欧米の研究者が過去と未来を論じ、中国の研究者が現在を切り取っているとの印象です。
セッションは全部で15個あり、口頭発表が180件、ポスター発表が116件でした。
全体会での講演7件を加えて、全体で300を超える発表があったことになります。
各セッションのタイトルは以下のとおりです。括弧内は (Oral, Poster)の内訳です。
現状で、国際的にどのような研究分野に人気があるかは、下記の発表件数から類推してください。
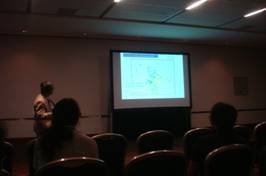
Invited Speaker:Dr. Akimoto(ACAP)
T1. Emissions Inventory (12, 3)
T2. Long-range Transport and Modeling (15, 10)
T3. Atmospheric Dry
Deposition (11, 7)
T4. Cloud Chemistry and Wet Deposition (21, 24)
T5. Air Pollution and its Impacts (29, 10)
T6. Air Pollution, Acidification and Climate Change
(12, 6)
T7. Soil Acidification, Forest Damage and Critical
Loads (7, 7)
T8. Biogeochemical Cycles (10, 5)
T9. Water Acidification and Effects on Aquatic Biota
(4, 12)
T11. Long-term Trends of Acidification and Recovery
(10, 9)
T12. Nitrogen Cycle and its Effects on Ecosystem
(10, 2)
T13. Regional and Hemispheric Strategies and Policy
(9, 0)
T14. Control Technology of Acidic Pollutants (5, 4)
S1. Physical and Chemical
Processes in the Atmospheric Boundary Layer (10, 7)
S4. EANET and its Relative Activities
(Past, Present & Future) (15, 10)
また、招待講演者26名の国別構成は、日本4名、英国3名、米国3名、ノルウェー3名、カナダ2名、スウェーデン2名、
中国2名、オーストリア1名、韓国1名、フィンランド1名、イタリア1名、フランス1名、ドイツ1名でした。

Demonstration of EANET
EANETは”つくば”と同様に、北京でも専用ブースを設置し、
これまでのモニタリングの集計結果や最近の活動に関して、ポスター掲示や出版物配布によるデモンストレーションを行いました。
EANET参加国からの参加者は、中国、次いで日本が多く、3番目はロシアでした。
印象的であったのは、韓国からの参加者が1名のみで、それもEANETの中心メンバーであるInha大学のProf. Choのみであったことです。
彼によれば、韓国では政府も含めて大気環境問題としての酸性雨の位置は低く、粒子状物質が主要な研究テーマとなっているためとのことでした。
中国は前回のプラハ開催時に次回の開催を約したものの、国内的にはいまだに対策が不十分である酸性雨問題をことさらにクローズアップすることへの反発や、
加えて、ジャスミン革命以来、中国政府当局が大人数の集散を好まない傾向にあり、そのためにこの開催に際しては大きな困難があった模様です。
それらの困難を乗り越えられたのは、実質的に会議の全てを取り仕切った中国科学院大気物理研究所のProf. Zifa Wangの快活で明晰な資質が大きな原動力になったものと推察されます。
次回の開催は、英国が候補として囁かれている程度で未定です。協議では、酸性雨から間口を大きく広げて、名称も変更してはとの意見も出たそうですが、
酸性雨を長年専門としている研究者からは、他の国際会議との棲み分けこそが重要との意見が出され、合意に至らなかったとのことです。

Photo by Dr. Huo
私は“つくば”以来の2回目の参加でした。
前回のプラハには行きそびれてしまったので、その分も、北京の初夏を満喫させていただきました。
昨年度からACAPに勤務している北京大の出身のDr. M. Q. Huoという強力な案内役のおかげです。
以上、簡単ですが、報告させていただきました。