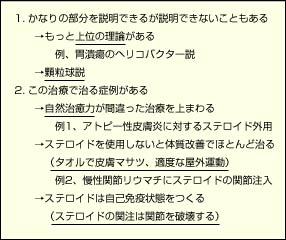
ATOPY INFORMATION論文に戻る
体調と免疫系のつながり 再び、胃潰瘍、アトピー性皮膚炎、慢性関節リウマチについて
(治療、82, 9, 2433-2438, 2000)
新潟大学医学部医動物学教授 安保 徹
*
はじめに
一度、教科書的になってしまった病気の考え方や治療法を変えることは大変難しい。たまに、現場の医師がその病気について疑間を持ったり、なかなか治療がうまくいかない現実に疑間を感じたりしても、まわりの大多数の人達が大きなうねりの中で流れているのを引き留めるには、爆発的なエネルギーが必要だからである。
ここに述べる胃潰瘍、アトピー性皮膚炎、慢性関節リウマチは上記した病気の典型ではないかと思う。この3つの病気を治療する医師は、それぞれ専門家であり長い治療経験を積んでいる人も多い。そしてこの治療経験の長さが、さらに問題を複雑化していく。
この連載ですでに、個別にこの3つの疾患の病因と治療法を述べたが、その説明は第一線の専門家を説得するのに十分だったとはいえない。ここではその後さらに研究を続け、もう少し上手に説得できる考え方やデータを得ることができたのでここに紹介する。
*
胃潰瘍学説の検証
胃潰瘍の成因を「顆粒球説」とすると、すべての胃潰瘍の成り立ちを矛盾なく説明できる。ストレスの持続(精神的なものも身体的なものも含む)→交感神経緊張→血流障害と顆粒球増多→粘膜障害である。
このような簡単な理論で胃潰瘍の成因を説明できるのであるが、これを納得させる最も単純な事実は、病理標本で見ると胃炎の粘膜や胃潰瘍の周囲には多数の顆粒球が浸潤しているということである。特に急性炎症にこの傾向がはっきりする。実際,最近は「胃炎や胃潰瘍の炎症説」がこの分野の多くの専門家によって提唱され始めている。
しかし、後で述べるように「炎症説」は「顆粒球説」の一部分を説明しているが、まだ不完全な考えである。
また、病理学者の中には、潰瘍ができたからあとで顆粒球が集まってきたのだと私の説に反論する人もいた。しかし、これもこれから述べるように事実の一面しか見ていない。
皮膚や粘膜に傷がつくとその周囲に顆粒球が集まるのは事実である。これも、組織障害は原因に関係なく一時的に交感神経系が刺激されるという法則ゆえである。逆に無傷の部位に顆粒球が集まり過ぎると、血流障害が先行してその後組織が破壊されるということも理解しなければならない。顆粒球増多⇔組織障害、のサーキットである。
また、胃潰瘍の酸説(peptic
ulcer
theory)をきちんと考察しないまま、最近では胃潰瘍の形成に「ヘリコバクター・ピロリ菌説」が登場している。そして、いずれの専門家もそれぞれの矛盾点を指摘しないまま共存している。この理由は、2つのそれぞれの説の矛盾点を十分考察しないまま、当てはまる事実だけで理論を考えるからである。(図1)
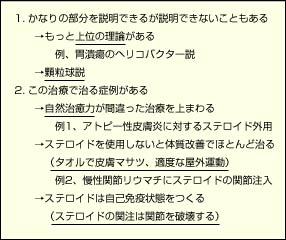 |
|
|
胃潰瘍のヘリコバクター説の弱点は、ヘリコバクター・ピロリ菌(−)の人でも胃潰瘍になる人がいるし、また逆に、ヘリコバクター・ピロリ菌(+)の人でも胃潰瘍にならない人がいることである。いくらヘリコバクター・ピロリ菌を抗生物質でたたいて胃潰瘍が治ったとか再発しないとかいっても、こういう疑間点を解決しないのは問題である。
最近、一部のみを説明できる理論を普遍的理論と勘違いする人が多すぎる。このような時は、もっと上位の理論がある可能性を考えなければならない。
つまり、胃潰瘍の場合は「顆粒球説」である。この理論を導入すると、ヘリコバクター・ピロリ菌説もすべて飲み込んで説明できる。つまり、ストレスで増加した顆粒球を活性化するのは常在する細菌であるし、ストレスが強過ぎる時は常在菌の存在しない人でも顆粒球の単独の働きで粘膜が十分破壊されるからである。ここでは再び詳しくは述べないが、「胃潰瘍の酸説」は治癒反応を誤解して生じている(文献3を参照)。
*
ステロイドホルモンの抗炎症学説の検証
多くの医師は、ステロイドホルモンを抗炎症作用を持つ物質と単純に信じてはいないか。これは半分は正しいが、残りの半分は正しくはない。つまり、ステロイドホルモンはリンパ球の炎症に対しては抗炎症作用を示すが、顆粒球の炎症に対しては使用が長引くと、むしろしだいに炎症増悪作用を発揮し出すからである。このため、多くの間違った治療が行われているように思う。
ステロイドは組織に停滞した時、自然酸化を受け酸化コレステロールに変性していくからである。酸化物質は局所から全身へと交感神経緊張状態をつくり、血流障害と顆粒球増多を招き、ついには顆粒球の炎症を誘発する。
この考えやデータを知らないと、アトピー性皮膚炎の難治化やステロイド依存症のメカニズムをいつまでも理解できない。もし、この考えがない場合は、アトビー性皮膚炎に対してステロイド外用薬を使い続け悪化しても「仕方のない」ことと自分を説得する。患者の体質のせいにする。また、「この治療で治る症例もある」と自己弁護する。
確かに「この治療で治る症例がある」ということ自体に間違いはないが、これは自然治癒力が間違った治療を上まわったと考えるべきと思う。実際、例1のごとくステロイドを使用しない人達は体質改善でほとんど治るからである。もし、患者がすでにステロイド依存症に陥っていたとしても、ステロイド離脱ができるし、その後の予後の良さはステロイドを塗り続けるのとは比較にならない。
ステロイド外用の破綻はアトビー性皮膚炎に限ったことではない。例2のごとく慢性関節リウマチ患者にステロイドの関注を行った時でも同様である。関節局所に激しい血流障害と顆粒球増多がきて、関節を破壊していく。現在は、このような治療がほとんど行われなくなったが、同じことがまだアトピー性皮膚炎の治療では続いている。アトピー性皮膚炎の場合は破綻までの経過が長いために、破綻に気づきにくいためであろう。
ここで付け加えておきたいことは、慢性関節リウマチを含めたほとんどすべての自己免疫患者はリンパ球が減少して免疫抑制状態になっていることである。
ここに免疫抑制剤であるステロイドホルモンやメソトレキセートを投与するのであるから、むしろ病気を悪化していくことになる。
自己免疫疾患は、顆粒球と胸腺外分化T細胞の過剰活性化によって引き起こされている病態である。進化レベルの高い免疫系はかえって抑制されている。RAでもSLEでもリンパ球減少がくることを思い起こしてほしい。
*
痛みや炎症反応の正しい病態把握
ステロイドホルモンやNSAIDsを長期使用することによって、炎症が悪化するメカニズムを述べてきたが、これを正しく理解するためには痛みや炎症がどのようにして生じているかをも理解する必要がある。この理解なくしては、だれもステロイドホルモンやNSAIDsが炎症増悪作用を併せ持つことを納得することはできない。
この理解を助けるための図をつくってみた(図2)。私達の組織はいろいろな原因によって障害を受ける。例えば、寒冷による血流障害(霜焼け)、筋疲労による血流障害(椎間板ヘルニア)、物理的力による組織障害(外傷)、熱や紫外線による組織障害(やけど)、アレルギー反応による組織障害(アトピー性皮膚炎や気管支喘息)などを思い浮かべてほしい。このような血流障害や組織障害の極期は、その局所や全身が交感神経緊張状態になっている。
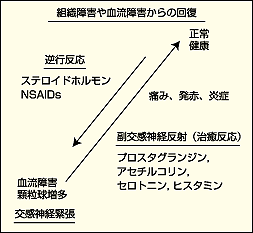 |
|
治癒にどのように関与しているのか |
この血流障害や組織障害の部位には顆粒球が集まってきて破壊された組織を取り除く働きをするが、この過剰反応は自ずからの組織を自分でさらに傷つけることになる。そして、生体がこのような状態から逃れようとする反応が次に引き起こされる。つまり、副交感神経反射あるいは治癒反応である。この時、プロスタグランジン、アセチルコリン、セロトニン、ヒスタミンなどが分泌され、血流が回復し組織の治癒が進む。しかし、これらの物質は血管拡張や発赤や痛みを生み出し炎症として,私達の目に留まる。
このような反応が十分起こると、組織は修復され正常あるいは健康な状態に戻る。しかし、この副交感神経反射が強く起こり過ぎた時は、「虚血後再巻流」とも呼ばれる反応となる。上記した反応である。したがって、この治癒反応をゆっくりと進める意味で、ステロイドホルモンやNSAIDsの使用は意味を持っている。
ところがステロイドホルモンやNSAIDsを多量にあるいは長期間使用した場合には、図に示すように逆行反応を引き起こすことになる。これが、それぞれアトピー性皮膚炎の難治化や腰痛の難治化である。
*ステロイド依存症の脂質・コレステロール代謝
アトピー性皮膚炎患者にステロイド外用薬を長期間使用した場合、ステロイド依存症になる。
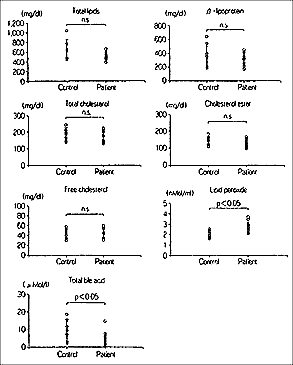 |
|
陥った時の脂質、コレステロール代謝 |
使い始めはステロイド外用薬が一時的に抗炎症作用を示すが、炎症は再発しこの繰り返しで長期使用に陥る。外用したステロイドホルモンは組織に残り、自然酸化を受け酸化コレステロールとなる。コレステロール骨格の側鎖の酸化パターンによって約20種類の酸化コンステロールとなっているものと考えられる。
酸化コレステロールは局所や全身を酸化物として刺激し、血流障害と顆粒球増多を招く。この状態は、交感神経緊張症状としてとらえることができる。白血球分画はリンパ球が減少し顆粒球が増加するパターンとなるし、頻脈や不安などの交感神経症状も伴ってくる。
これらの考えをもっと科学的に示すため血中の脂質、コレステロール関連物質のレベルを測定した。その結果、脂質、コレステロール代謝の異常が来ていることを明らかにした(図3)。ステロイド依存症のアトピー性皮膚炎患者ではコントロール(年齢をあわせた)に比べて、血中の総脂質、β−リポプロティン、総コレステロール、エステル型コレステロールが多少減少している。遊離コレステロールに差はないが、「過酸化脂質の増加」と総胆汁酸の低下が有意(p<0.05)に見られた。患者ではコレステロールや脂質の酸化が進み、これを胆汁酸やその他としてさかんに排泄する現象が表れているのではないか。
*“ストレスと病気”に介在するもの
これまで精神的ストレス(心の悩みや不安)や身体的ストレス(働き過ぎや不規則な生活)が病気を引き起こすメカニズムとして、交感神経緊張によってもたらされる血流障害と顆粒球増多を強調してきたが、さらに介在する因子を挙げる必要がある(図4の1)。つまり、血流障害と免疫抑制によってもたらされる次なる現象、潜伏ウイルスの顕性化を考えなければならない。若い人でも老人でもストレスが加わった時に、それぞれ口唇ヘルペスが出現したり帯状庖疹にかかったりすることはよく知られたことである。
この他、私達のからだの中には多くのウイルスがプロウイルスという形で遺伝子中に潜伏していて、からだの抵抗力が弱った時に顕性化する。そして、からだの方に余力がある時はリンパ球を増やしてこれらの顕性化したウイルスと戦い治癒する。これらは風邪と似た症状を表す。しかし、余カが少なくなっている人は時にはウイルス疾患として発病するものと思われる。
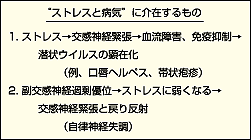 |
|
感受性の上昇のメカニズム |
もう1つ“ストレスと病気”を深く理解するために必要なことがあると思う(図4の2)。副交感神経優位はそもそもリンパ球増多を招き感染に対する抵抗性が高まる状態であるが、これが過剰に進むとストレスに弱くなり病気を起こしやすくなるという逆転現象に至ることを知る必要がある。
ストレスに打ち勝とうとしてよくものを食べ、肥満が進んだ状態ともつながっている。また、運動不足や排気ガス吸入もこの体調を招く。ちょうど肥満が進むとある所まではゆったりした副交感神経優位の体調なのであるが、行き過ぎるとからだが重過ぎて、少しからだを動かすと息が切れる、疲れるといった状態を指している。これが図4の2の状態である。まとめていうと、交感神経緊張状態が続くと病気になるが、逆にゆったりが過剰になっても(過剰の副交感神経優位)病気になりやすくなるということである。
*おわりに
胃潰瘍、アトピー性皮膚炎、慢性関節リウマチなどのありふれた病気が、病気の本体を正しく理解しないまま治療が行われているといわざるを得ない。また、これらの治療に使用する薬の作用も、表面的な作用だけを見ては、その作用の本質を誤るのではないか。これらの問題は、現在の医療の不信や民間療法の花盛りを生み出す原因の1つにもなっているのではないか。