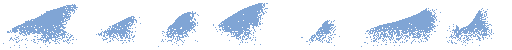
2006年1月19日(木) 本日も いまいちのお天気 バイクで通勤。 バイクで行くと、冷える冷える。 なんとかG農業の原稿ができたので とりあえずホッとした。 でも、また遅れた。あいかわらずの いいかげん文章で編集部の方がきちんと 校正してくれるので出せているが・・・ もうちょい納得して書けたらえいが・・・ 今日も机の上のおかたずけなどした。 H少年氏らを誘って、北関東あたりの 近郊隆盛産地&GAP&省エネ&新品目 あたりでの調査などの計画をしてみることにした。 帰ったら モリは微熱で学校早引けダウン マコもついでにダウン していた。 ありゃま・・・ 夜は 会の準備をしないといけないのだが これまたどうも気が乗らない。 普通、わたしらは会を段取る時には 目的がある。 会を通じて対象者を目的に近づけていくために開催する。 ただ会を開いただけで、結果がでるわけないので 普段の活動の中で、現場を歩いて 会の効果を上げるための下ごしらえをしたり 情報収集したりする。 そういう生きた情報と、現状の課題整理があって それを会の中に盛り込んで、初めて会が生きる。 参加したメンバーに当事者意識ができる。 それから、会で反応を見て、 会の後の普段の活動で またフォローして次へつなげる。 そういうのが普及員の仕事だ。 そのいわゆる、会に集まるメンバーの レベルアップなり合意形成なりを仮にも目指しているのなら、 そういう会の前後のフォローを含めての、 普段の活動の計画なり作戦が ぼんやりとでもいいので頭にあった上で、会をし そしてまた、普段の活動をし、 そして次のステップアップした 会へつなげていくというのが定石だ。 そういうつもりがないと、 絶対にいい会にはならない。 そうでないと まず、一回の会は、ただの一回の会をやっただけ で終わってしまう。 自分たちがかかわって、相手にかわってもらう 成果を残すには、それくらい継続的な あの手この手、手を変え品変えの取り組みが必要だし、 会の開催というのはその過程の単なる手段にすぎないわけだ。 それから講師を呼ぶだけの会はよくない。 講師に全部任す!という会のやり方は 技術屋としては自分の仕事を捨てたということになる。 現在毎日その地域で関わっている人というのが 一番わかっているわけなので、 まずはその当事者が汗をかかないといけない。 その上で、会の参加メンバーがさらに こういう話も聞いてみたい となった時には、 適した講師に来てもらうという順番がある。 ただし、講師はあくまで、会のあるいは地域の 当事者ではないわけだし 参加メンバー達、そして会をやる人が どういう考えで、普段何をどうしようと取り組んでいるのか がわからないままでは、本当につっこんだ話はできない。 だから、講師を呼ぶならば 講師と会を段取る人との 打ち合わせなり役割分担が 欠かせない。 『私たちは今、こういう考えで、こういうことに取り組んで、 対象はここまでは来ている。でも、ここが足らないと思うので ここをこういう風に話してくれないか! こういう風な話ができないか!』 という持ちかけをしないといけない。 そういうのがなくて、講師に任せっぱなし というのは、無責任だと思うし 時間ももったいないし 講師にやりがいも持ってもらえない。 ということは、そういう会は はじめから、おもしろい、よかったという会には なりにくいちゅうことなのである。 ま、けんど、あちこちには 会をすることに意義があってやる会もあるわけで かく言うわたし自身も、そういう会も 最近はやったりしていたりしているわけで ま、世の中 まったく意味がないことは一つもない まったく必要でないことも一つもない まったくムダなことも一つもない まったく矛盾がないことも一つもない ということで 前向きにいかんといかんかねえ・・・ |
 2006年1月表紙へ
2006年1月表紙へ