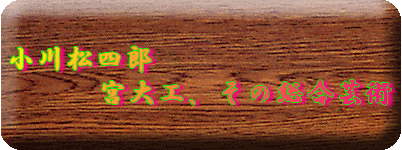左の写真が、松四郎作と言われる「獅子頭」である。全国各地で舞われている典型的な「獅子舞用」の獅子頭である。実際に使用されたものであるのかはわからないが、、しかし使用されたものならば、我が家に存在するはずはなく、今頃は神社などに鎮座していたのかもしれない。
上から順番に写真をご覧戴きたい。表面を黒漆で塗り、口の中に当たる内部は赤漆で塗られている。歯と目は金色が塗られ、他には一切の色を使用していない。頭部後方に規則正しく穴のようなものが並んでいるが、ここには毛髪が植え込まれていたようだが、父母や亡くなった祖父の話によると、犬の管理人が物心つかない頃に引き抜いてしまったらしい...
また、あごが上下するようになっていて、左右に木片が蝶つがいとしてはめ込まれている。だが、向かって左側のものは当初からの木片ではなくなっている。(紙を筒状にして丸めた物がはめ込まれている。)
獅子と言えばライオンのことと言われる、「シシ」という言葉自体シルクロードの彼方の言葉がそのまま日本に伝えられたと言われている。さらに驚いたことには、獅子または狛犬そのものがエジプトのスフインクスをあらわしているのではないかとも言われる。前述したように全国各地に獅子舞が残っていて舞われているが、獅子舞というのは何なのだろうか?日本神話には登場してこないように思う。しかし、神社と獅子舞は切っても切り離せない存在である。修験者により各地に伝承されていったところまではわかっているが、なぜ修験者なのかはわからない。わからないと言っても犬の管理人がわからないだけで、ちゃんとした文献などを読むとわかるのかもしれないが、少なくともインターネット上で見てもわからなかった。ご存じの方がいらしたらこ教授願いたい。
一見怖そうですが、じっくり見ると笑ってしまいそうになる「松四郎作 獅子頭」をじっくりご覧下さい。
耳の形などは犬が悪いことをして主人に許しを請う時に、こんな風に耳を伏せています。