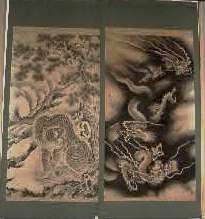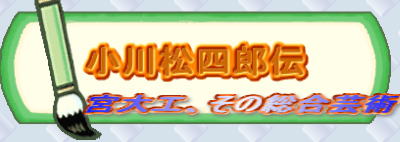小川松四郎伝 その一
宮大工 小川松四郎の生涯(犬の管理人私見)
松四郎は、犬の管理人の曾祖父に当たる。宮大工にして神社仏閣はもちろんのこと多くの絵や彫刻等を残した。
松四郎は、嘉永2年(1849)11月9日出生と本荘市役所の戸籍原簿に記載されているが、先頃、我が家の古箪笥の中から発見された木札によると、嘉永元年(1847)12月7日出生となっており、裏には、八幡神社宮司の名前が書き込まれ、表書きを証明している。当時としては、出生しても1年以上も、出生届をしないのが当たり前の時代だった。
それだけ、乳幼児の死亡率が高かったのではないかと思われる。以上余談である。
松四郎は、羽後の国、南内越郷(みなみうてつ)川口村に小川家17代当主になるべく出生した。父は大工であったが、親類に尾留川宇左右衛門という宮大工がおり、その人の影響を受け宮大工を志したと思われる。
兄弟たちは、それぞれ近くに分家あるいは、嫁いでいって、子孫なども判明しているのだが、嘉永5年に生まれている弟の小川松五郎なる人物のその後は定かではない。
明治三年に元本荘藩主、六郷公の下働きとして、東京の江戸屋敷に奉公に行き、のち警視庁巡査として奉職し、士族の養子となり、名を田中信正と改め東京は四谷に居住している。ということまではわかっている。子供がいなかったという話が残っているが、いま、田中家としての家名が存続し、子孫が存在していることを願いたい
さて、宮大工としての技能を着実に向上させていった松四郎は、神社仏閣を飾る彫刻まで手がけ、よりいっそうの技術向上のため絵を描くようになった。その師匠として、本荘藩御用絵師、増田象江を選んだ。増田象江は江戸で高名な絵師、谷文兆とも交流があったといわれている人物で、花鳥風月の絵は写実を極めている。一方、大黒天を描いた掛け軸が、我が家に残っているが、その風貌はひょうひょうとしたおかしみも感じられ、描画の技術に並々ならぬ物を感じさせる。一方、松四郎の絵は同じ大黒天の絵が残されているが、技術的にはうまいが、少し堅さの残る絵となっている。また、松四郎描くところの竜と虎の二対の掛け軸(写真)が、常に我が家の床の間にかけられているが、それらは、ややユーモラスな描かれ方がされている。描かれた年代によっても違うのかもしれない。さらに、述べさせてもらうと、晩年、親類縁者に頼まれて絵や彫刻等を描いてやった物が現存する。それを見せてもらうと、技術としては緻密に描かれているのだが、それらは、絵の堅さと言うより情感が伝わらず単なる絵としてしか見えてこない。すべてを見たことがないので断定的なことは言えないが、晩年は肝臓病や怪我の後遺症で思うままの絵や彫刻をすることが出来なくなっていたので、それが作品に現れているのかもしれない。
一方彫刻に目を転じると、これは生き生きと彫り込まれていて、絵ではやや平面的な絵を描いた松四郎だったが、彫刻の面では本領が発揮されている。掲載した写真の唐獅子は荒削りな作風に見えるが、その表情は堂々としていて実に素晴らしいものがあると思う。神社仏閣の飾りに使用される彫刻は、遠くから、あるいは見上げた状態でその作品を鑑賞することになる。従って、やや荒削りに仕上げることによって、その作品を引き立たせようという宮大工としての意図があるのではないだろうか。
彼は、近在近郷の神社仏閣はもとより、有名な山形県朝日村の注連寺建立(再建)にも携わっている。ここは山形県庄内(酒田、鶴岡周辺)にある出羽三山(羽黒山、湯殿山、月山)の即身仏信仰で高名な寺である。また、芥川賞作家で森敦の小説「月山」の舞台となったところでもある。犬の管理人も何度か訪れたことがあるが、本堂の縁側から遠く月山が望まれ、松四郎がここに寝泊まりをして仕事に従事していた頃を彷彿とさせるが、残念ながら、松四郎が彫刻などをした痕跡を見いだすことは出来なかった。
その生涯において、数々の神社仏閣を建立、それに彫刻を施し、また数多くの設計図面、絵、彫刻などを仕上げた松四郎であるが、明治44年、重陽の節句の日に61歳の生涯を終えている。生前、「隠居したら家に残す物を多く作りたい」と言っていたそうであるが、前述したような病や怪我には勝てず、当時としても享年としては若い方だったのが悔やまれる。
このようにして、我が家にはそれなりの数の作品群と、絵の師匠、増田象江の遺族から送られた絵が残ったわけだが、これに関しては、犬の管理人の祖父の功績が大きい、松四郎が死亡したとき祖父は19歳だったという。祖父は、几帳面な性格で、捨ててもいいような物まで事細かに分類して引き出しにしまっておく人だった。自分の父親の作品、あるいは作品とさえ言えないような物から、単なる書き付けのたぐいまで整理、保存してくれた。
そういう性格が幸いして、今我々は小川松四郎という人物の作品を通じ、その人となりを実感できるのである。
ただ、残念なことに彫刻師としてあるいは絵師としての手の器用さが、遺伝として少しも我々に伝わっていないのである。祖父も、絵はそれなりに上手だったことを覚えているが、直系では無いせいなのか、あるいはそういう感性とか技術といった物は遺伝より学習で覚えていく物なのかはわからない。
(注)冒頭でも、記述したように、あくまでも「犬の管理人」の私見であり、自ら思うままに参考文献を利用さ
せてもらい書きつづってみた。
参考文献 「飛鳥慕情」 小川 武 著

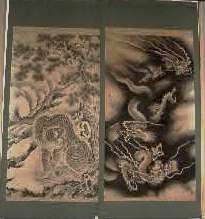


先頃見つかった出生証明書
唐獅子一対
唐獅子、一対の内の一つ
龍虎二幅
この掛け軸の場合、虎は左、竜は右になっている。方角で言えば、虎は西側にあり、竜は東側にかけられている。旧来、我が家ではこれとは逆にかけられていた。しかし風水などで言えば、青龍は東でなければいけないし、白虎は西でなければいけない。移転するに当たり、家内の考えによって昔からの掛け方を変え、上段の写真のようにかけられるようになった。果たして、いずれの掛け方が正しいのだろうか・・・?