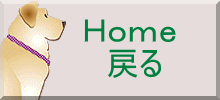ふすまについて
今回は、旧宅で百年以上も「ふすま」として使用されていたもの、そしてそれに描かれていた絵を紹介しようと思う。
※卒塔婆小町一字返歌之図
※助左右衛門父子助命嘆願之図
卒塔婆小町一字返歌之図
小野小町は承和八年(八四一)仁明天皇の宮中に仕えた。
歌人として名をなした小町の晩年を慰めるため、逢坂山中腹、蝉丸神社の裏山に住んでいる小町に陽成天皇は詠まれた歌を使者大納言行家に託し返歌をくれるよう注文した。
雲の上 ありし昔に変わらねど
見し玉だれの内やゆかしき
小町は天皇の詠まれた歌に対して優劣を競うような返歌は畏れ多いと考え、一字を変えて返歌した。
雲の上 ありし昔に変わらねど
見し玉だれの内ぞゆかしき
天皇は、このような和歌の作法があるのかと尋ねた。
小町は、これを「おうむ返しの作法」と申します。
以後、一字返歌が流行したといわれる。
犬の管理人の感想
卒塔婆小町とは
平安朝で絶世の美女と言われた小野小町であるが、晩年は老いさらばえて、だれにも相手にされず山裾に庵を結んで過ごしたという。絵の中央左が「小野小町」、中央右が天皇からの使者である。大きな松がよく描かれていて、山中の雰囲気を表現している。人物描写はやや平板な感じがするが、配置としては申し分がない。
助左エ門父子助命嘆願の図
本荘藩内越郷土谷村名主、助左エ門は藩財政建直しのため勘定吟味役として取立てられた。
江戸家老、内本一九郎と国家老、幡江右膳たちと権力争いとなり、それに巻き込まれ助左エ門と長男恵蔵に入牢打ち首の沙汰が下された。このことを知った内越郷百姓四百人余りは本荘城に向かって不穏な動きがあった。その知らせを聞いた象潟蚶満寺住職覚林は早馬を飛ばし父子の助命嘆願書状を持参したが間に合わなかった。文化十二年六月十二日であった。(本荘市通史Ⅱ)六一〇~
この絵は六十五年後、明治十三年頃、小川松四郎が描いた。
犬の管理人の感想
絵の中央に処刑の検視役を配し、左端に首切り役人と、処刑される息子の方であろうか、が配置されている。そして白馬に乗って助命嘆願書をふりかざしてくる僧侶の姿が躍動的に描かれている。緊迫した場面の中に静と動が巧に表現されている。
上記の解説文はいずれも「飛鳥慕情・・・小川武 著」に寄るが、「この絵は明治13年頃描かれた」という点にやや疑問が残る。というのは、母方の祖母の話によると、自分が小さい頃、父親(松四郎)が熱心にこのふすま絵を描いていたと聞いたことがあるからだ。祖母は明治27年の生まれであるから、この絵は少なくとも明治30年代に描かれたのではないかと推察する。