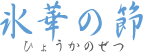|
息苦しくなって、思い切り口から気を呼び込む。満たされていくものと同時にひなびた藁の匂いが胸に広がる。そんな時、ふと我に返ってしまうことがある。 ここはどこだ、そして今はいつかと思う。薄暗い廃屋。灯りと言えば、くり抜かれた窓から差し込む天の輝きだけ。その朽ち落ちそうな内壁に絶え間なく響くふたつの息づかい。 それが…自分が彼女に囚われているからこその感情だとは、どうしても思い切ることが出来ないでいた。飲み込まれるのは怖かった。 彼女は気付いていない。情事の最中に彼がこんな物思いに耽っていることを。こうしているうちにも本能として腰が動き、彼女の中をかき混ぜる。何度となく身体を重ね、全てを知り尽くしていた。彼女が一番弱いと思われる場所も知っている。そこを丹念にこすり上げると、堪えきれずに細い悲鳴が上がった。 行き場のない想いがそのまませめの激しさに繋がる。身を起こして彼女の細い肩をぐっと掴んで固定する。藁の上にはその場しのぎの白い敷布を置いていた。それだけが人らしいただひとつのもので。あとは獣同然の絡み合いだ。そんなものなのかも知れない、身体を求め合う行為に虫も獣も人もあるものか。白い肌が熱く火照り薄桃色に色づいてくる。 彼の乳白色の肌も紅潮して、その身体全体が汗で濡れていた。滴ってくるもので手のひらが滑るほどに。濃紫の瞳で見据える。腕の下の人はもう息も絶え絶えと言う感じだ。でも行為を止めて欲しいという言葉はついになかった。彼女はいつでも彼が与えるものを全て受け止めていた。 「あ…ああっ…!!」 「…うっ…!!」
◆ ◆ ◆
燭台の明かりを淡く灯した屋内で、お互いに背を向けたまま身を清める。ひとつしかない水桶に手ぬぐいを浸しては、まだ熱い体を冷ましていく。しゅるしゅると彼女の身体を這っていく衣の音。あの白い体に今濡れた布が置かれているのだ。 考えたくなくても考えてしまう。忘れたくても忘れられない。彼女の肌の滑らかな感触も、甘い香りも。許されるのなら、このまま一晩中でも、いや、飽くまで何日でも抱きしめていたい。この廃屋から出られないようにして、ふたりだけの世界に迷い込みたい。 …そんな、馬鹿なことを。 彼が自分の中に芽生えた欲求を振り払うように首を横に振ると、壁に映った長い影も同じように揺れた。彼女の方を振り向くことも出来ずに、影だけで動向を探る。そんな癖も付いていた。自分が耐えきれないほどに彼女を欲していることを悟られたくはなかった。 「…満鹿(ミツシカ)様…」 「何だ?」 こくり、と息を飲む音がする。彼女の白い喉元が微かに動く。そこに唇を這わせながら、何度印を付けてしまおうと思ったことか。誰もの眼に晒される場所に愛し合った軌跡を付けることなど、出来るはずもなかった。少しこちらに向き直った美しい横顔が蝋燭の炎に舐め上げられる。ゆらゆらと妖艶に輝く姿。それを目で追いながら次の言葉を待った。 「日取りが…決まりましたの」 ややあって。もったいぶると言うよりは、言いたくないことを必死で口にするように彼女が話し出す。頬が強ばっていた。 …日取り? そうは思ったが即座には聞き返せなかった。 「七月の始め…わたくしの里では『氷華の節』と言う時節がございます。その時に式を挙げるので戻るようにと家から…」 滑らかに、よどみなく。決まった台詞を口にするように淡々と彼女は事実を述べた。それからまた口を閉ざしてするすると髪を梳き始めた。墨色の流れは櫛通りも良くて、油など付けなくてもいつでもしっとりと艶めかしい輝きを放っている。もっと固いものだと思っていたのに、実際に触れてみるとやわらかくて滑らかで、その豊かな流れに指がどこまでも沈んでいきそうだった。 黙りこくった横顔をしばし眺めてから、彼、満鹿はバサバサと乱暴に衣をまとい始めた。この地では男も女も衣のかたちは変わらない。色目の違いでそれを区別する。自分にはあまり似合わない黒い袴に足を突っ込んだ。 「…『氷華の節』は…」 「北の集落はここ、都よりもまた北に位置します。冬の寒さは皆様に想像も出来ないことかと思われます…そうですよね? 満鹿様は南峰のご出身でいらっしゃるもの、こんなことを申し上げても分かっていただけるか知れませんが…秋、急に寒くなると、咲いたままの花がそのまま氷の中に閉ざされてしまう現象が起こるのです。その花は氷の中に閉ざされたまま、冬を越えて夏を迎えます…そして、七月の暑くなる頃に周りの氷が溶けてその姿を気にさらすことになるのです…でも、一瞬にして暑さで枯れてしまうのですけど…」 しゅるしゅると衣擦れの音。彼女が立ち上がった。足元に脱いだかたちのままになっていた重ねを取って、静かに藁を払う。その仕草も乱雑なところもない。流れるように行っていく。 「それでも…里の者は一瞬でも時を違えて咲く花を愛おしんでその名を付けました。かの地では一年中で一番、眩しい季節なのです。氷華を髪に飾って婚礼の式を挙げた花嫁は一生幸せに暮らせると聞いておりますわ…」 自分のことを言っているのに、まるで他人事のようだ。民特有の気質なのか、彼女の性格に寄るものなのか、いつでもこの女子は穏やかにしている。気分を荒げたりすることもない。 「氷華の…節…」 「はい」 「袷が…少し、曲がっていておかしいですわ…」 「あの…髪は…?」 「いい、…このままで」 ぷいと横を向くと燭台を手にした。 「これ以上、遅くなるとまずいだろうが。早く戻った方がいい」
壊れかけたかんぬきを外すと、きしみをあげる戸を押し開ける。ひやっと春浅い冷たい気が流れ込んできて、身体がぶるっと震えた。 来たときと同じように人目を避けて山道を行く。少し山に入ったここはふたりしか知らない秘密の場所だった。 しかし。 ふたりがその様な部屋を借りることは今までなかった。このような関係を重ねていることも誰にも告げていない。気を許した同室の者にすら、それは同じことで。 北の集落と南峰の集落。漆黒の髪に闇色の瞳を持つ種族と、陽の色の髪に濃紫の瞳を持つ種族。相まみえぬとされるふたつの民だから、というのもある。…でも、それだけなら、多少の例外として認められよう。問題はもっと他にあった。 彼女――瑠璃(るり)は集落に戻れば、将来の夫と決まった男がいるのだ。幼少の頃から種族の間で決められていた婚礼、それに従うのが一族の娘としての彼女の宿命だった。
お互いにそう割り切っているからなのかも知れない。…いや、瑠璃の方が、そんな風に割り切っているからこそ自分に身体を開くのではないか。そうは思いたくないが、そう思わなくては自分の心に押さえがきかなくなる。もう、彼はギリギリのところにいるのだ。 今夜、瑠璃が決定的なひとことを口にしたとき。つとめて冷静に装いながら、心内は煮えくりかえるほどいきり立っていた。何故、その様なことを当たり前のように口にするのか。ないがしろにされている自分が情けなかった。もしも、自分のことを少しでも好いていてくれるのなら、どうしてあんな風に何気ない様子で話が出来よう。 情事の後に肌の火照りも引かないままに、他の男との婚礼のことを口にする。そんな彼女は聞いたばかりの氷漬けの花の話よりも、もっと冷たく手に届かないものに思えてならなかった。
◆ ◆ ◆
沙羅様、とはこの海底の国の全土を治める竜王・華繻那様のただ1人の御子であられ、その上に、次期竜王様であられる亜樹様のお后様。そうなれば、彼女のお産みになる御子様は次の竜王にもなる御方である。そうなるともう国全体を上げての大事であった。 満鹿がここに上がることが出来たのは偶然と偶然の重なり合いの果ての様なものだった。各集落からは出仕できる「枠」がある。満鹿の暮らしていた南峰の集落でもその定員など遙か昔から埋まっていた。が、いよいよ都に上がる時になって、急病人が出た。満鹿と同じ年頃の若者だった。それで、満鹿がその代わりに出仕することになったのだ。同じような背格好で歳が近いと言うだけで。 そんなわけで思いもかけずに、都でのお務めが始まった。満鹿が属したのは竜王様の御庭の周辺を警護する外回りの侍従の寄り所。そこで侍従見習いの任に就いた。 王族の方はもちろん、自分と同じような身分の侍従や侍女ですら、里にいた頃には見たこともないほど高級な衣をまとっている。その文様の、色彩の素晴らしいこと。織りの優美なこと。長く髪を伸ばして様々に結い上げた侍女たちは近くによると信じられないくらいいい香りがした。この地に伝わる匂い袋によるものだと後から知った。 玻璃(はり…硝子のこと)の細工物の他は大した産業もなく、鮮やかな陽の下で、おおらかに過ごす南峰で生まれ育った満鹿には、堅苦しい御館でのお務めすら新鮮に楽しかった。
◆ ◆ ◆
外歩きの時にはどうしても御館の侍女たちに目がいく。中にはほとんどの女子の出身地や名前を把握しているすごい者もいて、そう言うときは自らの博学をひけらかす。まあ、海底の民はその出身地によって、見目かたちが際だって違うので見定めるに容易い。 そして、そこに彼女もいた。ふと、そこで視線が止まる。 満鹿にとって馴染みの薄い漆黒の髪。ああ、竜王・華繻那様と同じ容貌だ、と最初に思った。もちろん下っ端の彼が竜王様に直接拝謁する光栄など望むべくもない。幸運にも遠目に拝見したお姿で、そのお美しさと堂々たる風格は消えない印象になって残っていた。 「ああ、駄目だよ。彼女は…」 「え…?」 「彼女は北の集落の、青の一族の一派の者。名前は瑠璃。ここには行儀見習いで入ったばかりだけど、里には決まった婚約者がいるそうだよ。その者、先年妻を亡くしたそうで、急遽、彼女がその後妻に入ることになったそうだ。あの集落では良くあることらしいがね…」 隣りの男も身を乗り出して話に加わる。 「もう、その男とは寝てるんだと、もっぱらの噂だよ。そうじゃなくちゃ誘惑の多い都になど、どうして出せるものか。思いがけずに年若い美しい妻を娶ることが出来ることになった男が、心配にならない訳がないじゃないか…」 「生娘で婚約者がいる、っていうなら大変だけど。もう、男を知ってるならきっと今頃は、彼女だって寂しくて仕方のない頃だろうよ。一度お手合わせ願いたいものだね」 「きっと、色々知っているよ。何しろ背の君は自分の倍も年上なんだ。男は精力が及ばなければ技巧に走るしかないだろうから…」 物陰で彼女たちに聞こえないからと言って、何とも口さがない会話だ。満鹿は腹の奥で何かが沸々するのを感じていた。 今思えば。 あの時にはもう、淡いながらも彼女への特別の想いが芽生えていたのではないだろうか? そうでなければ、あの感情は説明が付かない。侍従仲間たちの話が不快で仕方なかった。
◆ ◆ ◆
満鹿の生まれ育った里では一年中、原色の鮮やかな花が咲き乱れていた。それを思い出しながら、橙色の八重の花びらを見つめていたら、ついっと何かに引っかかった。続いて、ぱきっと何かが折れる音。 「…あれ?」
「…どうしましたか?」 誰もいないとばかり思っていた空間に。振り向くと、彼女がいた。大きく目を見開いて、辺りに墨色の髪をなびかせて。手には青い花をたくさん抱えていた。 「まあ」 「何か…代わりに結うものがありませんでしょうか…」 「いいよ、このままで戻るし…」 「いいえ、そうは行きませんわ」 「立派な殿方が、髪を下げたままで歩くなんてみっともないことです。ああ、どうにかしなくては…でも…困りましたわ…」 「ああ、そうですわ。これで、如何でしょう…?」 「それほど、華やかなものではありませんし…。 寮に戻られるまででしたら、これで充分でしょう?」 「え…いいよっ! 君の髪が解けてしまって…そんな。この紐でどうにかするから、気にしないでっ、ほんとにいいんだから…」 「そんなに真ん中から切れてしまってはもう、無理ですわ。こちらをお使いになって? さ、遠慮なさらずに…」 「あ、ありがとう…」 すっと、脇を向くと、彼女の視線を感じながら必死で髪を結おうとした。でも焦るとただですら下手な結びがもっと乱れてしまう。何度ひとまとめにした髪を片手に持って紐を回してもバサバサと落ちてしまって、収拾がつかない。 静かに黙ったまま眺めていた彼女が、とうとう観念したように小さくため息を付いた。 「…座ってくださる? 結って差し上げますから…」 「…え?…」 「まあ、やわらかいんですのね? 南峰の亜麻の髪はもっと硬いのかと思っておりましたのに…」 「せっかく、こんなお美しい髪なのですから、もっと綺麗になさって。もったいないですわ…」 その言葉には正直驚いた。漆黒の滑らかな髪を持つ北の民は、南峰の亜麻の髪を疎んじているのだと聞いていたから。軽々しくて、良くないと。そうだとばかり思っていたので、意外だった。 きりきりと少し強く引かれて、すっきりまとめ上げられる。綺麗に結び終えると、彼女はほっと安堵の息を付いた。 「…素敵ですわ、満鹿様…」 「…え?」 「君、何で…俺の名前、知ってるの?」 たどたどしく問いかけると、彼女はにっこりと微笑んだ。 「君、じゃありませんわ。わたくしは…瑠璃と申します。南所で若姫様のお世話をさせていただいておりますの」 そこまで告げると、自分のもう片方の飾り結びも解く。長い帯が気の流れに舞い上がる。幾重にも折り重なった墨色の帯が、たとえようのないほど美しかった。それから、元のように花の束を抱える。 「侍女の寄り所では、あなた様のお名前が頻繁に囁かれますの。聞く気がなくても耳に飛び込んで参りますわ…楽の名手で…特に横笛がお上手で…。すらりと上背があって、月明かりよりも綺麗な髪をなさっていらっしゃるって」 当たり前のことなのかも知れない。でも初めての経験だったから、驚いたし、嬉しかった。満鹿は慌てて立ち上がると、彼女の後を追った。 「あの…瑠璃さんっ!」 「…はい?」 「その花、持つよっ! 重そうだから…! で、あのっ…もし良かったら、今度、もっと上の方まで散策に行かない!?」 後になって考えると、何とも陳腐な誘いだった。年若い女子を山歩きに誘うなんて。せめて花の綺麗な野に案内するくらいの機転が欲しかった。 「…え? あの…」 「ええ、わたくしで良ろしかったら。喜んで…」 天女の様な微笑みだった。本当に天界の地から舞い降りた人のように…それでも、その時。瑠璃はしっかりと満鹿の目の前に存在していた。
|