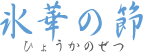|
もしかすると、約束が果たされるとは思っていなかったのかも知れない。 足早にその場所に向かい、樹の影に牡丹色の重ねの袖を見つけたとき、嬉しいと言うよりは不思議な感じがした。本当に彼女が来たのだ。こちらの気配に気付いたのだろう、艶やかな黒髪を辺りに揺らしながらゆっくりと振り返る。口元に浮かぶ淡い笑み。初夏の陽ざしが他に人通りのない空間を照らし出していた。
◆ ◆ ◆
ふたりの休みの日を照らし合わせて、それが一致する一番近い日を選んだ。もう夢中で。瑠璃の承諾の微笑みを見たところからは夢中で。強引に話をまとめていた気がする。西の通用門までの道のりはとても長いようにも短いようにも感じられた。
竜王様はこの海底の全土を支配する者。「陸」の人間とあまり変わることのない外見の海底人がこうして深い水底で気を取り込み呼吸し、生活できるのは竜王様御自らが張っていらっしゃる「結界」があるからに他ならない。高貴な王族の血筋を引く者が幼き頃からの修練によって身に付けるもの。 外回りの侍従は「お庭番」と言う夜間の寝ずの番もある。東所や南所の御館の表の庭で一晩中起きて、不審な点はないか番をするのだ。まあ、これも他の警護と同じように名前は堅苦しくてもその仕事内容は簡単な者であった。
ごろりと寝台に横たわる。土間に敷物を敷いていた南峰の暮らしとは何もかもが異なる。里にいた頃は髪も結ったり結わなかったり。結うとしても宮仕えのように高い場所ではない。うなじのところで軽く麻紐で結ぶだけだ。だからきつく結われた髪は堅苦しくて、いつも部屋に戻るなり解いてしまっていた。 でも、今日は髪をくくった紐を解く気になれない。あの白い指が髪の間に入り込みまとめ上げてくれたのだ。地肌に何とも滑らかな感触が残っている。解くのはもったいなかった。 じわじわと感動が湧き上がってくる。仲間たちと眺めた風景で目に飛び込んできた異郷の娘。ひとめで心を奪われていた美しい人と直接話をすることが出来たのだ。しかも皆が言っていたような軽々しさもふてぶてしさもない。まるでほころんだばかりのつぼみのように、淡くて愛らしかった。 ころころと軽やかな笑い声、小首を傾げて見上げる瞳。汚れのないまっすぐな色が胸に迫ってくるようだった。あの人が、本当に自分とまた会ってくれるのだろうか。口約束だ、すっぽかされるかも知れない。婚約者がいながら、他の男の誘いに乗ることなどあるのだろうか。他でもない、規律正しい「北の集落」の女子が。 …夢を見ていたのかも知れない。そんな気がしてきた。あまり期待すると、落胆が大きくなるかも知れない。来なくても構わない、来るか来ないかなんて、分かりっこない。何度も自分に言い聞かせた。このことは誰にも内密におこうと思った。
待ち合わせは西の通用門の出たところ、三本杉の向こうだった。狩りや花摘みでもなければ行かないような人通りのない場所だ。そこを彼女が指定してきたとき、ああそうかという落胆の気持ちが湧き出た。自分に必死にすがられて、断れなかっただけだろう。当惑した顔が脳裏をよぎる。 寝台の上で寝返りを打って、瞳を閉じる。それなのに彼女の笑顔がぱあっと浮かんでくるのだ。胸がひりひりと痛んだ。
◆ ◆ ◆
「いいえ」 「わたくしが、だいぶ早く着いてしまったんですの。お気になさらないで」 改めて見つめる。小さな輪郭の中の整った顔立ち。うっすらと綺麗に塗られた化粧。白いきめの細かい肌にそのまま吸い付いた白粉、花色の紅。それはあでやかな南峰の手法とはかなり違っていた。種族によって髪の色や顔立ちが違うのだからそれも当然なのだろう。 「…さ、参りましょうか。でも、どこにいらっしゃるんですの?」 「…え、あ…、うん…」 「ご、ごめんっ、俺、こっちに来てまだ間もなくて…実は良く知らないんだ、この地のこと」 「…まあ」 「実はわたくしも。都のことはよく分かりませんの、でも山歩きは好きですわ。故郷を思い出しますもの。竜王様の御領地はわたくしの生まれ育った地と良く似ておりますの…せっかくのお天気ですから、当てもなく歩きましょうか?」 「あ…、う、うんっ! そうしようっ!」
さらさらと流れる小川を超えて、小高い丘に出る。視界一面に広がる色とりどりの花の絨毯を眺めながら草の上に腰掛けて一服した。ふんわりとまた良い香りがする。 「…どうしました?」 「え? …ええと…」 どこまでもさらりと何気なく。そう言う巧みな会話術が女子の心を掴むのだと仲間たちがまことしやかに語り合っていた。お務めの最中も手が空けば、女子の話になってしまう。独り身の侍従は想い人を手に入れようと必死なのだ。 何しろ連れだって歩くカップルが異様に多い土地柄。更に南所では次期竜王の亜樹様とその正妃様の沙羅様が仲睦まじくされている。お上の方がそんな感じだとお仕えする者も色めき立ってしまうのだ。 でも満鹿は女子のことなどよく分からない。どんな話をしたら喜んでくれるのかも思いつかない。ここに来るまでの道のりもぽつぽつと故郷の風景の話をするくらいだった。それでも瑠璃はそんな話を真面目に聞いてくれる。 「…君、すごくいい匂いがする。髪に何か特別の油でも使っているの?」 …ああ、これでは女子慣れしていないのがバレバレじゃないか。情けないったらない。瑠璃はそんな満鹿の言葉に一瞬大きく目を見開いたが、すぐにふうっと微笑んだ。そして胸元の袷から何やら小さな布袋を出す。彼女の小さな手のひらにちょこんと乗る、淡い桜色の袋だった。口元を赤い紐できゅっとくくってある。それを満鹿の手の上に乗せてくれた。 「ご存じありませんか? …匂い袋です」 へえ、とまじまじと見つめてしまう。着物用の衣の残りで作られたのであろう袋。そこからほのかに匂う甘い香り。香の袋のことを聞いたことはあったが、こうして実際に見たのは初めてだった。満鹿の生まれ育った地にはこのようなものを身に付ける習慣はなかったから。 「北の集落の…我が『青の一族』は香の調合を手がける者として、代々竜王様のお仕えしております。耕地の仕事は殿方の行うことが多いのですが、その精製や調合はわたくしども女子もお手伝いいたします。香を実際に用いることが出来るのは王族の方々のみですが…庶民はこうして匂い袋を楽しむんですの…」 「これは荘寿(そうじゅ)の実から取れる香で…先々代の竜王様がご愛用になっていらっしゃったものだそうです…」 荘寿の実、と言うのは知らないが、耕地なら舞夕花(まゆか)の花の頃に行ったことがある。竜王様の御領地、東の御庭の向こうにそれは広がっていた。もちろんお務めの一環だったが、畑の中に巡らせされた足場を歩いていくと一面の花から薫ってくる強烈な香りにクラクラと来た。 きっちりと四角く切り込まれた耕地を眺めているだけで、北の集落の民の潔癖さが見えてくるようだった。南峰は本当に畑か荒れ野か分からないようなところを焼いて作物を作っていたので、何だか不思議な気がする。逸れも躍起になって栽培するわけもなく、何となく種を蒔いて、収穫できれば食する。それが上手く行かなければ、山菜を採ったり、木の実を拾ったり。川魚を捕まえて来ることもあった。 そんな話をすると、今度は瑠璃が不思議そうな顔をする。肉と言えば貝が主で、後は野菜と木の実のささやかな食事をしている北の集落。満鹿が実際に携わった、大きな獣を捕まえてきてバラし干し肉にする話などは本当に驚いていた。 育った環境も置かれた立場も全く異なる。満鹿は瑠璃の婚約者のことを知っていてどうしても訊ねられなかったし、彼女から切り出してくることもなかった。当たり前の会話をしているだけで、時は瞬く間に過ぎていく。心地よい時間はあっと言う間に終わりを告げていた。 自分を見上げてやわらかく微笑む人ともう一度会いたくてたまらない。このまま二度とふたりで会えなかったら嫌だ。もう一度だけ、こんな時間を持ちたい。一度だけ会えばそれでいいと思ったのに、我慢が出来なくなった。別れ際、次の約束を取り付けていた。瑠璃もちゃんとそれに応えてくれた。
◆ ◆ ◆
仲間の侍従は次々に女子を口説いて行く。中には付き合ってひとつきでもう結婚を決めてしまった者すらいる。まあ、所帯を持つ平均的な年齢は男子が17,8で女子が15,6…そうなると宮仕えをしている侍従や侍女は皆が結婚適齢期と言っても良かったかも知れない。
「…あ、うん。そうだけど…」 「わたくしの同室は柚羽様ですの。余市様と同郷のご出身なんですって、よくお名前を伺うから…」 「ああ、そうか」 「これは、内緒のお話ですけど」 「柚羽様は余市様のことが好いていらっしゃる、わたくしはそう思っておりますの」 「え…?」 「そうか…なあ?」 竜王様の御館の侍女たちはびっくりするくらい積極的だ。余市も自分も向こうから声をかけられることがある。最初はびっくりしたが、だんだん慣れてきた。立ち話くらいだったらする。余市などはそう言うことすら面倒くさそうだったが。女子には興味もないのかなと思っていた。さもなくば、里にもう決まった女子がいるのかと。 自分が色恋沙汰に縁がないからと言って、余市までがそうだとは限らない。でもどうしても自分の視点でしか物事を見ることが出来ないのだ。正直、浮かれまくっている侍従たちの中で、ふたりは少し浮いていた。 「柚さんがそう言ったの?」 「いいえ」 「柚羽様はそんなことを軽々しく仰らないですわ。でも、わたくしには分かるんです。とても良く…」 「柚羽様、余市様から頂いた飾り物をそれはそれは大切にしてらっしゃって。小箱一杯にあるんですわよ。それをおひとりで並べては眺めているの、わたくし気付いておりますもの…」 そんな風に呟く瑠璃が何を想っているのか、気になった。もしかしたら、遠き里の婚約者に想いを馳せているのではないだろうか? 彼女を待つ男のことを。そう思ったら、胸が今までにないほどキリキリと痛み出した。それを悟られないように必死になっていたら、その後の時間は何を話したのかもよく分からなかった。
◆ ◆ ◆
それからしばらくしたある日、表の侍従たちが集まる寄り所に自分を訪ねてきた女子がいた。いくら積極的な竜王様の御館の侍女と言っても、単身で寄り所までやってくる者は珍しい。仲間たちに冷やかされながら、戸口まで出ていくと黒い髪の女子がいた。顔は見たことがある。でも黒い髪、瑠璃と同じ地の出身の者であっても何だか異質な者の様に思えた。 「単刀直入に申し上げるわ。満鹿様は今、お付き合いなさっている方がいらっしゃるの?」 「あ…いや…」 「そうでしょうね、そんな話もありませんし。でも、それならどうして特定の女子をお決めにならないんですの? 里にそう言う人がいらっしゃるのか、それとも…誰か想い人でも?」 「…え?」 満鹿が黙りこくっていたので、彼女の方がまた言葉を続けた。 「私、存じ上げておりますのよ? 満鹿様は今までに何人もの女子から誘いをかけられて、無下にお断りになっていらっしゃるって。何故ですの? …よもや、女子がお嫌いなのではないでしょうね。中には余市様との仲を疑う者もありますのよ…?」 その言葉にはさすがにぎょっとして目を剥いた。 「なっ…何でっ…!! ちょっと、待ってくれよ。そんなのっ…!!」 「そうじゃないと仰るのでしたら、私と付き合ってくださらない? そんな馬鹿馬鹿しい噂など蹴散らして差し上げましょうよ…?」
◆ ◆ ◆
その気の流れの如く。その日の満鹿は沈んでいた。傍らを歩く瑠璃が何度も心配そうにこちらを覗き込んでいるのが分かる。優しい瞳に見つめられても気は晴れなかった。
「…満鹿様…?」 「何やら…少し流れがおかしいようですわ、…ご覧になって…」 「…何? これ…」 「多分…野分の荒れですわ。今に強い流れが来ると思います…」 天を仰げば禍々しい色に塗り替えられている。先ほどまでは青い色だったのに。今は灰色に黄色が混ざったような恐ろしい顔色に変わっている。何か大変なことが起こるのだ。この周囲の風景からも瑠璃の表情からもそれが分かった。 「そんな…!! 早く戻らなくては…!?」 そう言い終わる前にゴウッと気が唸り、ふたりに襲いかかってきた。まるで生きているかのようにふたりの存在を目指して強い流れが起こる。咄嗟に瑠璃を庇う。やわらかな花の香を無意識のうちに抱き寄せていた。 流れに背を向けて、必死で目を凝らす。視線の端に茶色っぽいものが見えた。四角い、もしかしたら、少しの間この荒れをしのぐことが出来るのだろうか…? 片手で瑠璃を庇いながらゆるゆると進んでいくと、そこは山裾の廃屋だった。ぼろぼろな外装だったが、外にいるよりはマシかも知れない。立て付けの悪い戸を開く。ひなびた香りがした。収穫した藁をたくさん積んである物置だったのだ。それでも人間が座る場所くらいは残されていた。
「…大丈夫? 瑠璃さん…?」 満鹿が自分の重ねを脱いで藁の上に敷く。そこに座るように促すと、彼女は申し訳なさそうに満鹿から離れて端の方に腰を下ろした。そして、乱れた髪を手櫛でそっと整える。その指先がまだ小刻みに震えていた。痛々しいほどだった。 「…申し訳ございません。わたくしがきちんと注意していればこんなことには…」 「ううん、瑠璃さんのせいじゃないから…」
あの女子が手にしていた包みの中身は分かっていた。あの大きさは衣だ、多分彼女自身が仕立てたものだろう。女子が男に衣を贈るのは一種の求婚の意思表示だ。衣の仕立ては妻の役目とされている。だから、これからあなたの衣のお世話をさせてください、と言う気持ちが込められているのだ。でも、それを受け取ることなど出来なかった。 それを知ったとき、満鹿が最初に思ったのは瑠璃のことだった。自分のひどい噂を耳にして、一体どうするのだろう。軽蔑してしまうかも知れない、もう会ってくれないかも知れない。そう思うと口惜しくて仕方がなかった。 そして、同時に。 どんなに深く瑠璃を思っていたか、その自分の気持ちに気付いてしまったのだ。あの女子の話しぶりから見て、自分たちのことは知られていない。知られてはならないことだと思っていた。 もう会うのはやめようと何度も思った。それでも別れ際には次の約束をしてしまう。いつかは里に戻って嫁いでしまうと分かっていても、それでも止められないのだ。今この瞬間に、自分に微笑んでくれる瑠璃が大切だった。 何故、瑠璃は他の男のものなのだろう。彼女は時々里に戻る。一日歩けば辿り着ける近い距離なので、三日休みが貰えれば帰ることが出来るのだ。そして、戻れば男に会うのだろうか? その胸に抱かれるのだろうか…そして、男は瑠璃の微笑みを見つめるのだろうか?
今、腕を伸ばせば届く距離で、瑠璃が震えている。寒いのか、恐ろしいのか。今にも崩れ落ちそうな廃屋に打ち付ける気の流れ。薄い壁がかろうじてふたりを守ってくれてはいるが、いつ崩れてしまうかも知れない。 「…瑠璃さん…」 次の瞬間。 満鹿の身体が跳ねた。飛びかかるように瑠璃に抱きついて、抱きすくめる。柔らかな身体を必死で抱いた。甘くてうっとりする花の香り。小さく震えながら、それでも彼女が自分にすり寄ってきてくれるような気がした。滑らかな黒い髪、それを一束掴んで握りしめる。 女子のぬくもりは初めてだった。そう言う経験は里にいる頃はもちろん、この地に来てからもなかった。場末にある遊女小屋にも行ったことがない。馬鹿馬鹿しいと思われようが、どうしてもそう言う気持ちになれなかった。口惜しくて、愛おしくて。腕の中にいる人を生まれて初めて欲しいと思った。体中の血液がぎゅうっと頭に流れ込んでくる。 夢中で唇を重ね、強く吸う。彼女の甘い唾液ごと、飲み込んでいく。そして…その後は、もう自分を止めることなど出来なかった。 どうして、どうして他の男のものなのだ。どうしてっ…!! 頭の中でそんな想いがばちばちとはじける。衣をはぎ取り、白い柔肌に吸い付き、味わう。怒りにまかせて貫いて、何度も何度も突き立てた。その行為の方法など、耳で聞いた知識でしかなかった。実際にそう言う状況になったとき、手順が分からなかったらどうしようとも思っていた。でも本能のままに動けば何も恐れることはなかった。 突然の満鹿の行動に驚いたのか、抵抗も忘れて瑠璃は身を任せている。額に脂汗を浮かべて、必死に声を殺していた。それでも時々、悲鳴のような細い声が上がる。墨色の髪が辺りに漂って2人を巻き込んでいく。 彼女の中に欲望の全てを吐き出して、その後もしばらくは呼吸を整えるだけで精一杯だった。
いつか、外の荒れる音がなくなっていた。戸口の隙間から赤い夕暮れの光が漏れる。その時になって、ようやく我に返った。 「あ…!?」 「ち、ちょっと待ってっ!! どうしてっ…、どうして、瑠璃さん…!?」 「何でっ!! 何で初めてなんだよっ!! 瑠璃さん、男がいるんだろう…!?」 瑠璃は。ハッとして瞳を大きく見開いた。それから唇を噛みしめると、満鹿の腕を払って起きあがる。彼女のものとは思えない、低いかすれた声が上がる。 「…あの方とは…わたくし、お目にかかったこともございませんの。ずっと長いこと遠くの地で兵役に携わっていらっしゃって。お兄様である跡取り様が流行病で亡くなったことで、急にこちらに戻されることに相成ったのです…本当でしたら、わたくしは跡取り様の妻になるはずだったのですが…」 そこで言葉は途切れた。しばらくの間、彼女が身支度を整える衣擦れの音だけが、部屋に響き渡る。やがて、すっかり衣を整えてこちらを振り向いた彼女はいつもと変わらない穏やかな笑みを浮かべていた。 「さあ、早く御支度をなさって。夕餉までに戻らないと皆様、心配されますわ…」 愛し合った形跡をぬぐい取った手ぬぐいを手に、呆然としていた満鹿は、もはや何の言葉も思いつかなかった。
|