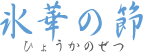|
とんでもないことをしてしまった。そのことだけが確かだった。
夫となる人が決まっている女子(おなご)である。そんな者が他の男とまみえるなどあってはならないことだ。それがもし知れたら、どんな制裁が待っているのか想像も付かない。 …しかし。満鹿はただ人である。とてもそんなことを出来る身分ではない。南峰の里にいる自分の父の妻は満鹿の母ひとりだ。片田舎のしがない農村の生まれだ。 対して瑠璃は。格式と秩序をことのほか重んじる「北の集落」の出身。その一派、「青の一族」の生まれだ。幼き頃から夫となる人も決まっている、それは一族の存続のために必要なことだった。簡単に覆せることではない。それは分かっていた、そんなことは承知していた。
それなのに…どうして。
このことがもしも公のことになれば、ただでは済まないだろう。満鹿のみならず、無理矢理に身体を奪われた瑠璃の方も罰せられる可能性がある。「北の集落」の法はとても重いと聞いている。想像しただけで恐ろしかった。 戻り道は無言であった。何か言葉を発すれば、気が狂ってしまったかも知れない。悶々と腹の中で思いを巡らしていた。もしも、瑠璃がこの事実を誰かに話したら、どうなってしまうのだろう。 さくさくと自分の後ろを歩いてくる人の足音は変わらずに軽やかで。廃屋で身支度を終えて満鹿を見上げてきた表情もいつもと変わらなかった。男と初めて契った後の恥じらいすらない。全てが夢であったように自然だった。それでも全てが事実であることは隠しようもない。 頭がぼうっとして、どこをどう歩いたかも分からない。別れ際に次の約束も出来なかった。そんなことを言える立場じゃなかった、瑠璃はもう二度と会ってくれるわけはない。あのように乱暴を働く男だと分かってしまって、どうして会いに来るだろう。一度だけの過ちに留まらず、不義を重ねればそれだけ罪が重くなる。このまま里に戻ってしまうかも知れない。 行くなとも、もう一度会ってくれとも言えなかった。そんな情けない男を瑠璃は綺麗な笑顔で見送ってくれた。そのあまりに変わらない姿が切なくて胸が痛んだ。
◆ ◆ ◆
…眠れなかった。申し訳ない気持ちでいっぱいだった。どうにか、もう一度会って謝りたい。あんなことをするつもりはなかったのだ、ただ魔が差しただけだと…でも。 どうして忘れることが出来よう。あの目眩がするほどの幸福な時間を。その上、瑠璃はまだ男を知ってはいなかったのだ。侍従たちの噂など何の根拠のないものでしかなかった。清らかなその姿と同様に何者にも汚されていない無垢な存在。それを抱きしめてしまったのだ、その身体を思いのままに味わって、自分を刻みつけた。 …否。彼女に限ってそんな。…でも。
一晩考えて、次の朝、いつもの待ち合わせの杉に細帯を結んだ。 予定が決まらずに次の約束が出来ないままに別れたときの合図として、2人が用いていた秘密のやりとりだった。赤い紐を結んでいるから午後からの。3本だから、3日後。朝が来るたびに紐をほどきに行き、それがなくなった日の午後に、また、その場所に出掛けていった。
◆ ◆ ◆
「…瑠璃さん…」 「如何…致しました?」 会ったら、この前のことを謝って、そのまま戻る予定だった。それなのに、瑠璃の姿を見た途端、身体が言うことを聞かなくなった。満鹿はもう、ずんずんとひとつの場所を目指して歩き出していた。 …信じられなかった。でも、一度味わってしまった果実はたとえ禁断のものであっても忘れられない。もう一度だけ会いたいと思っていた頃と同じように、もう一度だけこの腕に抱きしめたい、しっかりと味わいたいと思ってしまう。そんな彼の後ろを瑠璃はいつもと変わらない足取りで付いてきた。 ぽつんぽつんと言葉を交わしながら、自分がとても緊張しているのが分かった。受け答えをする声が情けないくらい震えている。廃屋の前まで来る。今日はすっきりとした爽やかな陽気だった。 「…あの、何か。お忘れ物でしょうか? ここに…」 瑠璃の言葉には答えず、すっと引き戸を開けた。そして、彼女の腕を取ると、強い力で中に連れ込んだ。藁の上に倒れ込む。何かを語ろうとした唇を塞ぎ、袴の帯を解く。衣に隠された花が現れる。他の誰にもさらしたことのないやわらかくて白い肌が満鹿を誘う。夢中で口を吸いながら、豊かな胸元に手を這わせる。頂が早くも固くしこっているのを知ると、じわじわと感情が溢れてきた。
◆ ◆ ◆
山間の地は白い霜に覆われて廃屋のある山の裾野も白い絨毯が敷き詰められていた。素足の草履では足が凍えて凍傷にでもなりそうだ。遙か向こうにある建物までは到底辿り着けそうにない。今日は無理かと諦めかけたとき、藁靴を出してくれたのは瑠璃だった。 「わたくしは冬道には慣れております。満鹿様がお使いになって? わたくしのものですが、たっぷりと作られておりますので、殿方でも使えると思いますの…」 足を入れるとギリギリでどうにか収まった。丈が長く膝下まで来る。足全体を覆うことができそうだ。 「…あの、瑠璃さんは…」 満鹿の声に瑠璃はにっこりと微笑んで言った。 「わたくしは満鹿様の後を行きますわ。足跡で踏み固めて、道を作ってくださいませ。滑りやすいですから、お気を付け下さいませ…」 そんなこと、出来るものかと思った。瑠璃を素足の草履履きで歩かせて、自分だけ楽をするなんて。満鹿は黙ったまま、燭台を瑠璃に差し出した。瑠璃は意味も分からずにそれを受け取る。その身体ごと、ふんわりと抱き上げた。 「きゃっ…!!」 霜は夜の気でカチカチに凍っていた。気の中に含まれる水分の粒が頬に当たる。つるつると滑るその上を慎重に歩いた。腕の中の人が温かくて、胸が高鳴る。どうして、この人は自分と会ってくれるのだろう。何も言わずに抱かれるのだろう。何度身体を重ねても、それを訊ねることは出来なかった。
◆ ◆ ◆
小耳に挟んだにわか知識により、最後に女子の体の中に自分を吐き出さなければその可能性が極めて低くなることを知った。完全ではないらしい、でもその様にして受胎の調節をしているカップルもいるらしい。
一方、瑠璃の側には満鹿を受け入れることが出来ない時期がある。大抵、七日に一度くらいの逢瀬だったから、それに当たることは月にあっても一度。初めてその日になってしまったとき、いつものように組み敷いて我がものにしようとする満鹿に対し、彼女が信じられぬほど強く抵抗した。満鹿は最初、どういうことなのか分からずに混乱した。とうとう愛想を尽かされたかとすら思った。青ざめて身体を起こした彼女は、苛立った表情の満鹿にすまなそうに言った。 「…申し訳、ございません。今宵は…その…」 「何だよっ!! そうならそうと早く言ってくれればいいのにっ!! わざわざこんなところまで歩いてきて…」 「すみません、…すみません、あの…っ!」 「…え? おいっ! 何するんだよっ! やめろよっ…」 慌てふためく彼の言葉など聞かず、袴を膝まで下ろすと、次に下着の紐に手をかけた。 「やめろってばっ! 瑠璃さんっ…」 「…お慰めさせてくださいませ。それくらいしか、今宵は出来ません故…」 その表情のあまりにも完成された美しさに息を飲んだ。彼女の中の真実がその姿を際立たせているのか、それは分からない。でも、慌てて気を取り直して叫んだ。 「瑠璃さんに…そんな遊び女みたいなことさせられないよっ。怒鳴ったのは悪かったから、本当に変な気を起こさないで――」 最後まで言葉を繋げることは出来なかった。少し満鹿の束縛が離れた隙に、瑠璃が彼自身をそっと握りしめてきたのだ。駄目だと思いつつも走り抜ける快感に、我を忘れてしまった。 「駄目だよっ…瑠璃さんっ…!!」 瑠璃は手を上下に器用に動かしながら、先端に唇を這わせてきた。信じられないほどの緻密な快感が背筋を駆け抜ける。ううっと呻いて、のけぞった。それに反応するように瑠璃は口の中にずずっと満鹿を取り込む。舌を使いながらそっと吸い上げて取り戻す。彼女の体の中に己を沈めたときとは全く異質の快感に溺れてしまう。 裏側に舌を這わせて、上下させる。男にとってもっとも弱い部分のひとつではあるが、そう言うことに長けているとは到底思えない瑠璃がどうしてこんなに良く知っているのだろう? 信じられなかった。慣れている、と言うよりは必死な感じで満鹿を翻弄する。ふと見上げると瞼を閉じた彼女の表情がどこまでも女子のものに見えた。袋を丹念に手のひらで転がされ、自身は口を使って愛されていく。若い満鹿にはすぐに限界が来てしまった。 「…うっ、うわっ――!!」 瑠璃の肩を押さえて引き剥がそうとしたが、間に合わなかった。満鹿はそのまま瑠璃の口の中ではじけていた。 「瑠璃さんっ…、駄目だっ…離してっ!!」 「ああ、…駄目だから…」 満鹿は振るえる腕を伸ばした。自分の傍らにいて、むせ込んでいる人を必死で抱きすくめる。申し訳なくて、それなのに愛おしくて、気が狂ってしまいそうだった。 女子にとって、あまり好む行為でないことは知っていた。それをして欲しくても、なかなか女性側が同意してくれず、仕方なく遊女小屋に行く男も少なくない。女子の身体で味わうのとは全く違った快感があるのだ。でもそれは性差というもので、埋められない溝だ。
◆ ◆ ◆
そう言う行為であること自体が、どうかしている。隠し立てをしなければならない関係をどうして続けるのだろう? 瑠璃はどうして拒まないのだろう? 自分はどうして我慢ならないのだろう。
◆ ◆ ◆
正月明けにひとつきほどの暇を貰い、里に戻った。満鹿の里は南峰の集落の中でも更に奥まったところにある。それだけの休みを貰ったところで、実は移動する時間の方が長いくらいだった。その道すがら、心の中にあったのはただ瑠璃のことであった。
別れるとき、次の約束は出来なかった。瑠璃も新年は里に戻る。そうすれば、婚約者と会うこともあるだろう。婚礼の日取りが決まるかも知れない。…もう、戻ってこないかも知れない。 今日は都へと立つ日、集落の中心部では市が立っていた。そこをぶらぶらと歩く。里に戻るに際して、今までの給金を持っていったが、そのほとんどは家に置いてきた。今、満鹿の懐にあるのは旅路ギリギリの宿泊費だ。それほど贅沢を都ですることもなく、必要以上の金銭は必要なかった。
真冬だというのに汗をまき散らしながら、必死で求め合う。瑠璃が反応する場所を丹念にこすり上げて、悦ばせてやる。他の男にここが分かるものか、と、妙な対抗意識が芽生えてしまう。しっとりした身体を抱きすくめると、乾いていた心が満たされていくのを感じた。 「…これを、わたくしに…?」 「宜しいんですの…? 本当に?」
両手にしっかりと抱きかかえてそれを持ち帰った彼女は、次から逢瀬の時には必ずその紅を付けてきた。満鹿は誰も通らなくなった夜道でふるさとの香のする唇を必死で吸った。南峰の紅を付けているうちに彼女が南峰の女子になってしまえばいいのに。漆黒の髪も瞳も装いを変えて、ついでに古くさい慣習も捨てて。満鹿を愛する女子になってしまえばいいのに…。 ありもしないこと、出来もしないことだった。いつか来る別れを恐れながら、それでも関係を断ち切ることは出来なかった。まるでこの日々春めいてくる時節に自分たちだけが永遠の冬に向かって歩いているような。重々しい空気が更にふたりをせき立てていた。
◆ ◆ ◆
淡々と他人事のようにそれを告げた彼女の声。何と言って反応したらいいのかも分からない。心のままに行かないでくれと懇願すれば、彼女はどんなに戸惑って困り果てるだろう。最初の時から、彼女に男がいることは知っていたのだ。口が滑ってそう告げていたし。だから割り切っている男にならなくてはと思った。 山間の気が一瞬にして凍り付いて、咲き誇る花ですら閉じこめてしまう…そんなこと、いくら想像しても信じられなかった。「霜が降りる」と言うことすら南峰の集落にはないことだった。厚い打ち掛け(重ねの表地と裏地の間に真綿を入れた冬の衣)を着なければならないほど冷え込むことはない。常緑樹に囲まれて、明るい輝きの中で1年の全てを過ごす。 瑠璃は。そんな満鹿の里のことなど知らぬままに一生を終えるのだろう。真っ直ぐに伸びた轍の上を進むことに何の疑問も抱かずに。それを翻すことは出来ないのか。どうにかして自分だけのものにしてしまうことは…。
どうして夢見ずにいられるだろうか。瑠璃と共に過ごす人生を。彼女を妻にして、子を作り、ささやかな愛に満ちた空間を作るのがどうして許させぬことなのだろうか? 温かい居室で彼女が待っていてくれることも、温かい夕餉を囲む食卓も、…抱き合ったまま朝を迎えるしとねも。みんなみんな当たり前のことのように手に取るように思い描けるのに。 もしも、自分が彼女の実家を納得させるほどの高貴な生まれだったら。彼女を欲しいままに出来る身分だったら…何度それを考えたことだろう。馬鹿な世迷いごとであると知りながら。
…断ち切らなければならないのだ。お互いのために…何よりも彼女のために。でも、どうしてそんなことが出来よう。正月にひとつき離れて暮らしただけで、気が狂いそうだったのに。この先の長い日々を彼女を感じずにどうして生きながらえることが出来るのか。 おしまいは近い。そこまで来ている、手を伸ばせば届くほどに。
◆ ◆ ◆
宴の喧噪が手に取るように分かった。明日は前々から決まっていた西の地への遠征団が出立する。かの地で起こっている村長と民の暴動を抑えに行くのだ。三月も半年もかかるとすら言われている。今宵は竜王様が御自ら主催された宴に団の者たちが招かれていた。 いつものように、彼女を抱いた。…否、いつもとはだいぶ違うような気もした。あの朽ち落ちそうな廃屋ではない。人気の消えた男子寮。満鹿の部屋だった。
出立の前の晩である。ゆっくり休まねばならない。そんなことは誰でも知っているが、あまたの遠征団の誰もがそれを守っていないことは明らかだった。一夜宿はずっと前から予約で埋まっていて、キャンセル待ちの札まで出たという。 でも余市がその様に過ごすとは思えなかった。そう言えばこの半月ほど、彼は元気がなかった。以前から大人しやかな寡黙な青年だったが、それが際立っていた。遠征団の団長に任ぜられて、緊張しているのかも知れない。でも…あんなに沈んでいてお務めが出来るのか? 心配ではあったが、それを気遣う余裕はなかった。満鹿の方も自分のことだけで手一杯だったのだ。 余市が戻らないと聞いて、満鹿は宴の給仕をしていた瑠璃をここに呼んだ。初めて足を踏み入れる男子寮に戸惑いながらも、彼女はいつもと同様、満鹿の言うがままに従った。男所帯で飾り気のない殺風景な部屋。でも、ふたりきりになるとそこは閉ざされた空間だった。まるで本当に所帯を持ったようだ。 自分の寝台に腰をかけると、手招きで彼女を呼ぶ。決して自分から求めてくるような淫らな態度に出る女子ではなかった。でも誘いかければ、大人しく応じてくれる。全てをはぎ取り、何も持たない姿で抱き合う。そこには一族も集落もなかった。あるのはふたつの身体だけ。寝台をきしませる重み。 思いのままに愛し合えない。その不完全燃焼はここでも同じだった。体裁を整えて、睦み合っても、触れ合えない部分がある。どこまでも平行線だ。彼女を貫いて、どうにかのぼりつめさせようと我を忘れて腰を動かす。乱暴な動きに、瑠璃の腰が大きくうねる。壊してしまいたい、身体ごと、心まで。 「瑠璃…、瑠璃っ!」 それを知ってか、腰に伸びてくる腕。やっとの思いで振り切ると、彼女の中から飛び出した。白い液体が滑らかな肌に注がれていく。呆然とそれを眺めていた。
そう言いながら、背を向けて身体を清めている。今日はちゃんと湯桶を用意した。本当に初めて人らしい営みを行い、人らしく後始末する。小袖を肩に掛けているので、その身体は確認できない。愛し合った直後の火照った肌。玉の汗。いつもよりも彼女の香りが深くて、思わず誘い込まれてしまう。胸に顔を埋めて、閉ざされた世界に入り込みたいとすら思うのだ。 「…そのことなんだけど…」 「あの、俺…志願したんだ。明日は皆と一緒に出立する。侍従長様と竜王様に許可を頂いたんだ」 「え…?」 微かな衣擦れの音。彼女が波打つように動揺したことを耳で確かめる。それを頼みに、一気に言葉を吐きだした。 「瑠璃さん、七月の頭には里に戻って祝言なんだよね? 俺、それまでには戻れないと思うから。もう…これで最後だと思う」 元気で、お幸せに。そう言いたかったが、そこまでは口にすることが出来なかった。
このままずるずると関係を続けても、やがて終焉は来る。彼女の口から、それを告げられるのが怖かった。そんなことになったら、自分がどうなってしまうか分からない。頭に血の上った自分がどんな行動に出てしまうか分からなかった。 どうしたらいいのか考えた。そして…結論として、この関係を自分から断ち切ろうと決断したのだ。彼女を引き留めることの叶わない土地に去り、全てを忘れ去ろうと。戻って、瑠璃がいなくても、初めからなかったことだと思えばいい。 思い悩んだ末の決断だった。この方法しかないと思った。
ひどい吐き気を覚えながら、それでも背後の人の次の言葉を待った。でも…瑠璃はあの一瞬の戸惑いの言葉の後は、ひとことも発する様子がない。身を清める手すら止まっているようだ。あれだけのことを告げたのに、何の反応も見せないと言うのか。 息を飲んで、今一時、待った。でも無駄なことだった。満鹿の悲しみは頂点を越えて、怒りの渦に巻き込まれていった。 「…瑠璃さんっ!!」 どういうことなんだ? 自分たちはそれほどの関係だったのか? …最初から割り切った付き合いだったから、最後もあっさりとしたままでいいと? そんなっ…、瑠璃はそれでいいかも知れない。でも、でも…!! 自分はそれではやりきれない。この身を切る様な身体の叫びをどうすればいいのか。 演技でもいい、行くなと言って、泣き真似でも出来ないのかっ…!! 細い両肩を捕らえて、ぐっとこちらを向かせる。彼女の美しい髪が辺りに漂い、流れ、…やがてさらさらと元のように彼女の周りに落ちていく。その瞬間、満鹿は信じられない光景を目にしていた。
|