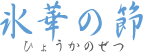|
最初は、決して手に入れることが出来ない崖っぷちの花だと思った。それを気付くと手折って、手中に入れていた。芳しい香を一度味わってしまえば、もう逃れられない。永遠の花園に堕ちていくしかない。 …花を。手折ったのは自分なのか? それとも、手折られたのが自分なのか…?
「…あ…」 目の前の瑠璃の頬が河の水に浸したように濡れていた。それが首筋から鎖骨の上、胸の頂きに流れ、行き場を失って膝に落ちていく。その源を辿る。綺麗な、長いまつげの向こう。黒目勝ちの瞳から、音もなく流れ出るもの。 「瑠璃さん…」
音もなく、声もなく。でも…いつから? 先ほどまでは背中越しに2人で普通に語らっていたのだ。その後…? 声が途切れてから、ずっと…?
瑠璃が。息を吸い込んで吐いた。すっとハナが鳴る。必死で呼吸を整えているのか。まつげが震えている、視線を一度逸らして、その後、覚悟を決めた表情で満鹿に向き直った。 揺らめく蝋燭の炎がその輪郭を照らし出す。青白い肌が橙色と相まって、神々しい輝きを醸し出す。彼女の動きに合わせて、素肌を、肩から掛けた小袖の上を流れる髪が静かに波打った。流れが変わり、輝きが角度を変える。 美しかった。ありきたりな表現しか思い浮かばない自分が情けない。でも瞳を逸らすことすら出来ない。完全に囚われていた。 瑠璃は満鹿の視線に気付いたのか、恥ずかしそうに小袖の前を手繰った。胸の前でしっかりと襟を持って手を握りしめると、かすれる震える声で語りかけてくる。 「…これで、最後だと。そう仰るんですね?」 「そ、そうだよ?」 「本当に。…今宵が最後の逢瀬だと…」 満鹿は身体が縛られているように動けなかった。泣いてすがってくれたら、少しは気が晴れるかとは思っていた。でも、そんなのは虫のいい考えだとも。反応を見せない瑠璃には苛立ったが、その反面、心のどこかではそれでいいような気がした。 まさか、こんな風に静かに嘆かれるとは。彼女の中にある感情が理解できなかった。 「満鹿様」 「な、なんだ?」 ただならぬ問いかけの音色にずずっと身体の向きを変えて、寝台の上であぐらをかいた。膝をきっちり閉じて正座した瑠璃に向かい合って。狭い寝台だ、膝がほとんど擦れ合うほど近い。 「最後と。そう仰るなら…お願いがございます…」 「最後に…わたくしを、きちんと愛して下さいませんか?」
ゆらり。気の流れも感じないのに、蝋燭の炎がひとりでに揺れた。
「…え…?」 「一度でいいですから、しっかりと抱いてくださいませ…」 「…なっ…!?」 瑠璃の上体がゆるりとこちらにしなだれかかってくる。それをはじき返す如く、大きくかぶりを振った。 「何だよっ!? 瑠璃さんは俺じゃ物足りなかったって言うのか!? そうなのか? だから、だから…いつも…!!」 押し殺した、控えめな声しか上げず、抱き合った後の余韻すら残さず。いつも平然としていた。そんな彼女があまりにも遠く感じて口惜しかった。男として、一度でいいから快楽のうねりに飲み込んでやりたかった。でもこの半年以上の逢瀬で、一度もそこまで行ったことはなかった。 「――俺みたいな若造じゃ、瑠璃さんを満足させられなかったって言うのかよっ!!」 やぶ蚊を払うように瑠璃の目前ギリギリのところで気をかいた。その勢いに瑠璃の脇の髪が舞い上がる。
そりゃ、自分は瑠璃しか知らなくて。瑠璃に夢中になっていた。諦めなくてはならない、これでおしまいにしなければならないと思いつつもそれが出来ないほどに。瑠璃も同じように思っていてくれるとは、望まなかったが、一度も満足してないから、最後くらいちゃんと抱いてくれとはどういうことだ!? 人を馬鹿にするにも程がある。 満鹿の汗に濡れた髪がうねった。結びなどとっくに昔に解けている。肩下までの垂らした髪だ。
「…そうでは…ありませんが…」 「満鹿様…いつも途中でおやめになるでしょう…?」 「え?」 「馬鹿なことを!! 何を言い出すんだ、瑠璃さん。そんなことを…」 出来るはずがないだろう? 困るのは瑠璃の方だ。夫となる者がいるのに、他の男の子を孕んだとあっては、どういうことになるか? もうどうにも言い逃れることは出来ないだろう。
恋人や夫がすでにいて、情をかわす男を別に作るなら、同じ土地の者にしなければならない。子が出来たとき、ひとめで異郷の者の種だと分かれば、どんな仕打ちが待っているか? それを知らぬほど、愚かな女子ではあるまい。年上の満鹿をきちんと立てながら、しっかりと導いていくそんな聡明さがあると思っていた。それに何度助けられたか、何度救われたか知れない。
しかし、瑠璃の口から出てきたのは満鹿の心内とは全く異なる言葉だった。 「…分かっております。遊びで抱く女子になど、情を交わせぬと仰るのでしょう…? そんなこと、分かっております。あなた様は最初から、そう言うお心でしたもの…承知しておりますわ」 …遊びで、抱いた? どういうつもりでそう言ってきたのか分からない。言葉をなくし、大きく目を見開いて見つめる満鹿に、瑠璃は泣き顔のままでゆっくりと微笑んだ。その奥から、つんとした寂しさが浮かび上がる。
「あの時まで、満鹿様は他の殿方とは違うお心映えの方だと信じておりました。こちらに参った当初から、わたくしはあまたの殿方の好奇の視線に晒されておりました。皆、わたくしに男がいると分かっていて、それで聞こえよがしにあれこれ仰るのです。恥ずかしくて口惜しくて…でも、満鹿様は違いました。まっすぐに私を見つめてくださいました…わたくし、あなた様ならと、思って。でも、満鹿様はそうではありませんでしたものね…」 キリ、と唇を噛む音が部屋に響く。 「満鹿様…あんなに驚かれて。わたくしが夫となる人と相まみえる前の身であったこと。悲しかったです…でも、それでもいいと思っておりました。わたくしはあなた様さえ…」 「な、何を言い出すんだよっ! 瑠璃さん、祝言が目前だろう!? 他の男に勝手に縁付く奴がそんな風に責め立てるなよっ! …俺は…」 何てことなんだ。全ては瑠璃のことを思ってのことだったのに。こんないい方をされて黙っておれるか? 身を寄せて、ずいっと凄んで見せはしたが、対する彼女はまったくひるまなかった。 「わたくしは、あの方の妻になど、なりたくはありません……!」 「満鹿様が…もしも、ひとことでもやめろと仰ってくだされば…わたくし、家も一族も…集落も、全て喜んで捨ててしまうつもりでおりました。満鹿様もお戯れにせよ、わたくしとこんな関係を続けていれば、いつか情が湧いてくださるのではないかと。わたくしを手放せなくなるほどに愛おしく感じてくださる日が来るのではないかと、夢見て…」 そこまで言うと、とうとう耐えきれなくなったのか両手で顔を覆って俯いた。小袖に覆われた細い肩が小刻みに震え、周囲の気をも震わせる。はあ、とため息を付くと、消えそうな声で言った。 「…私、何枚も縫ったんです…満鹿様の衣を」 「…え…」 でも、衣って? どういうことだ? 縫ったって言っても、自分は受け取ったこともないぞ? …しかも何枚もって? 満鹿の心の叫びに答えるように、瑠璃の細い告白が続く。 「最初は。物売りの方が持ってきた絹でした。お美しい色目に、つい買い求めてしまいました。満鹿様に良くお似合いになりそうな鮮やかな文様。ご迷惑なだけとは思いましたが、仕立ててみたかった。柚羽様がお留守の時を見計らって、もう必死で。これが完成したら、お渡しして、私の想いを知っていただこうと。もう、ひとりで抱え込むには重すぎるほど…私の心はあなた様で満たされておりました。想いを込めるように、針を動かして。寝食を忘れ、ってあんなことを言うんでしょうね? 瞬く間に完成に近付いて…でも、そうしたら、急に恐ろしくなって」 燭台の明かりに浮かび上がる、瑠璃の美しい横顔を思い浮かべた。針を動かしながら、自分への想いで頬をほころばせて。そんな彼女など、どうして想像も出来ただろうか? しゅるしゅると絹のこすれる音、針を引くとんがった音、…軽い吐息。微笑む口元。 本当にそんな光景が存在したなら、見てみたかった。 でも、こうして語る瑠璃を前にしても、まだ心からは信じられない。上手い具合に乗せられているのではないだろうか? 瑠璃が自分を想い続けていたなんて、そんな都合のいいことがあるのだろうか…? あって良いのものか。 「もしも…衣をお渡しして。満鹿様がご迷惑に感じられたら…そうしたら、もう会ってくださらなくなるかも知れない。逢瀬を重ねることもなくなったら、わたくしには何の望みもございません。わたくしのような困った素性の女子など、満鹿様の御相手にはふさわしくございませんわ、そんなこと、とっくに分かっておりました。分かっていても…わたくしは、ただ、衣を仕立てるしかありませんでしたわ。溢れ出る想いを閉じこめるにはそうするしかなかったのですもの。…もう、行李一杯になってしまいましたわ」 何と言うことだろう? 行李は大人の男がやっと抱えられるほどの大きさだ。その中に衣を詰めたら、どれくらい入るだろう…。それだけのものを仕立てながら、瑠璃はあんな風に穏やかに自分に微笑んでいたというのか? どうしてそこまで取り繕うことが出来たのか? 「…もう、時間がございませんでした。自分からはどうすることも出来なくて。ただ、満鹿様のお心がわたくしに向かってくださることを祈るだけでした…それなのに、やはり…分かってはおりましたが。このように、あっさりとおしまいを告げられるなんて。わたくしは…そんなにも軽々しい女子だったのですね? 満鹿様が本気で惚れてくださる身ではなかったのですわ…分かっていましたのに。どうして、こんなに…」 後から後から、頬に流れていくもの。未だに動けないでいる情けない男を綺麗な瞳が見つめる。必死の色を乗せて。 「決して、満鹿様のご迷惑になるような様にはしません。お約束しますから…だから。お願いです、一度だけ、夢を見させてはくださいませんか? …わたくしを愛していると…そんな振りをして。殿方は、お心がなくても情が交わせるものでしょう…? でしたら、お願いです、お願いしますっ…わたくしを。わたくしをもう一度、抱いてください…」 ここまで言われて。心が動かぬ男などいるだろうか? ましてや目の前にいるのは、自分が諦めきれずにもがいていたただ1人の女子ではないか。 匂やかな柔肌で満鹿を誘い、夢中にしてきた女子。共に添い遂げることを何度も夢見てきた。心も姿ももったいないほど美しくて、どうしても逃れられなかった。手放す場面など今までに何度もあったのに、どうしてもそうすることが出来なかった。 「…瑠璃っ…!!」 「満鹿様…」 冷たい頬に自分の頬を重ねる。ぺっとりと涙が張り付いてくる。もう一度、しっかりと見つめ合って、唇を合わせた。 すると、瑠璃がおずおずと、ためらいがちに自分から舌を差し込んできた。初めての行為に、満鹿はドキリとしてしまう。やわらかくて、甘いもの。いつも自分から攻め込んで、捕らえてきたもの。それが泡を立てながら、満鹿の口内を探っていく。夢中で応え、たぐり寄せる。頭の後ろをしっかりと支えて、逃げ場をなくして置いて、その行為に耽った。 それだけで、頭の芯がクラクラとしてくる。酒もないのに、すっかり酔いが回っていた。瑠璃に、瑠璃の存在に酔っていたと言ってもいいだろう。そのまま、愛し合ったばかりのしとねに再び倒れ込んだ。
身体の奥から湧いてくる感情がいつもとは全く違っていた。そこにはためらいというものが消え失せていて。ただ、自分が組み敷いた愛しい身体を貪るだけの獣になり果てている気すらする。それが求められていると知れば、もう何も恐れることはないのだ。 さっきまで。もう最後だと思って瑠璃を抱いていた。でも、最後だからと思っても、どうしても満足することが出来なかった。満たされない想いで、身体が引きちぎれそうだったのだ。 頬にかかった髪を払い、そこに舌を這わせる。瑠璃が産みだした塩味を舌に絡め取っていく。くすぐったそうに首をすくめる。申し訳程度にまとっていた小袖など、もうその辺に落ちてしまっていた。瑠璃も満鹿も産まれたままの姿で、ためらうこともなくお互いのぬくもりを重ね合った。背中に手のひらを這わせて背筋を辿りながら、唇は首筋を味わっていく。 「…あ、あんっ…!」 一瞬、ハッとしたが、気付かせてはいけないかと、知らぬ振りをする。ただ、首筋を辿っただけだ。敏感なところになど行ってないのに。満鹿の動きに合わせて、絶え間なく漏れ出る声はもう何も憚ることはなかった。部屋の内壁に響いていく、甘い音色。それをもっと聞きたくて、夢中で愛しい身体に自分を刻み込んでいった。 「…満鹿、様っ…」 待ち望んで隆起している頂をゆっくりと口に含んでいく。そっと吸い上げると、やわらかく自分の名が呼ばれ、彼女の腕が首に絡んできた。そうして貰うことを望んでいると言うように。瑠璃は首を横に振りながら、吐息混じりに声を上げる。 このままずるずると、しとねの白い布にふたりで沈み込んでしまいそうだ。深い深いところまで、堕ちていく。それでいい、ずっとそうしたかった。瑠璃とふたりでいられるなら、そこがどこでも楽園だった。 「瑠璃、瑠璃…ああ、瑠璃…」 細い膝を抱え持って、左右に開く。十分に潤っているその場所に、そっと唇を寄せた。瑠璃は自分からは満鹿にしてくれても、ここを舌で味わわれることをあまり好まなかった。それが何故なのかずっと不思議だった。 瑠璃の唇が舌が満鹿のその場所を這っていくとき、脳の中にぴりぴりと快感が走っていく。泣き出してしまいそうな贅沢な波が押し寄せて、自分の力では防ぎようがなくなる。いつもやわらかく穏やかな笑みを絶やさない落ち着いた彼女が、必死とも見える表情で満鹿を愛していく。彼女はそれが好きだったのだろうか? そうではない気がする。それでも、満鹿から求めなくても、行為に及んでくれる。 「…え? ああんっ…」 「や、…っ、やあっ!! 駄目、やめてっ! 満鹿様…っ!」 「…やめないよ、やめられないよ…っ!」 「ああっ! …満鹿、様っ…」 「我慢しなくて、いいのに。駄目だよ、そうして堪えちゃ…」 薄目を開けた瑠璃にそう言って口づけると、彼女は恥ずかしそうに顔を覆ってしまった。 小刻みに震える身体は薄桃色に上気して、次第にたかまりを見せている。頬も桜色に染まって、いつもより子供っぽく幼く見える。瑠璃が落ち着いている大人で、自分が不甲斐なく思えることが常だったので、それがとても嬉しい。汗ばんだ身体を持ち上げるように抱きすくめると、嬉しそうに寄り添って来る。 これが本当に瑠璃なのだろうか。全てを解き放たれた彼女は無邪気に微笑み、乱れ、満鹿を求めてくる。ついさっきに、思い詰めた表情で食い下がってきたあの瞳もない。満鹿が見ることの出来るのは、熱く甘く見つめてくる恋人の目だ。 「瑠璃…」 「あっ、あっ…ああっ…!」 「…瑠璃…」 「愛してるよ、瑠璃…」 瑠璃が。満鹿を包み込んでいる瑠璃の内側が、ねっとりと絡みついて収縮したのだ。たとえようのない締め付けに腰が泳ぐ。 「…やあっ…んっ…」 「満鹿様っ…満鹿様…っ!」 「瑠璃…君だけだ…」 「や…っ、あんっ…、駄目っ…!! もう、許してっ…!」 「み、満鹿…様っ…、あっ…、ああっ…!!」
「…え? …瑠璃…さん?」 「う…? あの…っ、わたくし…」 「大丈夫…? 平気?」 「…あ…」 「ごめんなさい…わたくし…」 「何故、謝るの?」 「だって…あの…」 「俺は嬉しいよ。瑠璃さん、思い切り感じてくれたんだね…最高だよ」 じわりじわり。瑠璃は無言なのに、別の場所が満鹿の言葉に反応する。そんな風に包み込まれたらたまらない。満鹿は小さく呻いた。 「…瑠璃さん…」 「もうちょっと、頑張れる? 大丈夫?」 答えの代わりに。瑠璃の細い腕がそっと満鹿の背中に回った。
勢いよく腰を動かすとまとわりつくひだがザラザラとなでつけてくる。そうすることが満鹿の快感を生み、瑠璃の快感をも生む。その行為がお互いをたかいところまで押し上げていく。腰に絡みついていく瑠璃の足。左右から包み込まれる。更にぎゅっと締まる気がする。 大波に巻き込まれていく。でもどこまで流されようが、沈み込もうが、瑠璃が共にいる。ふたりで作り出していく波なのだ。何を迷うことがあるだろうか。どこまでも行こう。 「う…っ! ううっ…っ!!」 瑠璃の中で、満鹿は弾けた。それをゆっくりと受けとめられる。心地よい圧迫感に強く引き込まれていく。腰全体が瑠璃の中に吸い込まれていく気がする。ゆっくりと腰を前後させながら、全てを注ぎ込んでいく。吐き出していくのに、満たされていく。なみなみと満ちゆく温かいものが満鹿の心を隙間なく埋め尽くした。
こんなに安らかで。こんなに暖かな時間を今まで共有したことがあっただろうか? 「…瑠璃さん?」 自分と同じように息が上がった瑠璃を静かに呼ぶ。腕の中の人は小刻みに震えていた。その震えが何であるのか、今の満鹿には分かる。全身で満鹿を受け止めたその余韻に酔っているのだ。 ついっと冷たい後悔が心をよぎったとき、腕の中の人が軽く身じろぎした。 「…満鹿様…」 瑠璃の腕が満鹿の逞しい身体を抱きしめていく。しっかりと身体を合わせると、激しく愛し合った後なのに、また新しく沸き上がってくる欲求がある。それをどうしようか思案していると、瑠璃の声が耳元に届いた。 「わたくし…幸せですわ。本当、もういつ死んでもいい…」
…え? 思わず我が耳を疑った。一体何を言い出すんだ? ようやくひとつになれたのに。信じられない気持ちで腕に力を込める。寄り添ったままの瑠璃がくすぐったそうに身じろぎした。
「ううん、…もう、このまま懐刀を胸に突き立てて果ててしまいたい…そうすれば、私は永遠に満鹿様に愛された幸せな女子でいられますわ。…もう、どこにも行きたくない…このまま…」 「…瑠璃、さん!?」 更なる言葉には、さすがにぎょっとして我に返った。肩をぐっと押さえて身を剥がす。そして、たった今信じられない台詞を呟いた人の顔を視界に捉えた。 「…あ…」 「ちょっと待ってっ! …あの、どういう――」
瑠璃はふっと視線を逸らすと、満鹿の胸を押して身を剥がした。がばっと起きあがって落ちていた小袖を取る。そのまま満鹿に背を向けて、寝台に腰掛けた。 「ご、ごめんなさい…気になさらないでっ! あの、今のは…何でもないんですの…本当にっ!」 慌てた仕草でもうすっかりぬるくなってしまったであろう湯桶の中の手ぬぐいを取る。でもその腕は身体を清め始める前に、満鹿によって捕らえられた。 「瑠璃さん――!? あの、君は…一体、何を…!?」 「は、離してくださいませっ! 本当に、気になさらないで。戯言ですわ…!」 大きく腕を振って、満鹿の束縛を逃れる。そのまま立ち上がって、すすすっと壁際まで進む。でも後から覆い被さるように満鹿の身体が追いかける。両方から壁に手を付かれて、彼女は身動きが取れなくなってしまった。それでも壁に向かって必死で叫ぶ。 「満鹿様にはご迷惑をお掛けしないと申しましたでしょう? 戯れで抱いた女子などお忘れになって下さいまし。わたくしは二度とあなた様の前には現れませんわ…だから、お健やかに。どうぞご出立なさって―」 「瑠璃っ…!!」 満鹿は夢中で彼女の腕を取り、こちらに向き直らせた。青ざめた顔がふっと俯く。その瞬間、彼は全てを悟った。
|