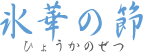|
禁を破った女子が里に戻れるはずもない。しかし、それならば、彼女はこれからどうなるのだ。自分は明日の朝、遠征団で出立する。これは決まってしまったことだ。もっとよく考えてから、決定するべきだったのにもう遅い。男として、一度志願したことを覆すことなどどうして出来よう。
「そんなことを言わないでくれよっ! 瑠璃さん、待っていて! 俺、戻ったら必ずっ…!!」 「…いいえ…」 「もう、宜しいんです。お気になさらないで…満鹿様には関係のないこと…」 それだけ言うと、青ざめた頬に張り付いた笑みを浮かべた。 「満鹿様は…わたくしにこんなに素晴らしい夢を見せてくださいましたわ…もう、充分です。二度と、お目にはかかりませんわ…わたくしのことなど、どうぞお忘れになって」 瑠璃は、もう泣いてはいなかった。しっかりとした口調で言い放つ。何事も寄せ付けない強い意志を感じた。また、目に見えないものに強く押される気がする。これが瑠璃と自分との間の「壁」なのだろうか…? 「瑠璃…」 何か言わなくてはならない。そう思っても言葉が浮かばない。喉の奥に張り付いた想いが息を詰まらせる。そんな満鹿の歪んだ表情をいつもの微笑みに戻った瑠璃が見つめる。凪の海のように微かな吐息。 「先ほどは、わたくしもどうかしておりましたの。これでお目にかかれなくなるのなら、もう里に戻りますわ。婚礼を前に、色々準備もございますの。元々あの方がお戻りになるまでのお務めで、家の者も何度も文をよこして来てますし。もう…お気になさらないで」
気の中を舞うように、小袖一枚を羽織った細い身体が向きを変える。豊かな漆黒の流れがゆらゆらと彼女を包み込み、その姿を覆い尽くす。 手を伸ばせば、すぐに届く距離にありながら。見えない透明な壁に阻まれる。凍り付いたまま身動きのとれない身体をもどかしく思っているうちに、瑠璃はさっさと身支度を始めた。いつものように。いつもの逢瀬の後のように…。
もしかしたら。これは永遠の別れなどではないのではないか。いつもと同じ、しばしの別れで。 ざわざわと未だに続く宴のさざめきが耳に届かなかったら、本当にそう信じてしまったかも知れない。それくらい普段と変わらないふたりに戻っていた。
このままで、いいのか。このままで。喉が詰まって呼吸も苦しい。重くなる身体で必死に自分に訴える。瑠璃が、本当にこのまま離れていって、自分はそれでいいのか? …耐えられるのか?
ふと。瑠璃の手元に目がいった。綺麗な装飾を施した鞘に収まった懐刀。侍従と侍女は主君をお守りするため、常にそれを懐に忍ばせる決まりとなっていた。それを取ろうと伸ばす手。長い指が震える。 その瞬間。 満鹿の目の前にひとつの光景がありありと浮かんできた。 「…瑠璃さんっ…!!」 ようやく想いがひとつの音になった。それに弾かれて、彼女の周りの見えない結界が壊れる。その中に入り込んで、瑠璃より先にその懐刀を手にした。 「え…、何をっ…」 「これ、俺が貰う。俺のと交換して」 静かにそう告げることが出来た。瑠璃は信じられないと言うように、黙ったまま、目を見開いて満鹿を見つめている。それから、ゆっくりとかぶりを振った。 「…その様なこと…なりませんわ。お返しになって…」 力無くそう呟くと、腕を伸ばしてくる。自分の方に身を乗り出してきた身体、きちんと小袖と袴を着込んだ侍女の装束。それを思い切り抱きしめた。満鹿の手からこぼれた瑠璃の懐刀が足元に落ちて転がる。カンカンと床を弾かれて、壁際で止まる。 「瑠璃さん…」 「…や」 「戯れなんて、そんなじゃない。こんなこと、急に告げても信じて貰えないかも知れないけど。でも、俺はいつだって、瑠璃さんが欲しかった。他の男がいると知っても、諦めきれなくて…頼むよ、俺と生きてくれないか。瑠璃さんしか、いないんだっ!」 「駄目ですわ…そんなこと、許されるはずも…」 「お願い、もう、やめて下さいまし。同情なんてしなくて宜しいのです。…私は、あの方の妻になるのだから…」 「そんなの、嘘だっ!!」 「どこに行く気なんだよ、瑠璃さんがどこに逃げたって追いかけるぞっ! お務めも投げ出して、瑠璃さんが見つかるまで一生かけてでも探してやるっ! 瑠璃さんは…俺の人生を滅茶苦茶にするつもりなのかい? 瑠璃さんを捜すために俺の全てを使わせるつもりなのかよっ!!」
しっかりと情を交わしたからなのか。満鹿は自分の中に浮かんできたものが瑠璃の心を映しだしたものだと確信していた。瑠璃は決して里へは帰らない。でも満鹿が遠征から戻る頃にはもうここにはいないのだ。どこか遠いところへ旅立とうとしている。彼女の抱え持つものは満鹿への想い、それだけなのだ。 見知らぬ土地をさまよう、寂しげな横顔。今、手放してしまったら、捕まえるのが困難になってしまう。
「もう…おやめになって。その様なことを仰らないでください、満鹿様っ…」 「無理…ですわ。一族の手から逃れることなど不可能です。わたくしなどにこれ以上情けをかけられては、満鹿様にまで害が及びます。満鹿様は明るい陽の下をお歩きになる方…私のために犠牲にならないで。本当に…もう…」 溢れ出るものがそれ以上の言葉を封印する。震える唇が言葉を紡ぎ出せない。腕の中にあって、きゅっと身体が強ばる。 たとえようもなく、愛おしかった。泣き濡れて、自分から離れようとする。その心根までを愛したいと思った。ぬくもりが力を生む。
そして。ぱあっと霧が晴れるように、満鹿の心に確かなものが湧き出てきた。
「…逃げることはないんだよ。どうして、逃れることだけ考えるの?」 「…え?」 「そうだよ、逃げることはないよ。そうなんだよっ!」 「…満…鹿、様…?」 「瑠璃さん」 しっかりと彼女を見つめて。満鹿は晴れ晴れとした声で言った。 「俺、必ず手柄を立てて、戻ってくる。そうしたら、一緒に瑠璃さんの里に行こう。俺、瑠璃さんの家の人にちゃんと話をする。瑠璃さんを下さいって。…だから、待っていてくれるよね?」 「…え…」 「満鹿様…? それは無理です! そんなことして、どうなると思っていらっしゃるのですか? ご冗談でもおやめになって下さい。…何て、恐ろしいことを…」 にわかに青ざめて、身震いしながら必死にかぶりを振る。そんな瑠璃の姿を見る前から、分かっていた。この提案がどんなに大変なことなのかを。それでも、満鹿は少しも怖くなかった。それどころか、うきうきと弾むような気持ちにすらなっていたのだ。 「冗談じゃないよ、だって、俺は瑠璃さんのことが本当に好きなんだから…」 身体の奥からこみ上げてくる希望。一度、細い身体をきゅっと抱きすくめる。それから、腕を解くと、ちょっと待って、と告げてからそこを離れた。物入れの中をかき混ぜて目的の物を手にすると戻る。 「瑠璃さん」 滑らかな手を取る。そこに先ほど脱ぎ散らした衣の中から拾い上げた自分の懐刀をそっと置いた。柄にたくさんの玻璃の飾りを施した南峰の短剣だ。田舎育ちではあったが、一応家の跡取りだ。きちんとした品を持たされていた。 互いの懐刀を交換して、夫婦の契りを約束する。侍従や侍女たちの間でいつしか広まっていた慣習だ。それをしたからどうなるという物でもないが、皆の憧れの行為でもあった。そのために懐刀だけは恥ずかしくない物を持ち、手入れも怠らなかった。それこそが持ち主の真の心映えなのだから。 瑠璃は未だに信じられない、と言った表情で呆然とそれを見守る。もう一方の手も取ると、そこには麻で出来た布袋を置いた。それほど大きな物ではない、いつか瑠璃が見せてくれた匂い袋をもう一回り大きくした程の物だ。でもずしりと確かな重みがある。瑠璃の手のひらの上で、それを紐解いた。 「……」 「知ってるでしょう? 南峰では妻になる人に玻璃を贈るんだ。高貴な身分の御方は玻璃の籠を贈るのだけど…俺たちのような庶民には手に入る物じゃない。でも…こうして、男子が生まれたときにちゃんと玻璃の珠を託されるんだ。綺麗でしょう…? ひとつひとつ色が微妙に違うんだよ…」 そう言いながら、ひとつひとつつまみ出す。南峰の特産物である玻璃はその産地の山によって色目が異なっていた。それぞれにいわれのある5色の珠を贈り、妻に乞う。それが古からの習わしだった。満鹿自身も正確なことは分からないが、5つ揃えれば、大変な価値になるらしい。これは命の次に大切な物だと幼き頃から言われていた。 「これはもう、瑠璃さんの物だから。ね、ちゃんと持っていて。俺の帰りを待っていて?」 「…そんな…」 「このような物、受け取れませんわ…駄目です、こんな…」 「満鹿様、そんな、気軽すぎます。里に来るなんて…わたくしに玻璃を贈るなんて、とても正気の沙汰とは思えませんわ。お忘れになってと申し上げたでしょう? わたくしは、あなた様にはふさわしくございませんわ…」 「瑠璃さん…」 顔を寄せて。甘えるように囁く。その吐息に瑠璃がぴくりと反応した。 「駄目なの? …そんなこと、ないよね? 瑠璃さんは俺のこと、特別に想ってくれてるんだよね…そうでしょう」 「無理ですっ…、だって…」 「こんなこと…許されるはずもございません…一族の許しがおりるとも思えませんわ…一体、どんな罪になるのか…」 「どうなったって、構わないよ」 「殴られても、蹴られても、何をされても耐えてみせる。瑠璃さんを失うことに較べたら、そんなの大したことじゃない…そうだろ?」 「…そんな…」 「満鹿様おひとりに罪は負わせられませんわ…叩かれるのでしたら、わたくしがその半分を負います…地下牢に入れられるのでしたら、ご一緒させてくださいまし…そして」 腕の中で満鹿の顔を見上げた彼女は、とろけそうな笑顔になっていた。戸惑いの霧が晴れていく。 「土牢でしたら…土を掘って、一緒に逃げましょう」 「…瑠璃さん…?」 「わたくし、お待ち申し上げております…本当に、その様なことが許されるのならば…」 夢のような答えだった。このような言葉を瑠璃が自分に告げてくれるなんて、信じられない。でも真実なのだ。 「…待っていて、くれるんだね?」 「はい、…いつまでもお戻りをお待ち申し上げておりますわ。家の者が何と申してきても、満鹿様がお戻りになるまでは、必ず」 「…瑠璃さん…」 初めて指先が触れ合った気がする。指の先から、身体の芯までしっとりと幸せが浸透していく。
「瑠璃さん…あの…」 きゅっと、髪を握りしめて身を寄せると…そっと耳元に囁く。 「ねえ、もう一度、いい? 瑠璃さんのこともっと感じてみたい。今夜はずっと一緒にいて…」 その言葉に、瑠璃が慌ててかぶりを振る。 「そ、そんな…明日はお早いんでしょう? 今宵はゆるりとお休みにならなければ…それに余市様だって、いつ戻られるか知れませんわ…わたくしなどがこんなところにいたら…」 「余市は戻ってこないよ?」 「俺、分かるよ。余市だって、今夜は戻りたくないと思う…だって」 顔を上げる。戸惑っている瞳をしっかりと捉えて。 「一瞬だって、離れたくないよ。ずっと、触れていたいんだ…それが一番の願いだ」 「…そんな」 瑠璃が真っ赤になって俯く。それは合意の仕草だと汲み取れた。満鹿は彼女の支度を終えてしっかりと結んでいた袴の帯をするすると解く。 寝台の横に置かれた物置の上の蝋燭の炎が、静かに流れて、つうっと消えた。
◆ ◆ ◆
「…満鹿、本当に出立していいの? やり残したことはない?」 その控えめな物言いがおかしい。この者はどこまで分かっているのだろうか。 「ううん、もう大丈夫」 「でも、遠征先ではやりたいことがあるんだ。どうにかして手柄を立てたい、同室のよしみとして遠征団の団長様も協力してくれるかい?」 軽い笑い声を上げながら、問いかける。遠征団の団長は余市本人だ。こんな風にあからさまに言われては彼も苦笑するしかないだろう。 「…やだな。手柄を立てたいのはみんな一緒なんだから。お前だけを贔屓は出来ないな。そもそも手柄を立てる気がない奴が、遠征団に志願するわけないだろう?」 「ま、それもそうか」 瑠璃をこの地に残していくことに、不安がないわけではなかった。ふたりが交わしたのは口約束だ。懐刀を交換して、玻璃を渡したからと言って、それが何になるとも言えない。 でもそれは、誰もが同じなのである。恋人であっても夫婦であっても、不変なものなどない。お互いに想い合うその心で支え合うのが男女の情ではないだろうか。瑠璃を守ろうと思う気持ちに嘘はない。それを証明するためにも、今回は頑張らなくては。
「冠の後ろ、綺麗に結んでやろうか? 一番人目に付くところだからさ」 すっかり支度を終えた余市が笑顔で入ってくる。それに満鹿も笑顔で応えた。
|