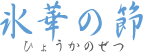|
瑠璃は必ず待っていてくれると信じていた。でも、長い遠征を終えて帰館して、迎えの群衆の中に彼女の姿を捉えたとき、胸の奥がじんと熱くなった。無事を祝うさざめきの中で、視線を交わし合う。出立の前と少しも変わらないやわらかい笑顔。ふたりを隔てていた長い時間が崩れて落ちてしまった如く。 都は春から夏へと季節を変えていた。ふわふわの花を散らしていた天寿花の林は深緑の森に変わり、御庭の遣り水もキラキラと輝きが眩しい。 西の地は竜王様の結界の端に当たるため、気が薄いのだという。そのせいか、夏なのに白っぽくどこか寒々しい気がした。物寂しい雰囲気に押しつぶされそうになる。元より、特に明るく活気に満ちた南峰の出身の満鹿である。辛気くさいのは苦手だった。
◆ ◆ ◆
遠征団を出迎えた竜王の御館では、夕刻から歓迎の宴が開かれた。無事、西の集落の暴動を抑えた功績は高く評価されていた。団の帰館に同行した村長本人の行動と竜王様への献上物の見事さからもそれが伺い知れる。館の侍女である瑠璃ももちろん給仕に出ていた。彼女が膳をもって渡りに出ていったところを追いかける。こちらの足音が聞こえたのか、瑠璃が振り向いた。 さらさらと彼女の回りを髪が流れる。黒い帯、その流れの向こうに、微笑む人の姿が現れる。スローモーションの時が流れていく気がした。夢の世界の様な光景にしばし見とれてしまう。言葉を発することすら忘れていた。 「お帰りなさいませ、満鹿様」 思わず、腕を伸ばしていた。膳が間にあるので心許ないが、それでも甘い香りが髪から感じられて手のひらが震える。胸元に顔を埋めた彼女がくすり、と笑った。 「…満鹿様…?」 「あ…」 「…ただいま、瑠璃さん」 「俺…手柄らしい手柄も上げることが出来なくて…ごめん、こうして身ひとつで戻ってきてしまった。あんなに景気良く出掛けたのに…」 瑠璃の笑顔に助けられながら、おずおずと口にする。瑠璃の両親を一族を前にして、恥ずかしくないくらいの功績を挙げたかったのに。自分なりには精一杯頑張ったものの、人に自慢できるような手柄は何もなかった。 うなだれる満鹿の前に瑠璃が進み出る。そして下から見上げて、にっこりと微笑んだ。 「満鹿様の、お部屋に行きましょう?」 瑠璃のその意外な提案に、さすがにひるんでしまった。ずりずりと後ずさる。 「――えっ…、でも、…余市が」 …でも、もう宴の席から余市は退出している。一番の功労者がどこへ行ったかと皆が訝しんでいるが、仕方ない。それを問われても満鹿にも心当たりがないのだ。いくら何でも外で、と言うのはまずいだろうし…部屋の錠を差してしまって密室にしたら、余市に悪いし…。 それなのに顔を上げた瑠璃は余裕の微笑みで満鹿を見つめる。 「大丈夫ですわ。余市様は今宵、お戻りにならないもの…」 「…え?」 「余市様がわたくしにお訊ねになりましたの。今日は柚羽様がふせっていらっしゃるの、お姿が見えないって心配されて。だから、直接部屋においで下さいって申し上げたのですわ、わたくしは戻りませんから、どうぞ御心配なくって。そうしたら、余市様は驚かれて…瑠璃さんはどうするのって…だから」 瑠璃はおかしくて仕方ないようにくすくす笑った。 「私は満鹿様のところへ行きますからって申し上げたら…目を丸くされてましたわ」 「瑠璃さんっ…!」 少し眉をしかめて、瑠璃はたしなめるような表情になった。 「…ひどいですわ、満鹿様。わたくしのこと、余市様にひとことも仰って下さらなくて。そんなに信用できませんでしたの?」 「…う…」 今までが全て内密なままに行われていたからだろうか? 遠征団の夜営で皆が酒を酌み交わしながら、馴染みの女子の話に花を咲かせていても、どうしても真実を告げることが出来なかった。あの余市ですら、話を振られて恥ずかしそうに柚羽の名前を挙げた。…それでも。 瑠璃への気持ちは誰にも負けないと思った。でも口にしてしまうと軽々しいものになってしまう気がして。もっと大切に温めたいと思った。 「もう、過ぎてしまったことは宜しいですわ」 「わたくしは、あなた様がお戻りになっただけで、嬉しいですわ…本当に、良くご無事で…」 そのとき客座の大広間では、どっと笑い声が起こった。そんなさざめきが瞬時に遠ざかる。瑠璃は渡りの隅に重ねられた膳の上に手にしていたものを置くと、そっと満鹿に寄り添った。
◆ ◆ ◆
久しぶりに触れる柔肌は、まるで初めての時のような心の高まりを覚えた。真夏のねっとりした夜の気に泳ぐふたつの身体。激しい動きに舞い上がる漆黒の髪にこのまま絡み取られてしまえばいいとすら思った。2人で永遠に美しい闇を浮遊する。何て甘美な檻だろう。 「…瑠璃、…瑠璃…っ!」 全ての束縛を解き放たれた海はふたりの為にどこまでも純白の輝きを見せていた。頂点まで突き上げられては引き戻され、何度も何度も閃光を見た。もう夢中だった。自分にはやはりこの人しかいない。 「玻璃」を贈るのは生涯でただ1人の女子である。それは何人もの妻を抱える高貴な御方に取っても同じことである。大概、体裁を整えるために正妻に贈られることが多い。しかし、やはり物事にはいつも「例外」があり、正妻を迎える前に寵妾に与えてしまう者もいた。 「女子を取り違ってはならない」 貧しい農村に生まれ落ちた満鹿もそんな教訓を幼き頃から聞かされていた。古からの語りのように、玻璃に囚われた一族の話を聞き、教えを受けてきた。 ただ1人の女子は必ず分かる。それを見誤ってはならない。何よりも大切な心をもって行かなければならない。心より大切なものがどこにあるものか。心以外の大切なものがあるものか。 「…満…鹿、様っ!」
静寂が戻ると、客座のさざめきが再び耳に入ってくる。宴はいつまで続くのだろう。でも満鹿は知っている、祝いの宴よりも大切なものが今回の同行した仲間たちにはあることを。それだけを頼みに皆は戻ってきたのだ。どんなに辛いことがあっても諦めることが出来ない希望が合ったからこそ、こうして生きながらえることが出来た。 満鹿も何度かひやりとする場面があった。あそこで命を落としてもおかしくないと思うような…。 「…瑠璃さん」 「はい?」 吸い込まれそうな笑顔に次の言葉を少し躊躇する。口の中で粘っこくまとわりつくものを飲み込んだ。 「瑠璃さん…何か、余裕じゃない? 柚羽さんは体調が悪くてふせってしまうくらいなんでしょう? それだけ余市のことを気に病んでいたと言うことだよね…瑠璃さんはそういうの、なかったの?」 彼女は黙ったまま、満鹿をじっと見ていた。答えがないので仕方なく次の言葉を放つ。 「少しやつれているかなと思っていたんだけど。それどころか前よりふっくらしてるみたいだし…俺がいなくても寂しくなかったの? そうだったら、ちょっと口惜しいなあ…」 ここまで言ったら、言い過ぎかも知れないと思う。でも瑠璃の変わらない穏やかさにちょっと落胆したのも事実だ。自分を本当に愛していてくれるなら、争いの地に出向いた安否をもっと気遣って欲しかった。我が儘とは知りながら、こうして待っていてくれただけでも嬉しいと知りながら。少し贅沢になっているらしい。 怒るかな、と思ったのに、予想に反して瑠璃はふうっと微笑んだ。 「それは…お待ちする時間は長くて寂しかったですわ。でも…わたくしは…」 「…ひとりでお待ち申し上げていたわけではありませんもの」 「…へ?」 「申し訳ございませんが。わたくし、お約束しましたのに。里に参ってご一緒に体罰の仕置きは受けるわけにはいかなくなってしまいましたわ…困りましたわね」 「るっ、瑠璃さん!?」 「…あの…?」 瑠璃が震えるまつげの下から、大きな瞳を揺らす。穏やかな水面の様に安らぎを伴って。この人の中に、出立の時にはなかった感情が芽生えていることを裏付けている。 「お正月明けには…お父様ですよ? 大丈夫ですか…満鹿様?」 「…わ」 くりくりと動く目に捉えられて、思わず口元を手で覆ってしまった。脇の下がムズムズする、そう言う事って、本当にあるんだ。当たり前のことなのに全然実感が湧かなくて、うろたえてしまう。瑠璃はおかしそうにくすくすと笑っている。 「赤さまがいるって分かったときから、不思議なくらい心が安らかになりましたの。満鹿様はきっとお戻りになるって信じられたし、少しも怖くありませんでしたわ。この子のためにたくさん食べて、元気になろうと思いましたの…ちょっと太りすぎたかしら…?」 「そ、そんなことっ…どうしよう。すぐに暇を貰って、瑠璃さんの里に行かなくちゃ…でも、大丈夫かなあ…」 「あのっ、瑠璃さん…今、俺。何にも知らないから…その…、大丈夫だった? 身体の方…っ!」 さらに背筋がぞくぞくする。普通の身体じゃないと分かっていたら無茶しなかったのに。瑠璃が何も言ってくれないから、思うがままに抱いてしまったじゃないか。身体にさわりがあったらどうするんだ!? 「あのっ…おなかなんて、全然分からなかったし…だから…その…」 「大丈夫でしたわ、私だって満鹿様に遠慮されたら悲しいですもの…でも、今日はここまでにして下さる? さすがに身体が重くて…」 「あ、…う、うんっ…!」 「それに。わたくし、そんなに体調も悪くありませんでしたわ。柚羽様だってお気付きにならなかったもの…何度か、訊ねられたけど、しらばっくれてましたわ。…ふふふ、びっくりなさるわね。きっと…」 「…あ」 ふと、思いついた。それをそのまま瑠璃に問いかける。 「あの? 瑠璃さんっ! …柚羽さんは赤さん、まだだよね? もしかして、もういる?」 「え…、――いいえ。それはないと思いますけど…」 「…満鹿様?」 きゅっと、腕に力を入れて。しっとりとした身体を更に抱きすくめる。 「…勝った」 「は?」 「余市に勝ったな。あいつには何をしても負けてばかりで口惜しかったから。こうして、逆転できて嬉しいな。こればっかりは日数の問題があるから、奴だって、これからじゃ追いつけないだろ? …ふふふっ」 「…まっ」 「その様なこと、競争するものではありませんわ。…はしたないことっ!!」 「でも、嬉しいんだよ〜。仕方ないじゃないか、本当のことだもの」 膨れた頬を指でつつく。手に入らないと思っていた頃、この人はいくら抱いても遠い人だった。でも、今は違う。何があっても生涯を通して守り通す。それが自分の生きる意味になる。 「居室は余市たちの隣りを借りよう、それで、見せつけてやろう。どうみても、瑠璃さんの方が柚羽さんより家事も上手そうだし、大人っぽくて綺麗だし。…衣もたくさん仕立ててくれたんだろ? 余市に自慢してやろうっ!」 「もう、何考えていらっしゃるんですか! それに柚羽様を侮辱したら、許しませんわよ!」 「…へ?」 「わたくし。満鹿様と同じくらい、柚羽様のことが好きですの。お忘れにならないで?」 「え!? …何だよ〜、それはないだろ〜!!」
狭い部屋の壁にふたりの笑い声が弾けた。開け放った窓から流れてくる闇色の気が安らかな空間に、涼しさを運んでくる。肩にひんやりとしたものが触って、ぶるっとした。その震えを何と取ったのか、瑠璃が再び胸にしがみついてきた。 「…頑張り…ましょうね?」 その震える声が切ない。でもふたりがこうして触れ合える事実だけは本当だ。何者にも代え難い。それを頼みに前を向いていこうと思う。 もうこの人は氷の中に閉じこめられる存在ではない。匂やかなその姿で満鹿を魅了し続ける常夏の花になる。それをあでやかに咲かせ続けるために頑張ろうと思う。この人のためなら頑張れる。 「…うん」
これから起こることを想像すれば、怖い。それは正直なところだ。だが、乗り越えれば春が来る。ふたりを包み込む幸せの空間は手を伸ばせば届く場所にあるのだ。 いつしかどちらからともなく、安らかな寝息に変わる。天の輝きに照らし出される愛の形はしとねの上、しっかりと繋がれていた。それは、未来へと。 了(20021003)
|