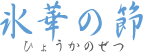|
注:出来れば「てのひらの春」も読み終えてからの方がいいかも? 肩の力を抜いてどうぞ。
真夏は朝からもう暑い。南峰生まれの満鹿も1年以上をこの都で過ごしたためか、すっかりこちらの気候に身体が慣れてしまっていた。それに、何というかまとわりつくような熱気。肌をじっとりとさせる。 「…う…んっ…」 「あれ? …瑠璃さん…?」 ふたり寝用の寝台を置いて、衣類をしまう棚や物入れがあるだけのそれほど広くもない寝所だ。居室はどこも似たような造りになっている。多少の部屋数の変化はあっても、木造の造りも木戸があるだけの大きな窓も似ている。満鹿たちの居室にはこの部屋の他に居間兼客間がある。それから水回り。 それにしても。 まあ、新婚の醍醐味は数あれど、朝と言ったらやはり寝台の上で「おはよう」、ちゅv…とか朝の挨拶をするものじゃないのか? あ、いや…別に普通はどうだとかそんなことを言っても仕方ない。それを言い出したらキリがないことをこのしばらくの生活で悟った。 まず、瑠璃はとても早起きなのだ。 前の晩にあんなことやこんなことや、妊婦相手とはあるまじき行為を思う存分やりまくったとしても、翌朝はすっきりと目覚めてしまう。こうなってくると一度くらいけだるくしとねにうずくまる姿を見てみたいと思ってしまうが、「青の一族」に流れる血は満鹿如きの力ではどうにも出来ない。 それから―― そう頭を回し始めたところで辺りにやわらかな気の流れが起こり、それに続いてたすき掛け姿の瑠璃が現れた。美しい漆黒の髪は邪魔にならないように首の後ろでまとめてある。朝仕事の格好だ。 「満鹿様!? お目覚めになられたなら、すぐにお召し替えになって下さいませ。その肌着は汗になってますのですぐに洗います。脱いでくださいっ!」 はきはきとそう言いながら、さっさと満鹿の肌着をはぎ取っていく。下の肌着の腰ひもに手をかけられたときにはさすがに仰天した。 「ままま…待ってよっ! 瑠璃さんっ…!! あの、自分で着替えるから、ちょっと待っていて」 「そうですか? じゃあ、すぐにお持ち下さいね」 「あの――、瑠璃さん?」 「…はい?」 新しい肌着を手にしたところで、おずおずと声を掛ける。戸口に向かって歩いていた瑠璃が足を止めて振り返る。一応口元は緩やかだ。それを確認してから次の言葉をかける。 「ちょっと…もう一度、ここまで来てくれる?」 瑠璃が小さな声でくすりと笑う。こちらの言いたいことが分かったのだろう。首をすくめて一息ついてから、もう一度寝台のところまでやってきた。 「おはようございます、満鹿様」 すっと寄り添った身体から洗濯粉の香りがする。瑠璃は洗濯魔でもあったのだ。一度身に付けたものは脱ぐなり洗ってしまう。そんなに洗ったら布地が傷みそうなものなのだが、それがどうしたことか彼女の洗い上げた衣はふんわりとしてとても心地よい。独身寮の洗い場に出していた頃とは全然違う。洗濯の干し方だってぴちっとしている。 「おはよう、瑠璃さん」 「はい、では食事のご用意も出来てますから。すぐにおいでになって下さいね?」 「瑠璃さ〜んっ…」 「もう、お務めに遅れますわよ。満鹿様がきちんとして下さらないと、妻であるわたくしが笑われるのですから。しっかりして下さいませ」 そう言いつつもその言葉の響きは甘やかでときめいてしまう。去っていく背を見ながら、次のふたりの合わせた休日はいつかなとか、ふと考えた。
食卓の上にはちまちまと小さな小皿がたくさん並んでいる。瑠璃はどかんと大皿で出したりしない。そして一度の食事に6品も7品も作る。上品な量で。満鹿の田舎では朝の食事は五目粥と果物だった。しかも大鍋のまま食卓にどんと置かれて、それをおたまで皆が勝手にすくって器に盛る。 「足りなかったら仰って下さいね。朝食はきちんと摂らないと、お昼まで保ちませんよ?」 そう言われなくても、瑠璃の手料理だったらいつも食べ過ぎてしまう。何だか遠征から帰ってから太った気がする。この年で中年太りはないだろう、ちょっと午後の剣の稽古では頑張ろうと思ってしまう。蒸し暑い気候でも食べやすいように皿の総菜はひんやりしているものが多い。食が進むのも当然だ。 「あの、瑠璃さん。この重ね、新しいの作ってくれたの?」 今朝、用意されていた衣は見たことのない新しいものだった。うす水に若草色の刺し文様を控えめに散らした涼しげな重ねで、生地のせいか羽織っても涼しげだ。夏のお務めはぴしっと着込むのがことのほか辛い。そう言えば少し前にそんなことを言った気がした。 「かや織りなので、肌に付く部分が少ないのですよ? これからの季節にはその様な衣も必要かと。それほど手も込んでおりませんが、当座はそれでしのいでくださいませ」 「ううん、そんなことないよっ! 嬉しいなあ〜、瑠璃さんは本当に何をやっても上手なんだもの。ああ、こんなの着てたら、みんなに羨ましがられるぞ〜」 「…満鹿様」 「あまり、目立つようにはなさらないでくださいませ。…御館には青の者もたくさんおりますから…」
ふたりのことは、瑠璃の実家がある一族に一応認めて貰った。でも自分が歓迎されない人間であることは雰囲気で察することが出来た。苦虫を噛みつぶしたような瑠璃の父親。白い顔をした母親。戸惑いの表情を隠せない兄弟たち。 規律正しい「北の集落」そこに属する青の一族。瑠璃の実家はその一族の分家筋に当たる家柄だった。瑠璃が同じ分家の頭領に嫁ぐのは、生まれ落ちたときから決められていたことなのだ。多産で知られていた瑠璃の家は頭領の跡取りを生むお役目を申しつかった。驚いたことにその頭領にはその時もはや妻がいた。しかし瑠璃が年頃になる頃にはもはや子を産めぬ身体になる。そうなったら、瑠璃が後添えに入るのだ。 それを覆すことが出来たのは、畏れ多くも竜王様の一の侍従である多岐様の書状があったから。北の集落の長の意見であれば従うしかないだろう。 そんな過程があるふたりだ。この先だってどうなるか分からない。瑠璃はそう言いたいのだろう。
「大丈夫だよ、瑠璃さん。俺、この頃は落ち着いてきたって皆に言われるんだよ? …父親の貫禄だって」 「まあ…」
眩しいほどの手つきで綺麗に亜麻色の髪が結い上げられる。襟元の崩れもなおして貰って、袴帯の位置も改めて貰い…まるで子供のようだ。 「…さ、参りましょうか?」
ささやかな庭先には洗濯物が揺れている。さっき脱いだばかりの肌着ももちろん掛かっている。瑠璃はもしかすると全てに置いて普通の人の2倍は身体を動かしているのではないか? 彼女がだらしなく休んでいるところを見たことがない。眩しい光に照らされた空間にも雑草ひとつ生えてない。 「おはよう、満鹿っ!」 「やだ〜ちょっと待ってよ〜。あれ? 懐紙が見つからない〜どうしよう〜」 「…おはよう、余市…と、柚羽さん?」 戸口から見える部屋の中が何だかガチャガチャしている。脱いだ衣とかがそのまま椅子の背に掛けられていたりして。その上、今日は洗濯もしていないらしい。物干し竿は棒のままだ。 「あ、満鹿様っ、瑠璃様っ…おはようございますっ!!」 それなのに余市ときたら、まあ、とろけそうな笑顔でその姿を見つめてる。 「柚、もう髪が乱れてる…ほら、ちゃんと着物は前を合わせて…」 「なあ、見てくれよっ! 余市〜、瑠璃さんが新しい衣を仕立ててくれたんだ。すごいだろ〜」 一応はたしなめられたけど、余市にくらいいいだろう。だって、自慢せずにはおれないようなすばらしさなのだ。衣も素晴らしいが、それを仕立ててくれた瑠璃も素晴らしい。余市なんて、去年と同じ夏衣だ。 「へえ、綺麗な色。それに、涼しげだね…」 「ふふん、いいだろっ!」 すると、後ろからぐいっと衣を引かれる。振り向くと、憮然とした表情で瑠璃が睨んでいた。美人が睨むと滅茶苦茶怖い。いいじゃないか〜余市の前くらい、はしゃがせてくれよぉ〜。 満鹿の心の叫びを聞いたのか聞かないのか、とにかく瑠璃は衣を掴んだ手をほどくと、すすっと柚羽の元に歩み寄った。 「柚羽様、おはようございます。今朝も素敵な髪ですね…やはり、器用なだんな様を持たれるとこんなに美しくして頂けて。全く羨ましい限りですわ…ねえ…」 な、何なんだっ!? どういうことなんだ? まあ、衣の自慢をして、妻の自慢をすると言うことは、イコール柚羽を卑下することになってしまうかも知れない。だってさ〜本当のことじゃないか!? 何だって瑠璃は柚羽のことになるとムキになるんだろう…!? 「そーなんだ、何しろ柚の髪は本当に美しくて、どんな風にしようかと毎朝悩んじゃってさ〜。今日の、どう? ちょっとこの辺の巻きを工夫してみたんだけど…」 「まあ、素敵。ここの紐の合わせ方もいいですわ…柚羽様、本当にお美しいですわよ。後ろじゃご本人は良く見えませんものね…」 「ああん、大丈夫? 派手じゃない? 平気かなあ…」 この娘も人より目立つことを良しとしない。大体、今、御館の侍従の中で一番人気の夫を持ってしまったのだ。侍女仲間からの攻撃もすごいらしい。それも余市が務めのときにあくびをひとつしただけで「淫乱なヘビ女」とか言われるそうなんだからどうにもならない。 そんな会話を和やかに交わしながら、3人はずんずんと進んでいく。物干し台の前に満鹿はひとり取り残されていた。 「おい〜? 置いていかないでくれよ〜!?」 慌てて追いかける。やっと瑠璃の隣りに陣取ると、誰にも見えない仕草で彼女が満鹿の手の甲をきゅっとつねった。 「…って!!」 「どうしたんだ、満鹿? 石にでも躓いたか?」 「…何でもない…」 「今日も1日、頑張ってくださいませ。…お父様」 前を行くふたりに聞こえないように背伸びして耳元に囁いてくる。思わずぽーっとしてしまうと、彼女はさっと身を離した。
御館への道は夏草が両脇に生え揃い、さやさやと揺れている。この道がずっと続いている気がする、どこまでもどこまでも穏やかに続いている気がする。 眩しすぎる光も自分へのエールの気がして、満鹿はすっと背筋を伸ばした。 了(20021114) |
|
追記>>「てのひら」と「氷華」合同の「らぶえっちキャラへの質問」があります♪
多少、本編のシリアスタッチが崩れてもいいやと思う方は、どうぞお楽しみくださいね! |