機上の空論
機体を読む 航空機から見た英国
今日、軍用を含めた航空機製造で、米国がリードを保っていることに異論を挟む方はいないと思います。数多くの傑作機を産み出し続けています。しかし、第二次大戦後のある時期まで、ユニークな設計と高い技術で航空界をリードした国がありました。英国です。
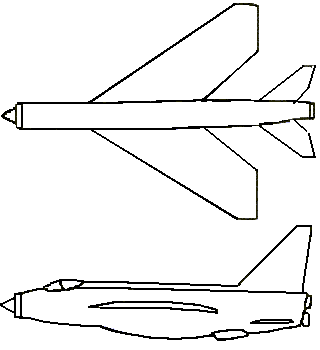 先ずは幾つかの英国機を思い浮かべてみてください。民間機なら、世界初のジェット旅客機コメットや超音速旅客機コンコルド、また、日本の航空会社でも飛んでいた、ヘロン、ダブ、マラソン、バイカウントなどを思い浮かべる方もあるでしょう。更に大型4発リアジェットVC10、アメリカの航空会社が短距離ジェット旅客機として最初に使用したBAC111、3発リアジェットの元祖トライデント、高翼4発STOLのBAe146などユニークなジェット旅客機もあります。小型機なら、多くのパイロットを育てたタイガーモス、斬新なオプティカ・スカウトもユニークな存在です。軍用機まで範囲を広げると更に面白い機体が目白押しです。大戦機からは、スピットファイアー戦闘機、ランカスター爆撃機、木製の高速機モスキート、ジェット機の草分けミーティア、戦後のジェット機では、キャンベラ、ヴィクター、ヴァルカンなどの爆撃機、双胴のヴァンパイアー、ハンター、ライトニング、VTOLのハリアーなどの戦闘機、バッカニアー攻撃機などいずれ劣らぬ、ユニークな機体ばかりです。
先ずは幾つかの英国機を思い浮かべてみてください。民間機なら、世界初のジェット旅客機コメットや超音速旅客機コンコルド、また、日本の航空会社でも飛んでいた、ヘロン、ダブ、マラソン、バイカウントなどを思い浮かべる方もあるでしょう。更に大型4発リアジェットVC10、アメリカの航空会社が短距離ジェット旅客機として最初に使用したBAC111、3発リアジェットの元祖トライデント、高翼4発STOLのBAe146などユニークなジェット旅客機もあります。小型機なら、多くのパイロットを育てたタイガーモス、斬新なオプティカ・スカウトもユニークな存在です。軍用機まで範囲を広げると更に面白い機体が目白押しです。大戦機からは、スピットファイアー戦闘機、ランカスター爆撃機、木製の高速機モスキート、ジェット機の草分けミーティア、戦後のジェット機では、キャンベラ、ヴィクター、ヴァルカンなどの爆撃機、双胴のヴァンパイアー、ハンター、ライトニング、VTOLのハリアーなどの戦闘機、バッカニアー攻撃機などいずれ劣らぬ、ユニークな機体ばかりです。
これらの機体を一堂に並べたら、とても面白い景観でしょう。「グロテスク」という形容詞がこれほど当てはまるものはないという景観は、見る者を圧倒することでしょう。そして「性能の良い機体は美しい外観を有する」との格言を疑うことでしょう。これらの形は性能の追求によって生みだされたのですから。
その好例は、右の図で示したライトニング戦闘機でしょう。基本レイアウトがまとまったのが、1948年8月で、試作機のロールアウトは54年5月、同初飛行が、同年8月です。3回目の飛行で、水平飛行で初めて音速を超えたターボジェット機となりました。設計思想の神髄は、「推力を最大限にし、抵抗を最小限にする」というものです。そのために、60度の後退角を翼に持たせ、2基の軸流式エンジンを縦に並べるという荒業を使いました。その結果、リヒート(アフターバーナー)なしで音速を突破し、上昇能力も当時としては驚異的な4分で
30,000ft を記録しました。
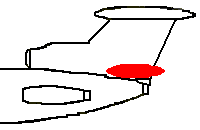 民間機で面白いのはトライデントでしょう。B727が席巻した3発リアジェットの元祖で、老舗のデ・ハヴィランドが構想したものです。その後の業界再編で製造はBACに引き継がれました。派生型は、1,1E,2E,3B,スーパー3Bと5種類あります。英国欧州航空(BEA)向けの2E型に世界で初めて自動着陸機器が搭載されたことは特筆すべきでしょう。また、3B型、スーパー3B型が、実は3発ではなく4発機であることも見逃せません。先述の派生型のうち、1E,2Eはディープストール対策としての翼の改良であったのに対して、3Bは、胴体を5m
(16ft 5in) 延長、よくも広げる大規模な変更でした。その結果、手持ちのエンジン推力が不足し、離陸用補助エンジンを尾部に追加する設計となったのです。右の図の赤い部分がその「第4エンジン」です。無駄な重量を加えるようにも思えるのですが、私としては、この強引なやり方に魅力を感じています。
民間機で面白いのはトライデントでしょう。B727が席巻した3発リアジェットの元祖で、老舗のデ・ハヴィランドが構想したものです。その後の業界再編で製造はBACに引き継がれました。派生型は、1,1E,2E,3B,スーパー3Bと5種類あります。英国欧州航空(BEA)向けの2E型に世界で初めて自動着陸機器が搭載されたことは特筆すべきでしょう。また、3B型、スーパー3B型が、実は3発ではなく4発機であることも見逃せません。先述の派生型のうち、1E,2Eはディープストール対策としての翼の改良であったのに対して、3Bは、胴体を5m
(16ft 5in) 延長、よくも広げる大規模な変更でした。その結果、手持ちのエンジン推力が不足し、離陸用補助エンジンを尾部に追加する設計となったのです。右の図の赤い部分がその「第4エンジン」です。無駄な重量を加えるようにも思えるのですが、私としては、この強引なやり方に魅力を感じています。
その他の機体については書くのを控えますが、英国機に共通して言えることは、その先取性と、多少欠点があってもそれを超える長所があれば評価し取り入れる姿勢です。これらが、目的とする性能の追求を支えているのです。その結果荒削りであり、米国製のバランスの良い(別の言葉で言えば「ちゃっかりした」)機体に、(特に民間機は)市場を席巻される事となったのでしょう。売れ行きによって、英国製の民間機は駄作揃いだ、との評価をよく耳にしますが、性能面から考えれば、米国機に勝るとも劣らずと言えます。
この性向は、英国人の気質から来ていると思えます。保守的でありながら先進的であり、紳士的であっても奇行があり、洗練されていながら土臭い、二律背反的な世界が航空機からも窺えます。シャーロック・ホームズやジェームズ・ボンド、そしてビートルズもそんな国で生まれたのです。
機上の空論 目次へ 号外 「温故知新」へ
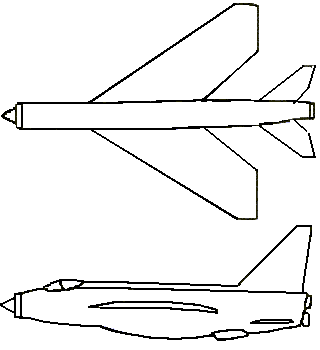 先ずは幾つかの英国機を思い浮かべてみてください。民間機なら、世界初のジェット旅客機コメットや超音速旅客機コンコルド、また、日本の航空会社でも飛んでいた、ヘロン、ダブ、マラソン、バイカウントなどを思い浮かべる方もあるでしょう。更に大型4発リアジェットVC10、アメリカの航空会社が短距離ジェット旅客機として最初に使用したBAC111、3発リアジェットの元祖トライデント、高翼4発STOLのBAe146などユニークなジェット旅客機もあります。小型機なら、多くのパイロットを育てたタイガーモス、斬新なオプティカ・スカウトもユニークな存在です。軍用機まで範囲を広げると更に面白い機体が目白押しです。大戦機からは、スピットファイアー戦闘機、ランカスター爆撃機、木製の高速機モスキート、ジェット機の草分けミーティア、戦後のジェット機では、キャンベラ、ヴィクター、ヴァルカンなどの爆撃機、双胴のヴァンパイアー、ハンター、ライトニング、VTOLのハリアーなどの戦闘機、バッカニアー攻撃機などいずれ劣らぬ、ユニークな機体ばかりです。
先ずは幾つかの英国機を思い浮かべてみてください。民間機なら、世界初のジェット旅客機コメットや超音速旅客機コンコルド、また、日本の航空会社でも飛んでいた、ヘロン、ダブ、マラソン、バイカウントなどを思い浮かべる方もあるでしょう。更に大型4発リアジェットVC10、アメリカの航空会社が短距離ジェット旅客機として最初に使用したBAC111、3発リアジェットの元祖トライデント、高翼4発STOLのBAe146などユニークなジェット旅客機もあります。小型機なら、多くのパイロットを育てたタイガーモス、斬新なオプティカ・スカウトもユニークな存在です。軍用機まで範囲を広げると更に面白い機体が目白押しです。大戦機からは、スピットファイアー戦闘機、ランカスター爆撃機、木製の高速機モスキート、ジェット機の草分けミーティア、戦後のジェット機では、キャンベラ、ヴィクター、ヴァルカンなどの爆撃機、双胴のヴァンパイアー、ハンター、ライトニング、VTOLのハリアーなどの戦闘機、バッカニアー攻撃機などいずれ劣らぬ、ユニークな機体ばかりです。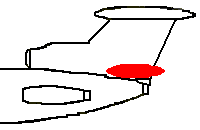 民間機で面白いのはトライデントでしょう。B727が席巻した3発リアジェットの元祖で、老舗のデ・ハヴィランドが構想したものです。その後の業界再編で製造はBACに引き継がれました。派生型は、1,1E,2E,3B,スーパー3Bと5種類あります。英国欧州航空(BEA)向けの2E型に世界で初めて自動着陸機器が搭載されたことは特筆すべきでしょう。また、3B型、スーパー3B型が、実は3発ではなく4発機であることも見逃せません。先述の派生型のうち、1E,2Eはディープストール対策としての翼の改良であったのに対して、3Bは、胴体を5m
(16ft 5in) 延長、よくも広げる大規模な変更でした。その結果、手持ちのエンジン推力が不足し、離陸用補助エンジンを尾部に追加する設計となったのです。右の図の赤い部分がその「第4エンジン」です。無駄な重量を加えるようにも思えるのですが、私としては、この強引なやり方に魅力を感じています。
民間機で面白いのはトライデントでしょう。B727が席巻した3発リアジェットの元祖で、老舗のデ・ハヴィランドが構想したものです。その後の業界再編で製造はBACに引き継がれました。派生型は、1,1E,2E,3B,スーパー3Bと5種類あります。英国欧州航空(BEA)向けの2E型に世界で初めて自動着陸機器が搭載されたことは特筆すべきでしょう。また、3B型、スーパー3B型が、実は3発ではなく4発機であることも見逃せません。先述の派生型のうち、1E,2Eはディープストール対策としての翼の改良であったのに対して、3Bは、胴体を5m
(16ft 5in) 延長、よくも広げる大規模な変更でした。その結果、手持ちのエンジン推力が不足し、離陸用補助エンジンを尾部に追加する設計となったのです。右の図の赤い部分がその「第4エンジン」です。無駄な重量を加えるようにも思えるのですが、私としては、この強引なやり方に魅力を感じています。