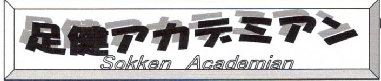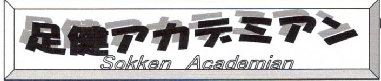『常に技術革新を』
第57号 08.12月号
2008
page 1
も く じ
巻頭言「常に技術革新を」 ・・1 台湾論文「自閉症の子供と脚底按摩」・・3
「崩れた体のバランスを取り戻す」・・1 「自閉症の子を持って①」 ・・4
ジョゼフ神父便り ・・・2 「自閉症の子を持って②」 ・・4 足もみの神経伝達が効果を生みだす ・・5
折田 充
2008年も終わりますが、1998年9月に独立開業して丸10年が過ぎました。独立するきっかけは働く環境に対する閉塞感もありましたが、最大の動機は自分で考えた足もみ技術の工夫を充分に活かせない拘束感を強く感じたことです。
「もっと良い方法があると思うのになあ」と感じながら仕事をしていました。教わった手技法を10年、20年と続けるのも一つのやり方だと思います。しかし教わった方法を単に崇めて慣行墨守型で続けるだけでは、生き生きした足もみを続けることはできません。
一年が終わりかけるといつも思うのですが、人は生きて常に変化しています。自分の技術もお客さんの体調の状況も常に変化しています。その変化に対する適時な対応は必要です。技術の微調整であったり、もしくは大転換があったりするのは当然のことです。
私にとってこの10年間は常に足もみ道を歩み続けた月日でした。幸いにして同じお客さんに5年、10年と続けて来て頂いています。中には私がこの健康法を習った直後からのお客さんも来てくれています。60歳だった方が80歳になられていますが、お互いに「齢だねえ」という会話をします。この方の20年間の体験は私の足もみの技術の変化を示す生き字引みたいなものだと思います。
お客商売をしていると、つくづく「お客さまは神様です」と思います。この11月の台湾でも「足健学術・技術交流会」でのテーマにこの不況を乗り越える成功パターンの発表がありました。こういう時期には、もし単に揉むだけの足もみ技術に対してはお客さんがお金を使わなくなります。そんな状況でもお客さまが来てくださるように保つためには、やはり技術の良し悪しが大きく関係してきます。
自分の足を自分で揉んでいる人にとっても、体調の変化は季節ごとにありますし、年齢とともにも進行します。道具を使っている方はその道具の使い方にも工夫の余地がたくさんあるはずです。新しい揉み方を見つけると足もみが楽しくなります。
『崩れた体のバランスを取り戻す』
私の心と体のバランスが崩れた始めたきっかけは、平成14年に左眼の眼底出血をおこして視力低下 (左眼0.1、右眼1.2)により物が歪んで見え始めたことからです。それから先はまるで坂を転げ落ちるように次々と病が私に襲いかかってくることになります。
足健ぷらざ横浜 平山澤枝
高低が分らない、遠近も分らない、杖を使って歩くときに筋肉に負担がかかる、それも左右の筋肉の負担の差がひどい。こうなってくると、持ち前の好奇心、やる氣をなくし、うつ状態に落ちいってしまいます。眼底出血が見つかってから2年経ち不自由な生活にも工夫しながらだんだん慣れてきた頃、平成16年でしたが、左肩関節内の石灰化による激痛が始まりました。腕も上がらず、関節内の注射と鎮痛剤とリハビリが1年続きました。やっと痛みから解放された頃、今度は反対側の右肩の関節の石灰化による腱板症になりました。左手の不自由さで右手を使い過ぎたためと思われます。肩手症候群による痛み、上腕前後のしびれ、第4指・第5指の軽い麻痺、握力低下、運動障害、さらには睡眠不足による強度の疲労感に悩まされることになりました。今度は右手の治療が始まりました。右利きの私には、本が読めない、字が書けない、包丁が使えない、髪が梳けない、雑巾が絞れない、杖を使っての生活、痛みと不自由さに負けそうになりました。苦しいから辛いのではなく、こういうふうに病が続くと夢がなくなってきて辛くなります。「こんなはずではない」「今の自分は本当の自分ではない」「違う」「違う」とイライラの毎日でした。