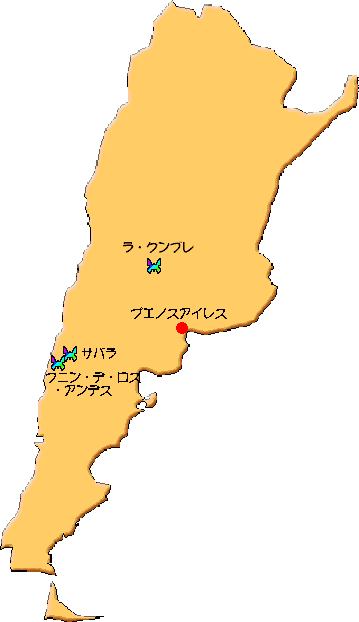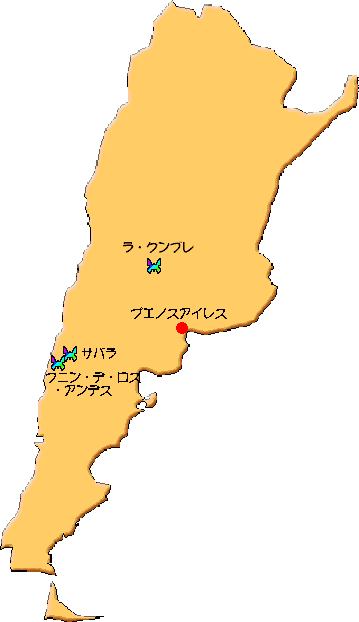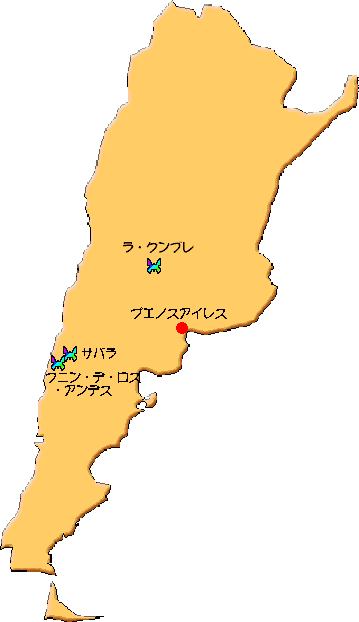
第1回:1999年12月25日 〜 2000年 1月 6日
 1 中部
 (1)自然について
 アルゼンチン中央部には、標高1500m位のコルドバ山脈が連なっています。南北の違いがありますが、宮崎県とほぼ同緯度にある温帯地方です。低地のコルドバ市よりバスで上って行くと標高が700m〜1000m位の高原地帯に至ります。森林は、この高原地帯までの間の渓流沿いに豊かに広がっていますが観光名所になっているみたいで、人と車で賑わっていました。高原地帯に入ると、急に森林はなくなり貧弱な草原へと移行します。山は、この高原地帯から聳えることになるので、余り高くは感じません。街は、山の麓である高原に広がっていて、そこから森林が始まりますが山の頂まで覆われていることは非常に少ないです。また柵に囲まれた私有地が多いため、昆虫採集する場所を見つけるのが大変です。  アルゼンチンは、サマータイム制を採用している訳ではないのですが、標準時間が1時間位遅れていて、午後1時頃、太陽が真南に来ます。従って、夜はなかなか暗くなりません。またレストランは、夜8時や9時頃からでないと開店しないので、時間を上手に使わなくてはなりません。  アルゼンチンの旅は、非常にゆったりしていて疲れるようなことはありませんでした。人々も大らかで南米の一国というよりヨーロッパの国という感じがします。  この時季は、日本でいう初夏に当たりますが、標高が高いため朝夕や雲に覆われた日などは、ひんやりとして肌寒いくらいです。
 (2)昆虫について
 南米といっても大変広く、アマゾンを中心とした熱帯・亜熱帯地方しか思い浮かばないかも知れませんが、温帯・寒帯地方も存在します。アルゼンチン中部は、温帯南部に位置しています。  コロラド山脈での採集は、まず場所探しから始まります。森林の木々は、余り瑞々しさは感じられませんが生い茂っています。冬は雪が降り積もる場所なので、新熱帯区の昆虫は少ないと思われますがしっかり生息しています。  ポリダマスアオジャコウアゲハ、トアスアゲハ、センナエオオキチョウ、ウェニラエヒョウモンドクチョウなど新熱帯区特有のチョウがいます。多分多くの昆虫は、アンデス山中起源の温帯・寒帯適応の昆虫たちでしょう。ミヤマモンシロチョウ各種、カリエアカタテハ、ウィルギニエンスアカタテハ、ケソニアモンキチョウ、各種ミナミヒョウモンモドキなどが見受けられます。トンボは少ないのですが、やはり温帯・寒帯特有のマダラヤンマの仲間がいます。  甲虫は、面白く、カタビロオサムシは、街中にもいますが見つけたのは踏み潰されたのばかりでした。その他にも赤銅色のオサムシもいました。同じように歩き廻っているのは、アブレルスツノカブトムシです。牧場脇の小径で、緑色のコガネムシに混じって歩き廻っていました。小形のカブトムシの割には、立派な角を持っています。他にもナンベイコカブトムシやサイカブトムシの仲間もいます。  セミは2〜3種類啼いていましたが、時々啼くぐらいで五月蠅いと言うことはありません。通りすがりに、藪の中で羽ばたくセミと、街中で転がっていたセミの2種類を採ることができました。
 2 パタゴニア
 (1)自然について
 私の旅は、余り予備知識を得ずに見たまま有るがままを受け止めて感じる旅です。アルゼンチン南部のパタゴニア地方は、具体的なイメージは持っていなかったし、昆虫もあまりいないだろうと思っていたのですが、一度は歩いてみたいところでした。  四角く区切られた畑ばかりで、森林の全くないパンパ地方を空から眺めながら行くと、途中から緑色のない真っ白な土地へと移ってきました。最初は、うっすらと雲がかかっているのかなと思っていたのですが、どうも違います。緑がないのです。”これでは昆虫はいないだろうな。”パタゴニア北部の州都ネウケンは、そんな土地にありますが川沿いにあるので四角く区画化された街郊外は背の高いポプラの木で囲われていて異国情緒たっぷりです。そこからアンデス側へバスで3時間の所にサパラという町があります。緑は、全くないと思っていたのですが、そうでもありません。ただ土ではなくて砂地なので、ぽつぽつと木生菊やイネ科植物が生え、道路沿いにはアブラナ科の花など数種が花を咲かせています。雨が強く降ったときもありましたが砂地なので、すぐ水は引いてしまいます。また風も強いので、濡れた葉もすぐ乾いてしまいます。この風景が延々と続くのです。家や町があるところ以外には、殆ど木々はありません。川沿いに貧弱な柳などが生えているだけです。サパラより更に、アンデスよりに行くと、砂地に加えて岩がごろごろした土地も所々に現れてきます。植林された針葉樹も多く見られますが、やはりここも砂に埋め尽くされた土地でした。
 (2)昆虫について
 半砂漠化したこの土地に、あまり昆虫はいないと思っていたのですが、そうではありませんでした。サパラの町外れの原野には、菊の小さな黄色い花が咲いています。  やはり気に入ったチョウは、ぎんぎらぎんに輝きながら翔び交うチリギンジャノメです。この地にごく普通にいる優勢種で、数は多いのですがジグザグに素早く翔ぶので採集するのは難しいチョウです。他にも銀色ではありませんが、モラニアチリギンジャノメ、レスビアモンキチョウ、カリエアカタテハなど数は少ないがいました。  ここは、チョウではなく甲虫が案外います。非常に固い殻(昆虫針を何本も曲げてしまった)のゴミムシダマシが何種類もいます。乾燥した地を歩き廻っているだけあって、標本にするため普段の4倍乾燥器にかけても変わることはありませんでした。こんなことは、初めてです。菊の花には、小さなタマムシが来ています。なかなか美しい3種類のタマムシです。何の糞か分かりませんががタマオシコガネもいました。  ヤンマが飛んでいましたが、多分ヒメルリボシの仲間でしょう。  一番驚いたことは、こんな原野にもセミがいたことです。多分、木生菊を餌にしているのでしょうが、小形のセミがいます。そして更に小さなセミがイネ科の茎に掴まって啼いていました。  アンデスの山麓まで行くと、やっぱりチリギンジャノメがいっぱいいますが緑が近づいてくるため種類が少し増えます。特に、アミメモンシロチョウとヒメギンボシヒョウモンが多くいます。そして川沿いには、イトトンボ、トンボ、エゾトンボ、サナエトンボ、ヒメルリボシが飛んでいました。ただアンデス山中は、国立公園が多いので注意しなければなりません。
|