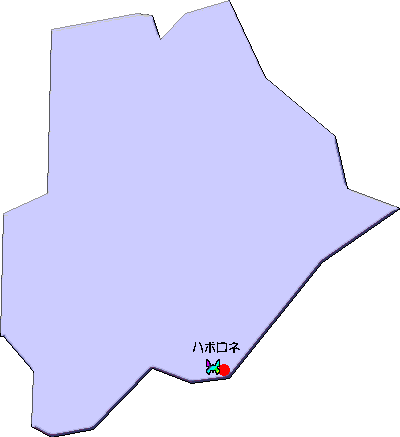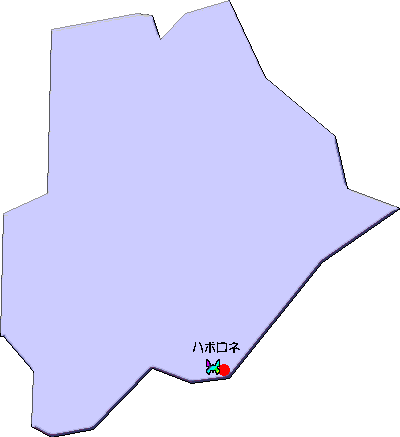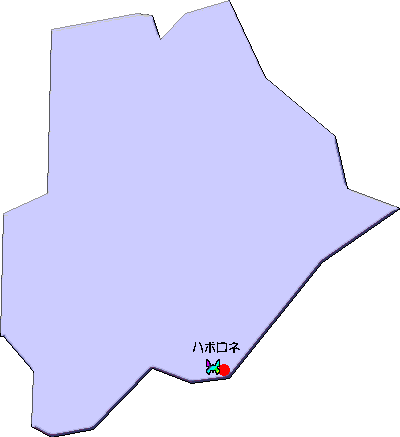
第1回:2003年12月21日 〜 2003年12月25日
 (1)自然について
 ボツワナに行くまでは、半砂漠地帯をイメージしていたのだが、アカシアなどの棘のある木々のが疎らに生えているサバンナ地帯であった。それ故、意外と緑は濃く見え、ハボロネの街は、サバンナの木々を残して見事な街を造り上げているように思えた。  街中は、緑が多く花も多いためサバンナのチョウが翔び廻っていた。そして郊外に出ると、そこは、本当のサバンナ地帯となるが野生動物を見ることは出来ないだろう。近くにダム湖があるが許可がないと入域出来ないようであった。また近くの山、カレ山も公園ではないのだが、“残すのは足跡、取るのは写真だけ”と書かれた看板が立っていた。
 (2)昆虫について
 サバンナの昆虫相が、おおよそ分かったような気がした。爪楊枝みたいな棘のあるアカシアでも昆虫には、全く害にならない。ダム湖近くのサバンナとカレ山とは3kmほどしか離れていないにも関わらず、カレ山の方には、チョウは殆ど見かけなかった。植物相の差があるように見えなかったのだが。  アゲハチョウは、アフリカオナシアゲハのみである。  シロチョウは、9種類のツマアカシロチョウ、そしてやはりアフリカの代表種、アウロタヘリグロシロチョウとフロレッラウスキシロチョウなどである。  マダラチョウは、日本より2回り位大きいカバマダラが翔んでいた。  タテハチョウは、メスアカムラサキ、イリティアヒメキマダラタテハ、アフリカタテハモドキ、ルリボシタテハモドキ、ヒメアカタテハ(未採集)、2種のホソチョウなどである。  シジミチョウは、アフリカ特有のアカガネシジミ、カクモンシジミなど数種だけであった。  ジャノメチョウとセセリチョウの仲間は、今回は一匹も見ることがなかった。  トンボは、やはりここでも汎世界種のウスバキトンボが数多く見受けられた。その他のトンボは、2〜3種くらいしか見ることが出来なかった。  セミは、ニイニイゼミの仲間が1種類いたが、黒っぽい木の幹そっくりの色合いをした翅をしているので、近くで啼いていても見つけるのは困難であった。  乾燥地帯のゴミムシダマシは、やはりユニークである。細身のアフリカゴミムシもすばしっこく走り廻っていた。ここでも大きなマメハンミョウを見つけた。そして、ちょっと背を丸めたフナガタタマムシやハナムグリは、花蜜を求めて訪れている。あちこちに落ちている牛糞には、緑色や赤銅色のタマオシコガネが群がっていた。
|