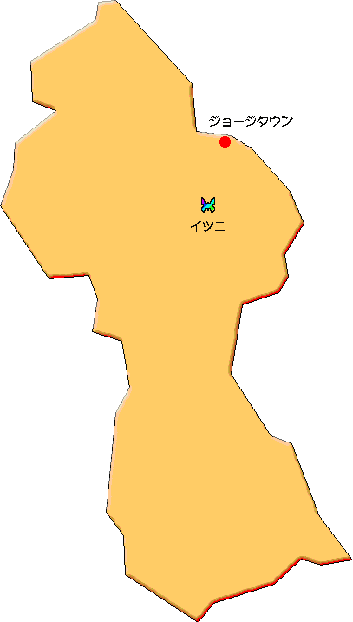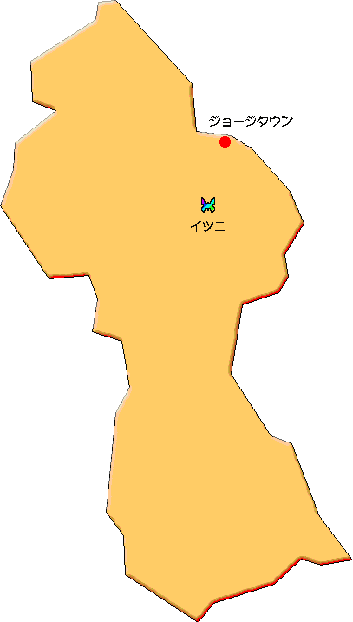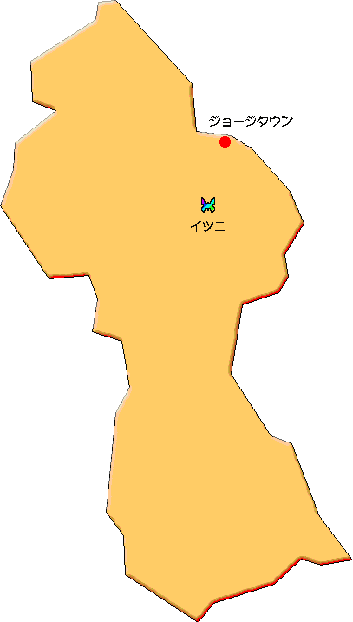
第1回:1996年 8月16日 〜 1996年 8月21日
 (1)自然について
 ガイアナの首都ジョージ・タウンからデメララ川沿いに南下すること100km2時間でリンデンの町に着きます。ここまでは、何とか舗装された道が続いています。しかし、その道もここまでです。この先は、もちろん舗装されていないし、そのうえ道は、なんと白い砂の道なのです。この辺り一帯は、白い砂の大地でした。そして、ところどころに赤茶けたラテライトの土地が僅かに広がっている程度なのです。そんな土地なので森林の発達は悪いのですが、それなりにはあります。道が悪いのでリンデンの町から次の村イツニまでの60km(この間には、一軒の家も建っていない)を約2時間かけて車は走ります。イツニの村は、30件ほどのこぢんまりした村です。そして運良く泊まるところもありました。ホテル(?)は、村の中心から外れます(歩いて5分くらい)が大きな1軒屋でした。殆どの家がそうなのですが、下は吹き抜けになっています。2階のドアの鍵を開けると中には、2人部屋が4つに長椅子の置いてある居間が1部屋、そして食堂がありました。しかし今は、殆ど使われていないみたいで中は荒れて、 ベッドも枠だけのものが殆どです。4つのベッドには、シーツと枕はありましたが、毛布等の掛けるものは何もありません。トイレ、バスタブ等の設備もしっかり付いているのですが、如何せん水が出ないので栓を捻ればとはいきません。窓には全て網が張ってありますが、大分傷んでいてある程度虫の出入りも自由でした。水は、貯水槽からバケツで運んできます。貯水槽も飲料用とその他で別に設けてあり、水は全て、屋根へ雨水を溜めるようになっています。飲料用の貯水槽は、家の近くにあり、雨水は網を通して蓄えられ、日光の入らぬようになっていますが、もう一つの貯水槽は井戸と同じく上方は開いたままでした。ホテルに来たとき”働きに来たのか?”と訊ねられましたが、この村に私のような観光客が来るなんて皆無に等しいと思われます。そして、その珍客も、日本からです。  ホテルに暫くお客がいなかったのでしょう。最初に風呂に入った(バケツの水で洗う)時、ここぞとばかりブユ(?)に目一杯刺されてしまいました。小さいので全く気付かなかったし、痒みも2日目からで襲ってきました。  村には1軒店があり、生活必需品が並んでいます。そして、そこで作っている菓子パンも並んでいて、それは、私の毎日の朝食となりました。また、そこは唯一の食事をする場所にもなり、私は毎晩夕食をここで摂っていました。インディカ米のご飯は、まだ温かかったので美味しかったのですが、それ以外には1品(焼きそば、マカロニ、煮豆など)が出るだけでしたので、やはりカロリー的には、不足がちだったと思います。  この村が、私の1週間の昆虫採集の拠点となりました。
 (2)昆虫について
 砂地の土地の上は、やはり貧弱な植生にしかなりません。草地には、ここにもエワレテタテハモドキがいますが、今までのとは少し色合いが違うみたいです。小川が流れている草原には、ヤトロパエカバイロタテハが翔んでいます。そして、時々オオキチョウの仲間が横切ってゆきます。ちょっと黄色っぽいシロスジタイマイもいましたが採ることはできませんでした。近くには大きな池とか川はないのですが、トンボは以外にも多くの種類がいました。地球規模に存在するウスバキトンボ、ハネビロトンボ2種、それから小形・中形種のトンボが数多く群れています。そしてギンヤンマの仲間と、緑色の美しいヤンマも。新熱帯区のヤンマは、緑色の体色を持つのが非常に多いみたいです。草原での採集は、収穫が少ない割には直射日光や白砂による照り返しのため非常に厳しいものです。  小川沿いの径と森林内の径が、2カ所ほどありましたが、奥に行くと湿地みたいになっていて、それより先には入り込めませんでした。チョウはやはり数が少なく、フチドリシジミタテハの1種を除いては同じ種を殆ど見かけることはありません。6日間の採集でエラトドクチョウを4匹掴まえましたが、実際には3種類のドクチョウでした。  ヘリコニウスタイマイを掴まえました。ヘリコニウスタイマイは、モンキドクチョウに擬態していることは有名です。森林の小径を歩いていると向こうからゆっくりとチョウが翔んできます。模様ですぐモンキドクチョウだと分かりました。翔び方もモンキドクチョウそのものです。網を振ると中で、やけにばたばた蠢いています。”あれ変だな”と思い見てみるとタイマイでした。モンキドクチョウは、結局4匹、タイマイはその1匹だけでした。タレスヒメドクチョウとフィリスドクチョウも、これまたそっくりでした。オレンジタテハの仲間も2種類掴まえましたが、それ以外には一度も見ることもできませんでした。一番いい状態の森林は、村から南に歩いて1時間半の距離にあり、途中道草をすると2時間は掛かってしまいます。鬱蒼と生い茂った中に車1台分の径が、ゆっくり歩いて往復2時間ほど続いています。ところどころに陽も射し込むところがあり、そんな径には、モルフォ、ハカマジャノメ、そして様々なシジミタテハが翔んでいました。しかし、やはりここも数は少なく、特に南米特有のトンボマダラは、1匹掴まえただけでした。しかし森林性のトンボは、それなりにいて、カトリヤンマは、日中はすぐ枝に止まるので2種類採ることができました。  諦めていたセミも、1匹叢でもがいていたのを拾いました。  種類も数も少ないですが、これがガイアナです。
|