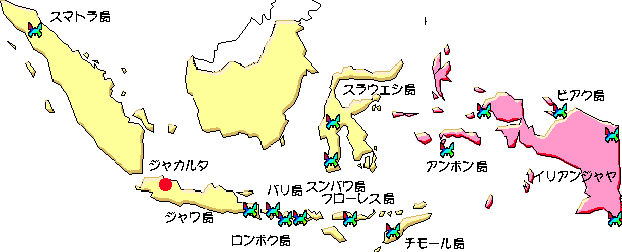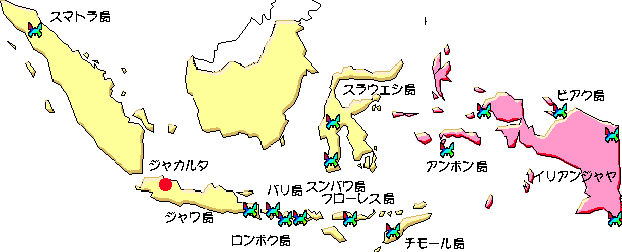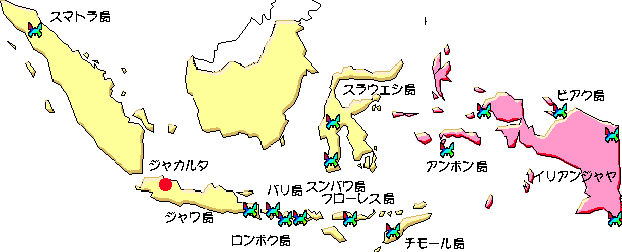
 1 スラウェシ中部
第1回:1990年12月29日 〜 1991年 1月 3日
第2回:1991年 8月12日 〜 1991年 8月16日
第3回:1992年 4月30日 〜 1992年 5月 3日
 (1)自然について
 スラウェシ島南部の玄関口ウジュンパンダンを夕方出発するバスに乗ると、真夜中バスは、漆黒の暗闇の中を移動し、朝早く中部高地のランテパオに着きます。舟形屋根の家屋で有名なトラジャ地方の中心地です。民芸品を売る店が軒を並べていて、多くの観光客が行き来しています。トラジャ地方は、水田、畑が多く、そして竹林も多く存在しています。キーコーヒーのコーヒー豆も、この地方で作られています。平地は、切り拓かれてしまっていますが、山岳地帯は、未だに鬱蒼とした森林に覆い尽くされています。しかしながら、森林を分け入る道が、殆どないのが残念です。  ここは、一年を通して雨が多く、5月、8月、12月に訪れていますが、一日中晴れという日は一日もありませんでした。森林内にヒルが多いのは、このせいです。  この豊かな森林相は、何処にも勝るとも劣らない大自然そのものです。
 (2)昆虫について
 スラウェシ島は、東洋区とオセアニア区の両方に跨り、豊かな自然を醸し出しています。当然、そこに生息する昆虫たちも、非常に多様で豊かです。  ランテパオから下った森林地帯では、アゲハは非常に大きなセレベスアゲハ、モンキアゲハよりひと回り大きいサタスペスアゲハ、際だって美しいブルメイアゲハ、ギゴンアゲハ、ポリフォンテスベニモンアゲハ、コルドスタイマイ、ミロンタイマイ、アンドロクレスタイマイ、他の所より大きいスソビキアゲハなど多くのアゲハがいます。シロチョウは、大きなのはツマベニチョウ、セレベスベニシロチョウなどで、中形のシロチョウは殆ど見かけません。あとは、キチョウ、タイワンキチョウ、アリタキチョウ、トミニアキチョウなどです。タテハチョウは、リュウキュウミスジをふた回り大きくしたイダミスジ、ヘドニアタテハモドキ、ストリガタイシガケチョウ、ティオネウスイシガケチョウなど、やはり他の所のチョウたちよりひと回り大きいです。セセリ、シジミも多種多様でオセアニア区のシジミであるタスキシジミも生息しています。  トンボは、森林地帯の渓流にミドリカワトンボより翅がひと回り以上幅広いムラサキカワトンボがいます。ミナミカワトンボに似た体が青銅色のトンボが数種いて、またフィリピンコシアカトンボよりひと回り大きいトンボやハナダカトンボも2種類ほどいます。  ハンミョウは、渓流沿いの葉っぱに数種類見受けられ、やはり他の地域に比べて大きいようです。
 2 スラウェシ南部
第1回:1992年 8月19日 〜 1992年 8月20日
 (1)自然について
 スラウェシ島のウジュンパンダンより南へ下ると、緑の薄い乾燥地帯へと変わってゆきます。中部地方の緑濃い大地に比べて、圧倒的に少ない緑の大地に、ただ唖然とするだけです。ロンボバタン山へ車で上っても、何処まで行っても森林地帯は存在しません。約1時間ほどの所にある小さな町で降りると周囲には、森林と言えるほどの緑はなく、竹林やら疎林がぽつりぽつりと在り、あとは草原です。ロンボバタンの町までの間も、全然風景は変わりません。  町から約7kmの所に、ビサップという滝があり、少し公園みたいに整理してあって、緑と川がある素敵な場所です。滝の上に行く道があれば良かったのですが、見つけることができませんでした。多分、そんな道があると思うのですが。もう少し周辺を歩いてみたかったのですが、たった一日でしたので、ここの緑を堪能することはできませんでした。途中の道路沿いの木は、緑色の幹をしているので、ちょっと異様な雰囲気がします。
 (2)昆虫について
 乾燥したロンポバタン山ではチョウは、余り見かけませんた。ローゼンベルギカザリシリチョウが、緩やかに舞っていたのが印象的でしたが、それ以外はぱっとしませんでした。トンボも、未成熟のアカスジベッコウトンボの仲間が、少し群れて疎林内にいただけです。ロンポバタン山を更に上って行くといいのかも知れませんが、私には、未知の場所のままです。  滝のあるビサップでは、メナドヒメワモンが下草を這うように翔び、ヘドニアタテハモドキが行ったり来たりしています。ミリナハレギチョウのブルーが美しく燦めいています。ベニモンアゲハに擬態したシロオビアゲハが翔んで行き、大きなトリタエアアサギシリチョウも川沿いに通り過ぎて行きます。川の淀みでは、ハナダカトンボがいました。  全体的に、ちょっと物足りません。半島の南西部側ではなく、南東部側の方がいいのかも知れません。行ってみなくては。
|