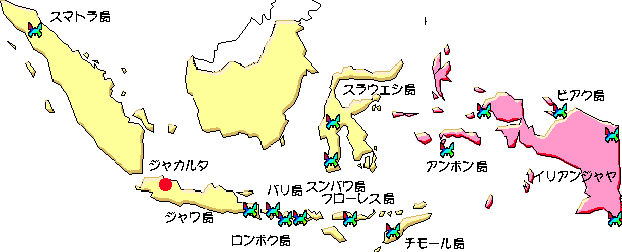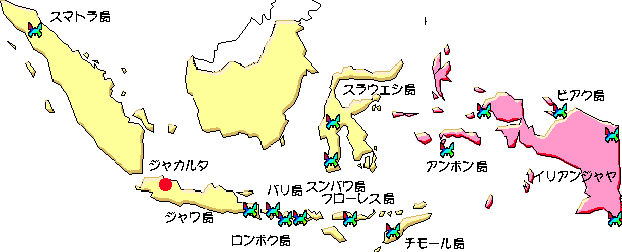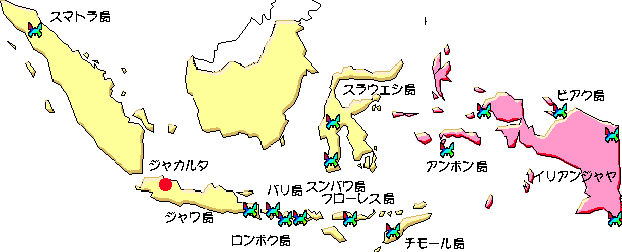
 1 イリアンジャヤ西部
第1回:1994年 8月25日 〜 1994年 8月28日
 (1)自然について
 ニューギニア島の西半分は、インドネシアのイリアンジャヤになります。そのイリアンジャヤの西端にソロンの港町があり、ソロンの空港は、その港から船で約1時間の場所にあります。初めてここに来たとき、空港のロビーを出ると目の前に海が広がっていたので、”え!!”と思ってしまいました。  ソロンの周辺には、余り森林が発達していないと言うよりも、切り拓かれてしまったみたいになっています。海岸よりの場所は、林が殆ど失われ、僅かに残された林は、植林されています。また珊瑚が発達していたと思われるところでは、マングローブ林が発達しており、岩石のような珊瑚の岩がごろごろしています。林の中の道は、伐採された木々の根っこや珊瑚で非常に歩き難いところです。森林地帯もありましたが、そこは開発から辛うじて残った場所で、管理された公園になっていました。ジャングル内は、やはり素晴らしく、下草も、中位の木々も、そして高い木々も緑豊かに育っています。何処でもそうですが、こういう場所は、どんどん減ってきています。そして残された場所は、国立公園に指定され採集禁止になってしまいます。
 (2)昆虫について
 海辺の林の中には、オナシベニモンアゲハやオオルリアゲハが翔んでいました。林の外では、光の中で燦めく大きなメガネトリバネアゲハの雄を、初めて見ることができました。海辺で見るマダラチョウも、これまたいいものです。  マングローブの貧弱な林では、ちょっとチョウの数は少ないのですが、たまにはこんな所もいいでしょう。タスキシジミやそれに似たルリウラナミシジミがちょこまかと翔んでいます。紫色したベニリアキンミスジが舞い、アダトガリシロチョウが通り過ぎてゆきます。  豊かな森林内においては、様々なチョウが翔んでいます。特に、テグリナトラフタテハやクリシッペハレギチョウ、カトプスメダマワモンが悠々と翔んでいる光景は、とても美しいです。その中でもクリシッペハレギチョウは、どきっとする美しい輝きがあります。リギナミナミヒョウモンも、これまた美しいブルーのチョウです。タスキシジミも少ないながら、翔び廻っていました。林縁の泥の道には、多種のルリマダラに仲間が来ていて、博物学者ウォレスの名を付けたワレスルリマダラは、ここで初めて掴まえました。そう言えば、オセアニア区に分布するルリマダラの仲間は、瑠璃色に輝くチョウが殆どいません。瑠璃色どころか、白っぽくなってゆきます。どうしてなのでしょうか。林縁から林の中へと小川が流れていて、そこにはいろいろなトンボが飛んでいました。紫色の翅を持った小形のチョウトンボ、翅の根元だけが彩られたチョウトンボやハグロトンボ、ハッチョウトンボなどなど。そしてウチワヤンマの仲間も飛んでいました。
 2 イリアンジャヤ東北部
第1回:1995年 8月12日、1995年 8月16日
 (1)自然について
 ジャヤ・プラの空港ということで降り立つと空港そのものは、ジャヤ・プラの隣の町センタニにありました。この町は、ニューギニア高地への玄関口になっているので、西欧の若人をよく見かけます。従って、ガイドは捜さなくても向こうからやってきます。この町から他の町へ行くときは、旅行許可書が必要となり、警察が発行するのですが、その書類手続きはガイドがやってくれました。町の裏には山があり、鬱蒼とした森林が茂っています。町から歩いていける距離なのですが、この辺りは、採集禁止(?)になっているみたいで2日間の採集時には、極力人気のない場所を選んで案内してくれました。非常によい状態の森林で、頂上まで径は続いています。昆虫も豊富と思われるのですが、隠れての採集なんて望まないから今回限りとしました。
 (2)昆虫について
 緑豊かなので昆虫たちも、非常に豊かですが、採集には許可が必要みたいです。  町からそれほど離れていないところでメガネトリバネアゲハが翔んでいました。雄の美しさは何とも言いようがない美しさですが、如何ともし難いです。アルビヌスアゲハ、アエゲウスアゲハ、アガネムノンタイマイ、デオイスムラサキ、アスピラトラフタテハ、アルミウスメダマワモン、スリアッリスルリモンジャノメ、各種ジャノメ、マダラ、セセリ、シジミがいました。思う存分歩き廻れれば素晴らしい昆虫採集になるのですが仕方ありません。トンボも豊富である。ウチワヤンマ、翅が青いミドリカワトンボの仲間、その他いろいろいまた。セミも丁度、人の背丈程度の所に止まっているのがいました。  ここで、ごく普通の昆虫採集を趣味にした人が、思う存分採集するにはどうしたらいいのでしょうか。残念です。
 3 イリアンジャヤ東北部
第1回:1995年 8月13日 〜 1995年 8月15日
 (1)自然について
 イリアンジャヤの最東南部に位置するメラウケは、鬱蒼とした森林の多いニューギニアとしては珍しく乾燥した地域です。海に近く、平らな土地が広がっています。町中から車で20分もするとワスル国立公園の道へと入りますが、当然ゲートがあり監視員がいます。イリアンジャヤそのもので採集するのは難しいと思っていたし、まして国立公園内で採集なんて、当然駄目だとばかり思っていたのですが、近くの展示室を見た後、ゲートを開けてくれました。メラウケ周辺は、採集そのものの禁止はないようです。しかし残念ながら、高く盛られた道路の外は、湿地帯みたいで、木々が疎らに立っている風景がずっと続いていました。森林と言えば、発達したマングローブ林がありましたが昆虫が余りいませんた。でも一カ所、海に面した小さな疎林に多いとは言えませんがチョウが舞う場所を見つけました。  もっと遠くまで車で行けばいいのかも知れませんがガイドを頼むときには、その土地の慣習に倣って無理しないことにしていますので、これもまた愉しや。
 (2)昆虫について
 乾燥した土地なので森林性の昆虫は見かけませんでした。アフィニスカバマダラとペリマレマルバネシロチョウが一番の多く見られました。フスクスアゲハ、そしてオナシベニモンアゲハ(?)が翔んでいましたが、オナシベニモンアゲハは、4日間で1,2匹見ただけです。ミシスカザリシロチョウがただ移動してしているというのが目に付きました。パウリナトガリシロチョウ、キチョウもいましたが、パウリナトガリシロチョウ(♀)は1匹採っただけです。数種類のルリマダラ、ユベンタヒメマダラ、そしてチビマダラが翔んでいました。オセアニア区のルリマダラは、どちらかというとチャイロマダラで、殆どの種がぱっとしない色彩をしています。ユベンタヒメマダラは、いろんなところで採っていますが、やはり紋様や色合いが違うため一杯持っているからといって採らないという訳にはいきません。ジャノメチョウは、メドゥサニセジャノメを含め草原性にジャノメです。スリアッリスルリモンジャノメは、他のところで採ったのとは幾分紋様が違い個体差(♀)も見受けられます。ビリダタテハモドキが道の傍らに、ベニリアキンミスジが疎林の中で翔んでいます。セセリは少なく、シジミチョウは、ムラサキシジミ、ニシキシジミの仲間が意外といました。  トンボは、それなりにいます。乾燥してはいますが、低湿地帯なので、沼沢が多いのです。砂浜の上を舞っていたチョウトンボは、ニューカレドニアで飛んでいたのと同じトンボでした。そしてここにも、コシボソトンボが飛んでいます。  夕方、町中を歩くと数少ない外灯の下に、エンマコオロギと痕跡程度の角を持った2cm位のカブトムシの仲間が落ちていました。
|