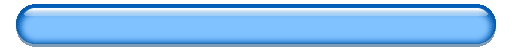
| 1月24日 懲役14年は長いか短いか(2) 昨日の新潟少女監禁事件についての話の続きです。昨日の日誌を読まないとわかりませんので、必ず読んでくださいね。 さて、本件の問題は、窃盗罪の扱いと量刑にあります。 窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですが、実際に窃盗罪のみで3年以上の懲役になることはあまりありません。 ましてや、前科前歴がなしで単なる下着の万引き1件程度であれば、通常は「起訴猶予」、つまり裁判にかけられることすらなく、検察官に怒られておしまい、という処分が普通です。仮に何らかの事情があって起訴されても、前科がなければ通常は執行猶予がつく可能性が高いでしょう。同種の前科があった場合でも、せいぜい重くても懲役1年がいいところでしょう。 それが、本件では監禁致傷罪と併合罪になった途端に「プラス4年」の結論が導き出されているのです。 併合罪は「二つの罪を犯しているのだから1+1=2以上に重く罰する」規定ではありません。昨日掲げた刑法47条の条文を見ていただければわかるように、2つ以上の罪について、同時に刑を執行するとき、結果として刑期が長くなりすぎないようにするための調整規定です(外国だと、複数の犯罪の法定刑を足していった結果「懲役200年」なんていう荒唐無稽な判決が出されることがありますが、日本の刑法はそのような事態を予め防いでいるのです)。 つまり、併合罪は1+1≦2とするための規定です。ところが、今回の判決は、結果として1+1≧2としてしまっています。これは併合罪の趣旨に正面から反します。 裁判所は「(窃盗は)監禁していた被害者に着せるための犯行で常習性も疑われ相当悪質」であることをプラス4年の一つの根拠にしているようです。しかし、窃盗罪は、財産的価値を保護するための刑罰規定であり、どんなに動機が悪質であろうとも、2464円相当の物に対する刑としては懲役4年は説明が付きません。また、「常習性が疑われる」としていますが、常習性は「疑われる」だけで立証されておらず、これを被告人の不利益に判断すること自体、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則に反します。法律上常習性が明らかな窃盗については「常習累犯窃盗」という別の犯罪が定められているのですが、その場合でも通常は懲役3年を超える刑はあまり科されません。なのに、常習性が立証されていない本件を「4年」と評価するのはいくら何でも無茶でしょう。 民主主義社会には「罪刑法定主義」という譲ることのできない原則があります。これは、ある行為がどんなに社会的に見て悪であっても、その行為が行われた当時にその行為を罰する規定がなければ罰することはできないし、その行為が行われた当時の罰則以上の罰を加えることもできない、ということです。 この原則がなければ、我々はどのような行為が許され、そのような行為にどのくらいの制裁が加えられるのか全く予測がつかず、結果として過度に行動を自粛せねばなりません。それでは人権保障もあったものではありません。 誤解のないように再度言っておきますが、私は佐藤被告が行ったとされた行為の評価として、懲役14年が「重い」と言っているのではありません。法定刑が許せば、無期懲役という選択もあり得るかも知れないくらいの行為だとは思います。 しかし、あくまで、法律が許せば、です。本件のような「刑を重くするため」の併合罪の適用は、刑法の「想定外」で、本来の趣旨から明らかに反します。 裁判所は「(犯行は)刑法の想定を超える最悪のもの」とコメントしたそうです。このコメント自体には私も異議はありません。しかし「刑法の想定を超える」から「刑法の想定を超える刑を科してよい」わけはありません。それでは罪刑法定主義は何のためにあるのか、ということになってしまいます。 例えば総会屋への利益供与(商法違反)や、脱税(税法違反)など、法律に定められた刑罰が軽すぎて、国民感情からすれば納得行かない軽い刑しか科すことができない事例は結構多くあります。そのような場合には「法律が定めたものだから」ということで、そのままの刑を科し、今回だけ、という裁判所の態度には重大な疑義があるといわざるを得ません。 |
一つ前へ 一つ後へ
日誌の目次に戻る
 トップページへもどる
トップページへもどる