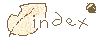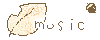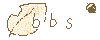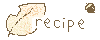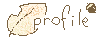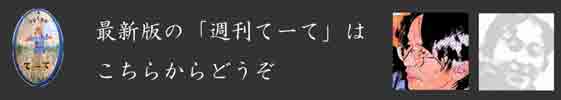
|
週刊てーて ひらく農園から
「冬の草を取る」
この地方の冬は暖かくて、ゆっくりではあるけれど作物は成長しています。野菜の品種は耐寒性の備わっているものが選ばれるために、低温でも伸張しやすいと言えます。一方、野菜を取り囲む草の数々は、この気候風土に合ったものしか発芽してこないので、耐寒性、低温伸張性ともに抜群ですから、春先までに野菜を追い越していくことになります。
毎日の収穫作業には、草取りも含まれます。先日の大雨でたくさんの水分を含んだ土は、それまでのカチンカチンの土から一変して、ふくよかな相を見せています。大根の抜き菜を収穫して手で土を寄せる作業は続いていて、そのときに草を取って畝間に落としていきます。夏には、草取りで取った草を畝間に落とすと、抜いた草に根がついているならば、生育適温ですから草は再生してしまいます。冬の場合は、この寒さと強い風による乾燥から、さすがの草も再生できません。しかし、草を取らなければ、今はまだ小さい草の芽が根をしっかりと張って、じわじわと野菜を脅かすことになります。
白菜のような大きく成長してきた野菜の周りの草は、もうほとんど取ることはありません。下手に草を取り過ぎてバランスを欠き、アブラムシが発生するという事態を避けるという意味合いがあります。たとえて言えば、外で元気に仲良く遊びまわっている子供たちは、時間の許す限り遊ばせておくのがよいというわけです。アブラムシの大量発生は、大抵は人間の過剰な世話や過剰な栄養、あるいは未熟物の土への混入に端を発しているようです。
これからまだ成長してもらわないと収穫にいたらなさそうな野菜のまわりは、慎重に草を取ります。低温で肥料分を根が吸いにくい時ですから、根のついた草を取ることで土が持ち上がり土に空気を入れ、草を取った部分を手で土を掻いて野菜に頬ずりするようにして、世話を焼くのです。いくら暖かい地方であると言っても、遠州の空っ風の体感温度はかなり低いものであるので、野菜にしてもその体力の消耗は相当なものでしょう。ですから、世話を焼くべきところは焼いて、放りっぱなしでは済まされない部分を見極めていかなければならないのは人間と同じようなものです。
とーと畑の中の開墾部分に作付けされた小松菜などの葉もの類の土は、雨のおかげでふかふかしてきて、この草取り作業が一層楽しくなってきました。夏の草取りがやたらとシビアな印象の中にあることに比して、冬の草取りには、何ともいえない熟成された気分が満ちています。時間に追われないわけではなくとも、なんとなくゆったりとしていて、土の熟成に立ち会っているようなそんな気分に満たされて心地よいのです。
2002年1月24日 寺田潤史
|
←イネ科の草 |  |
転がして草を取る |
 |
←草をつかむ |  |
間引き前の大根 |
 |
←草を引っ張る |  |
間引き土寄せ後の大根 |
 |
←空気が入る |  |
水菜と小松菜 |
|
←土を落とす |  |
上の通路に抜いた草 |
|
←ふかふか |  |
タフベルで保温 |
このページの最初に 戻る