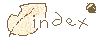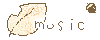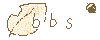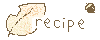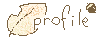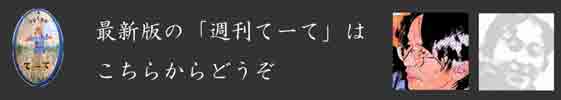
週刊てーて ひらく農園から
「無農薬無化学肥料で多品目野菜を育てることとは?その一」
ここのところ、立て続けにアドバイスを求められた。簡単に言えば、無農薬無化学肥料で野菜の営利栽培をしたいのだが、どのようにすればよいか?というアドバイスを求められた。以前からたまにそういったアドバイスを求められることがあったが、十日ばかりの間に数度となると、いったいどういう流れだろう?と思ってしまう。そこで自分自身に再確認してみた。
無農薬無化学肥料で多品目野菜を育てること、その言葉そのものを三つに分けて考えることもできる。無農薬、無化学肥料、多品目野菜という三つだ。と、ここまで書いて気がついた。こんなことはどう簡単に書いても、ちょっとやそっとのスペースでは書ききれるものではない。とりあえず、最低三回のシリーズにしなくちゃどうしようもない。
まず無農薬ということ。僕が一度も農薬というものを使ったことがないので正確ではないが、大雑把に分けて除草剤、殺虫剤、殺菌剤の三点が挙げられるだろう。「除草剤」は、草取りが面倒なので草を枯らしてしまえ、というわけだ。これを逆に考えてみれば、草を取る取らないはともかくとして、草取りの嫌いな人は無農薬栽培には適さないから、草取りを好きになろう、ということでもある。奈良の川口由一さんのように不耕起栽培をする場合も草はとるのだ(草を刈る)。次に「殺虫剤」。これは虫を殺すものだ。青虫や夜盗虫の大きなものからアブラムシなどの小さなものまでたくさんの種類の虫が野菜とともにある。特に葉もの類はアブラムシがつけばあまり売り物にならなくなってしまうので、つかないような栽培方法が求められる。殺虫剤の代用なんて考えていたら、無農薬栽培は違う方向に行ってしまうに違いない。「殺菌剤」は、病気をなくすためによい菌も悪い菌もすべて一時的に殺してしまおう、という皆殺しの方法だ。これは、日本の農業が産地形成を前提として推し進められてきたので、たとえば白菜なら白菜ばかりを毎年同じところで育てることによって生まれる連作障害というものをなくすために奨励されたものといえるだろう。どんな菌にも理由があってそこに存在しているので、一つの側から見てよい菌がすべて万能ということはありえない。相互のバランスがこの世を支配しているのだ。
つまり無農薬ということは、草や虫や病気を苦にしなくてよいような栽培方法を確立することにあるのだ。実はこのことは、シリーズの二回目三回目にも予定している無化学肥料、多品目野菜ということと密接に関係してくる。「そんなことをしたら絶対に虫が出てしまうし、病気にも弱くなってしまうよ」という言葉を僕たちの農の仲間である「こぼれ種の会」の勉強会でどれほど吐いてきただろうか?それほどに僕たちは失敗を繰り返してきて、いやというほど売れない野菜を育ててきたともいえるだろう。無化学肥料、多品目ということが、無農薬であることの重要な要素になっているのだ。無農薬、無化学肥料、多品目をまとめて欧米では「有機」あるいは「オーガニック」と呼んでいるが、日本の場合は違う。使ってよい農薬があっても、使ってよい化学物質があっても単一栽培であっても、申請してお金を払って審査が通れば「有機」という表示ができる国であるのだ。申請しなければ「有機」という言葉は使えない国なのだ。横道にそれてしまったが、後は次回に。やはり、簡潔には書けそうにない。
2004年2月19日 寺田潤史
(すべて無農薬無化学肥料栽培です)
| 野菜 | 品種 | 科 | 播種日 | |
|
New New New New New New |
菜の花 玉葱 葉ねぎ フリルレタス サニーレタス ブロッコリー カリフラワー 春菊 チンゲンサイ べかな しろな 大根ぬきな 水菜 ロケット 大根 小松菜 京壬生菜 みかん キャベツ 人参 自然卵 甘夏 |
レタサイ もみじ3号 わかさまパワー グリーンリーフ なんそうべに 磯緑 オレンジブーケ 大葉春菊 福賞味 はまみなとべかな 京の四季 冬みね 早生水菜 オデッセイ 耐病総太大根 安藤早生 早生壬生菜 青島 彩春 紅映2号 ブラウン 水俣のきばるの低農薬 |
アブラナ ユリ ユリ キク キク アブラナ アブラナ キク アブラナ アブラナ アブラナ アブラナ アブラナ アブラナ アブラナ アブラナ アブラナ アブラナ セリ |
2003/8/21 2002/9/28 2003/3/18 2003/9/18 2003/9/19 2003/8/2 2003/8/2 2003/9/18 2003/10/30 2003/10/2 2003/10/2 2003/11/11 2003/9/16 2003/10/2 2003/9/20 2003/10/2 2003/10/2 2003/8/1 |
ご意見ご感想は、下記よりどうぞお寄せください。
このページの最初に 戻る