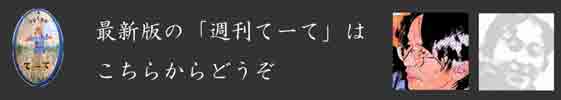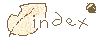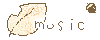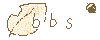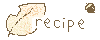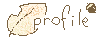「無農薬無化学肥料で多品目野菜を育てることとは?その五」
種を播いて芽の出たものを畑に植え付けるに耐える苗に育て上げることを、苗作りと呼んでいる。苗作りという言葉は一般的だが、苗を作るという感覚が僕にはない。苗を育てるというほうが近い。ここでは、一般的な苗作りという言葉を使わせていただく。昔から苗半作と呼ばれているくらいで、苗をうまく育てることができれば目的の作物は半分はできたも同然、という意味だろう。僕にとっては、苗八分作だ。それほどに苗作りを大事にしているし、時間をかけている。
春作と秋作とでは、苗作りの方法が若干違う。気温が違うのだから当たり前だが、今は春だから春作の苗作りを記してみる。大根、かぶ、法蓮草、ラディッシュ、しずむらさき、そしてジャガイモ、里芋、とろろ芋、生姜、人参、牛蒡、これら以外の野菜はすべて苗作りを行って畑に植え付けている。畑に植え付ける作業で腰を痛めることが多いがゆえの機械移植導入で、葉もの類も苗作りを常とした。苗作りする利点は他にもある。無農薬ということで草取りが大変で、畑に種を播いてすぐに生えてくる草に芽の出た葉ものが埋もれてしまうということが多かったが、苗の間に葉を大きくしていることから草に埋もれることがなくなり、葉ものに限っていえば、草取りをまったくしなくても葉もの自体が収穫を迎えることができる。また、冬から春先までは、アブラナ科の葉ものは地温十五度以下で花芽がつきやすくなるので、せめて幼苗期だけでもビニールトンネルの中で過ごすことで花芽を遅らせることができるのである。そして、雨でも夜でも、納屋で種播きを行えるという利点は、周年の野菜供給の安定性につながるという利点もある。
機械移植を前提にしている場合は、機械にあったトレーを利用して播種する。手植えでももちろん構わないが、トレーには種類がたくさんあるので長い目で見て使えるものを、そして種に合ったものを選ばなければならない。種に合ったものとは、播種後何日で畑に植え付けるかまで考慮しなければならないということだ。僕の使っているトレー(30cm×60cmの標準規格トレー)を記しておく。ちょっと専門的だが許していただく。葉もの、葉ねぎ、ニラ、玉葱はすべて288穴。キャベツ、白菜、ブロッコリー、カリフラワーは128穴。レタス、アスパラガス、とうもろこし、枝豆、インゲンは200穴。瓜類のダイレクトセル定植(鉢上げをしないで畑に直接植える方法)は72穴。瓜類(鉢上げ)は200穴。一月播種のナス科(トマト、シシトウ、ナス、ピーマン)は200穴。二月播種のナス科は288穴。ざっとこんな感じだろうか。
播種作業は、真空播種機が使える場合はとても早いが大きな種は手播きで十分。苗土は自作をお奨めする。動物糞の入っていない堆肥とピートモス、バーミキュライト、牡蠣ガラ粉末、水をよく撹拌して作る。ミキサーは必須だ。播種後、覆土するには肥料分がないほうがよいので、バーミキュライトがよい。寒い時期であれば、お湯を沸かして30度前後の水を使って十分に水遣りする。屋内のできるだけ暖かなところへ段積みして芽が出始めるのを待つが、レタス類の場合は2日で苗床に出して日を当てるほうがよい。こうして記してみると、常には体に染み付いていて気付かないが、実にこまごまとしたことを無意識に色分けていることがわかる。すべての作業に必然があるのだ。次回も苗作りの続きを述べたい。
2004年3月18日 寺田潤史