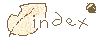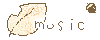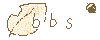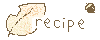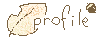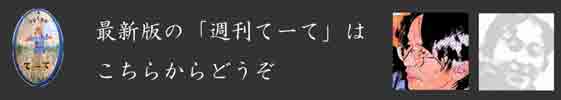
週刊てーて ひらく農園から
(すべて無農薬無化学肥料栽培です)
| 新着 | 野菜 | 品種 | 科 | 播種日 | |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
New New New New |
なす 玉葱 葉ねぎ じゃがいも ごぼう オクラ にら 南瓜 にんにく 胡瓜 青しそ インゲン モロヘイヤ ピーマン ミニトマト ししとう 自然卵 自家製味噌 |
千両2号、黒潮 七宝甘70 わかさまパワー 男爵、メークイン スターライト スーパーグリーンベルト 白栗 遠州早生 ときわ地這 自然発芽縮緬青しそ 黒種衣笠 自家採取 京みどり レッドメゴ ツバキグリーン ブラウン |
ナス ユリ ユリ ナス キク アオイ ユリ ウリ ユリ ウリ シソ マメ シナノキ ナス ナス ナス |
2004/1/12 2003/10/15 2004/2/2 2004/2/26 2003/10/8 2004/2/27 2000/1/25 2004/3/18 2004/3/1 2004/5/1 2004/4/26 2004/3/18 2004/1/9 2004/1/12 2004/2/2 |
ご意見ご感想は、下記よりどうぞお寄せください。
このページの最初に 戻る