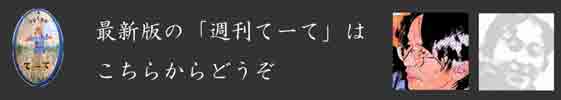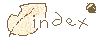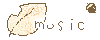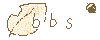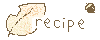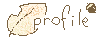「旬を食べる、旬を育てる その七」
先週、盛夏さながらの酷暑と書いたが、今週にいたってはもはや前代未聞のいらだつような暑さであるといいたくなるほどである。気温からすれば、32.5度とびっくりするようなものでもない。しかしながら、この過ごしにくさといったらない。いつもならば暑い暑いといっても、風という強い見方がいる。それが今回は無風である事が多い。微風でいいからそよ吹いて欲しい。今朝、鶏小屋に行ったら、鶏舎の中には一羽もいなかった。みんな、木陰であえぐようにして暑さから逃れていた。暑いのは僕だけではない。生まれて三ヵ月半の四女も過ごしにくいようで、団扇であおぐと気持ちよさそうな顔を見せる。何とかこの暑さをしのいでいかなければならない。
これだけ暑いと、旬から逃げ出したくなるのが本音だが、味噌汁と胡瓜やナスの浅漬けを玄米のおかずとして食べられるので、ばてることはない。生の胡瓜に塩をふったものにピーマンの刻んだものが混ざっていると食欲はさらに進む。このピーマンの脇役的な味は、暑さに強い野菜の独特なパフォーマンスの一つであるといってよい。
ピーマンは一月に種を播いて三月に畑に植え付け、五月末から収穫が始まった。十一月までの長期収穫野菜の一つだ。六月の台風で枝の折れたものや、枯れたものもある。それでも、どかなりもせずに少しずつ育っている。どかなりとは、収穫初期にどっとたくさん実をならせて、長期収穫に耐えられない生育をさせてしまう事だ。どかなりさせないためには、堆肥を通常よりも多めに入れておけばよい。たくさんの肥料分を消化できない状態を作っておいて、徐々にピーマンの木を作っていくのである。在来種のピーマンを少量の堆肥で育てると、どかなりしてしまう事が多い。品種の力も関係してくる。少しずつ育ってくれると、ピーマンの世話も収穫しながら少しずつできるので、多品目野菜を育てる僕たちにとってはありがたい。
今年のピーマンは、排水の悪い、土の出来上がりの良くない場所に植えつけた。大雨が降れば、水は畝間にたまったままのような場所だ。土も酸性が強く、芝草もはびこり、虫も多い。であるから、今年のピーマンは虫食いが多く、畑においてくるものがかなり出る。もう今は、草茫々の畝間である。そろそろ草を刈ってあげなければならないが、こんな暑さのときはかえって草があったほうが良い。鶏が木陰に休むように、ピーマンの根も草陰に守られるのだ。風が、コンクリートやアスファルトの上を通ってくるよりも、草や木の間を通ってくるほうが気持ちのよい事を誰でも知っている。が、どうしても人間というものは、利便性と見栄えを気にする生き物だ。家の周りの草取りは大変だから、家の周りをコンクリートで皆固めてしまう光景もよく目にする。固めなければ、たいていは除草剤をまく人が多い。さもなければ、草取りに精を出して、土が強い雨に流出されてしまう事も多い。その際たるものが土砂災害につながっている。土に木や草が生えているからこそ、人間は大地は守られてきたのだ。その事は、ピーマンとつながっている。
この狂った暑さの中で、僕たちの見ているものは、すべて土との接点にある。そして、その下で、微生物や水がどのように流れているのかを想像しているのである。とはいえ、日中は暑くて僕たちはピーマンを放って避難しているのであるが。
2004年7月8日 寺田潤史