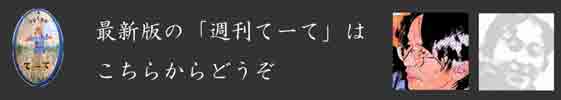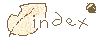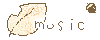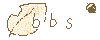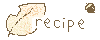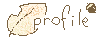「旬を食べる、旬を育てる その八」
今日のお昼には、35.5度を温度計が指していた。空梅雨の予想が当たり、予想外の台風がいくつも発生した梅雨も明けた。八月を思わせるほどの熱気に、畑の野菜はいうに及ばず、木々のてっぺんの葉もしなっと水分を失っている。そのくせ、秋風のような風が吹いてくるから不思議だ。秋が単に早いのか、予想に窮するが、秋物の種をまいてみたところで、この暑さを苗が耐え切れるとは思えない。来週まで、種播きを控えてみようと思う。
五角形のオクラが収穫の最盛期を迎えた。十一月はじめまで続く収穫期の中でも、湿度の高い今が一番のオクラの季節なのかもしれない。湿度が高く気温も高いと、オクラの実の大きくなる速度が速い。朝収穫して、次の日に横着をして夕方の収穫になってしまうともはや手遅れだ。実が大きくなりすぎてしまう。場合によっては、朝晩収穫しなければいけないときもある。真夏の収穫で体調を崩すこともあるので、オクラの作付け量を増やさないようにしている。ナスやピーマン、シシトウ、胡瓜などの収穫とが平行してなされるために、必ず毎日収穫しなければならないオクラの収穫時間を短くするためだ。オクラ農家ならいざしらず、多品目野菜を常とする場合には、気をつけなければならないポイントだ。
湿度の高いのが好みであるといっても、オクラの保管には湿度は気をつけなければならない。例えば、ピーマンやナスなどは、収穫後の貯蔵(長くても丸一日の貯蔵だが、これだけ気温が高い実物の野菜は呼吸熱が激しいので一日の貯蔵でも気を使う)は湿気があったほうが良いが、オクラの場合は違う。常温で少しでも涼しいところを選んで、湿気がこもらないようにしなければならない。うちの場合は、竹篭で収穫する事が多いから、その中へ置いたまま放置するのが良いが、風が通り過ぎても、熱くなった部屋の中でも良くない。予冷温度を十度にできるならよいが、玉葱やらジャガイモやらお米などの貯蔵が主の夏場では、設定温度を四度にしている。だから、できるだけオクラは冷蔵庫へ入れない。胡瓜でもそうだが、やむをえない場合は、オクラを発泡スチロールの箱に入れて、冷風の直接当たらないところに置き、できるだけ短時間の貯蔵にして、品温が下がり過ぎないようにするべきだろう。
オクラは、モロヘイヤと同様に粘り気に特徴のある野菜だ。五角形の星型でなければオクラでない、とする方もいるくらいで、夏に涼しさを演出できる野菜の一つである。しかしである。食べる側と収穫する側とではやはり、気持ちが違ってくる。特に真夏は、収穫に疲弊感があるために、僕個人としてはオクラの料理をする気になれない。出されれば当然食べるが、はねたオクラが山ほど出るので、食卓に乗るオクラの量も半端ではない。家庭に配達する一週間分を一食で食べてしまうなんてことはざらだ。これが農家の事情である。今日のお昼に温度計が35.5度を指していたときに恭さんは、オクラを収穫していたのだが、僕は思わず怒ってしまった。何度だと思っているんだ!腎臓をやられたらどうするんだ?と。真夏は、収穫よりも体である。何度も僕は失敗しているから、いくら体調が良いといっても、あとから疲れが出ることは必死なのである。多品目の中のオクラとはそういうものなのだ。
2004年7月15日 寺田潤史