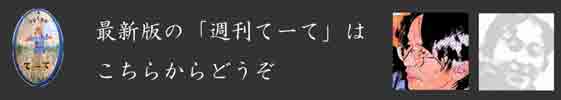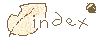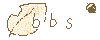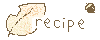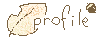「旬を食べる、旬を育てる その十四」
このところ、畑での作業はずっと素手を通している。冬もそうだが、夏の虫の多いこの時期も素手である。九年程前に、今は亡き奈良の大倭紫陽花村の矢追日聖さんに「出来うる限り素のままで」と言われてから、出来る限りは素手を通してはいたが、夏の虫の多い時期だけは手袋をして収穫をしていた。
先日、収穫の折、蚊が多くて、今夏の収穫でははじめて手袋をはめて収穫した。ナスやシシトウを収穫していたのだが、実に居心地が悪い。手触りで収穫物の質を判断しながらの収穫であったのが、手袋をはめると途端に感触がわからなくなって違和感を覚えたのだ。収穫した実ものは、実の柔らかさで畑に戻すかどうかを判断している。シシトウなどは特にその実の硬さで、実の大きくなってからの時間の長さがわかり、時間の長いものは辛味を帯びる可能性が高くなると判断しているのである。もっとも、毎年八月下旬になると辛味を帯びたシシトウを選別できなくなる事が多いが。
草取りもほとんどが素手でやる事が多い。十五年も露地野菜とつきあっていると、掌も免疫ができるのか、蚊に食われる意外は大分虫やかぶれに強くなってきた。オクラの収穫などは手が痒くなる事が多いのだが、手袋をはめるとかえって手袋に葉っぱがくっついてやりにくい。ここ数年は素手でも手が痒くなる事はなくなった。草取りでは、手袋をしていたほうが根を張っている草を抜くには力が入りやすいこともある。しかし、長続きのする草取りは素手が一番だ。土の感触が手先に伝わり、草の感触が掌に伝わる。手袋をして草取りを続けていると、何本も束になった根の張った草をまとめて引き抜いてしまう事が多く、結局握力が弱って長続きをしないのだと思う。素手の場合は、根の張った草を一株ずつ分けて抜く事が多く、急激な力を多く必要としない。時間が許すまで草取りを楽しむ事が出来るのだ。
十五年前、音楽を考え直す事をきっかけに農の世界に入ったのだが、今でも時々ふと頭をよぎる事がある。何のために畑をやっているのだろう?と。よく考えると、ああ、土に触りたいからだ、草に触りたいからだ、と思い至る。土に触る、草に触るということが僕の生活には欠如していたと納得したのが十五年前であった。だからあの時、つるはしと鍬だけで今はなき「てーて畑」を開墾していったのだ。その気持ちは、やはり今も変わらない。草一本も生えていなかった不毛のこの「とーと畑」が、今では草に覆われているのである。これこそ僕が待ち望んでいたことであった。草は土を生物の宝庫へと変えてくれる。しかも、その土に合った草が生えてくるのである。これが地球の生業なのだ。土に触り、草に触るということは、そこにけったいな薬品をまきたくないという気持ちを強固にする。まして、そこから人間の、子供たちの食べ物が生まれてくるというのならなおさらだ。無農薬無化学肥料で農業を営むということが出発点ではなく、土に触る、草に触るから、無農薬無化学肥料が前提だったのは自然の流れだったと思う。機械を多用するようになっても、いやそうなったからこそ、素手での作業を大切にしたい。素手で旬を丸ごと抱きしめるのだ。
2004年8月26日 寺田潤史