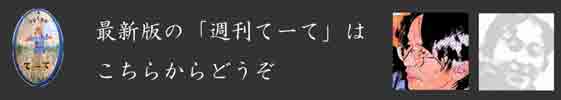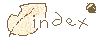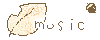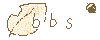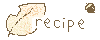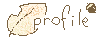「旬を食べる、旬を育てる その十五」
草を刈る、草を取る日々である。日照りの夏から大地を救ったのは台風であるが、大地を救うことすなわち草を救うことであるから、草々は俄然勢いを盛り返して、穂を出し、子孫繁栄に全精力を傾けている。
畑に収穫に行く途中で、里芋畑の草がまた繁茂しているのを見つけると、収穫のバケツを置いたまま、里芋畑に分け入っていく。真夏の炎天下ではどうしても草を取る気にならなくて、草に覆われた里芋の畝の左右から刈払い機で草を刈っただけであった。刈っただけの草はすぐに伸びる。やはり人間の手が入らなければならない。七月のはじめ頃に里芋の畝の株元に米ぬかを振ってあったところは、土がふかふかして大きくなった草でも意外に抜きとりやすいのだ。台風が去ったばかりなので、草を抜くと根に土が付いてくる。抜いた草を振って、土を里芋の株元に落とす。これが土寄せの役割を担う。抜いた草は畝間に放り込んでいく。仕上げに畝間の草の山を踏んで、米ぬかを振っておけば追肥となるし、再度の草の再生を抑えられる。しかし、畝のすべての草を取るには時間がかかるので、少しずつやっていくほかはない。少しずつがどれだけ長続きするかが収穫量に関わってくる。炎天下の真夏が終わったので、やることが山のようにあるので里芋ばかりにかまっていられない。とすれば、あとは愛情の問題だ。愛情をどれだけ表現できるかだ。
「ちーち畑」は唯一の砂地の畑だ。砂地ゆえに真夏の作物には渇きがひどく適さない場合が多い。この夏も草を刈っただけで、放っておいた。草は背丈以上に伸び、ツル物の草もはびこってきた。さすがにトラクターにつけたフレールモアでも、馬力を最大限に生かさないと粉砕できなかった。平らになった「ちーち畑」に残ったのは、自然発芽のシソだ。青シソは毎年種を播かないで、この自然発芽のものを収穫している。もうこの時期は収穫も終わりだ。もうじきシソも穂を出す。穂を完熟させるまでは粉砕しないでそのままおいて、冬になって耕し来年の自然発芽に備える。青シソも虫の害が大きい品目なので、自然発芽したものが一番虫害が少なくて済むが、それでも虫食いが多い。そのために、要望のあった場合にだけ出荷することが多く、あとは自家用となる。自家用には虫食いで充分なので、この夏も盛んに食卓に風味を添えてくれた。
どんなに炎天下の夏も、畑には毎日行くのは当たり前だが、毎日通る畑の通路の草も伸びる。何度となくフレールモアで平らにするのだが、しばらく雨が続くと意外に草の伸びるのは早く、収穫に向かう長靴に草が当たって邪魔になるし、服に滴がついて濡れる。気分よく収穫するには、やはり刈り取っておいたほうがよいし、この些細なことがことのほか重要のようにも思われる。苗床の横の通路などは、草が伸びて苗床の寒冷紗にかかると虫が中に入りやすくなる。苗を育てる上では、一番重要になる要素が周囲の草取りなのだ。無農薬で苗を育てるのはこの時期が一番難しいが、周囲の草を刈って虫を減らし、寒冷紗に覆われた苗床の苗を早く畑に植え付けることで、苗床の中の虫の循環をなくすことが出来るのである。この時期の重要な仕事である草を刈るということに時間を割く理由は、ここにある。
2004年9月2日 寺田潤史