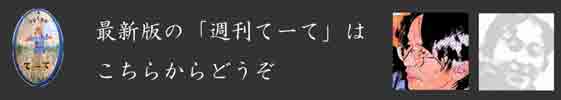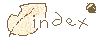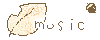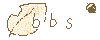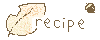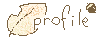「土作り その一」
夏中、草を刈ってきた畑を、今耕している。今年はフレールモアを導入したので、いささか趣が違う。草を土すれすれで粉砕してそのままに置くという行為は、地表の微生物の力を生かすことになっているのかな?という感じがする。人間が草を粉砕しておくことで、微生物は草という有機物を分解しやすくなるのではないか?という思いがある。しかも、放置するということは微生物に任す、という意味がある。
去年までの方法はといえば、草をいきなりトラクターで土の中に耕してすき込むという方法であった。刈払い機で草を刈るという面倒で体力を消耗する事を、大面積に対して行うという事は物理的に無理だといっていい。だから、伸びた草をいきなりトラクターですき込むのだが、これには草の勢いが強すぎてトラクターも悲鳴を上げる。しかも、一度耕しておいたものが大雨に降られると、当分その畑には入ることが出来なくなるのだ。また、伸びた草をいきなりすき込むのでそれなりに深耕しなければならず、嫌気性の微生物の多い領域にいきなり草をプレゼントすることになり、バランスは失われ、草の腐熟にも時間がかかってしまうと考えられる。草を刈っただけの畑であれば、大雨が降っても平気だ。土を動かしていないのだから、ぬかるみもできないし、微生物も死滅しない。畑の作物というものは、好気性の微生物の働きが重要になるから、土の表面付近にいる好気性の微生物が豊富であるほうが良い。もちろん嫌気性微生物といわれる空気のない状態に近いほうが好みの微生物の力も必要であることは言うまでもないが、表土あたりに分布するのは圧倒的に好気性微生物だ。この表土付近に草の粉砕したものを置いておけば、彼らは喜ぶに決まっている。草を刈ることとトラクターで耕すことの二度手間になるようにも思われるかもしれないが、結果的に有機物の分解は早まっているし、トラクターのロータリーの爪の消耗も少なくなる。真夏の植え付けをしない期間、草を伸び放題にしておくか、何度か粉砕しておくか、あるいは何度か耕すかで仕事の質も微生物の質も変わってくるというわけである。
うちの畑の特徴は、何といっても草の力を信じる事にある。草を生えるに任せるということではなく、生えるに任せた草の性質を土に生かすということだ。生えるに任せるとは、草が生きられる環境を自分で選択して生えてくるということで、言い換えればその環境に適した草だけが生えてくるということも出来る。最初に開墾したとき、「とーと畑」には草が一本もなかったのだから、今は草がいくらでも生えてくるくらい豊かな畑になった。生えてきた草を土に還元しては堆肥をまいて作物を植え、草を生やしてはまた還元してという具合に。その土を手で触ってきた。土が育っていく過程の中で僕たちも育てられている。草は敵でも味方でもない。草は土そのものである。草を刈りもするし、手で取りもする。しかし、そのまま草はそこにある。そのままの命が土に還るだけのことだ。微生物もそこにいるだけだ。そうしているだけで土つくりになる。土作りするのに、余分なものはいらない。雨と風とお日様と土、それだけあればいつか草は自然に生えてくる。人間が用意するものはできればよい堆肥だけだ。トラクターでも鍬でもエネルギーが加わるならばなおよい。もうふたつ、時間と根気だ。
2004年9月16日 寺田潤史