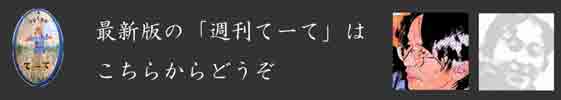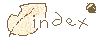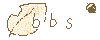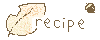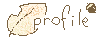「土作り その二」
土を作る、という言葉は日常では使わない。野菜を作るとも言わない。野菜は育てるものだからだ。では、土を育てる、というべきか?僕の正確な印象としては、土とともに育っていく、といったところか。ここでは、土作りという言葉の定義として、土とともに育っていく、とさせていただくことにする。
何度も週刊てーてに書いていることだが、「とーと畑」は土が入れ替えられて、草の一本もなかった不毛の畑であった。時が流れ流れて、この不毛の「とーと畑」がひらく農園の主だった畑となった。ここを良くしていくほかは、僕たちの百姓として食べていくすべがないのだ。開墾から初めて十年で熟畑となった今はなき「てーて畑」と「つーつ畑」は、荒れ果てていたとはいえ昔は畑であったところだ。そのようなところと「とーと畑」とは根本的に違っていた。この畑を良くしていくには、初心に戻ってやり直さないととてもできっこない、という気持ちであった。そう、僕たちは結果として、「とーと畑」の土とともに育ってきた。今、バランスのとれていない僕たちの体は、「とーと畑」全体のバランスがまだとれていないことを象徴するかのようだ。しかし、確実に「とーと畑」はよくなりつつある。
土作りというと、よく耕された土がふかふかで、周囲に草の一本もないような畑を思い浮かべるものらしい。でもよく考えてみると、そのような畑はたいてい土のアルカリ度が上がり、法蓮草はよくできるが、ねぎ類の根に病気が出やすい畑になっていることが多い。これは一概には言えないが、言えるのは病気が多発しているということで、バランスは失われていく方向をたどっている。であるから、農薬や殺菌剤がなければその畑で野菜が育たない、ということにもなる。しかも、除草剤などを使って草を皆殺しにしている常習犯であれば、土作りどころか土殺しの罪を犯していることにも気づかないほど麻痺しているだろう。そのほかに、よく土作りされた畑をはだしで歩くと病気が治る、というような魔法を夢見ている人もいるが、それは少し簡単に過ぎる発想である。昔から土に触りなさい、という教えがあり、それはそれで間違いではない。それは、その自分の立つ大地に種をまくなり苗を植えるなりして、精魂込めて作物を育てる過程として、土に触り続けるということである。つまり、作物を育てるという過程において、自分も土とともに育っていく、ということだ。
精魂込めるという行為は、人を清らかにする。殺意がなければなおさらだ。僕も虫を殺す。苗床のトンネルに侵入した蛾だけは、見つけて両手で叩き殺す。苗がなくては、何もはじまらないからだ。草や虫を一網打尽するということはないのでよしとしている。のべ十匹の蛾を殺すことと一万匹以上の虫を皆殺しにするのとでは、大きな違いがある。戦争に行って現地人をたくさん殺しながら自陣の兵士を千人失うということとなぜか似ている。爆弾や機関銃は、農薬や殺菌剤と同じで関係のないものまで皆殺しにしてしまうのだから、製造することにすでに不備があるといえる。話がそれたが、精魂込めて土に向かうことを常とすることは、美しいことなのだ、と力を込めて言いたい。農薬や爆弾と違って経済の糧が薄いが。
2004年9月23日 寺田潤史