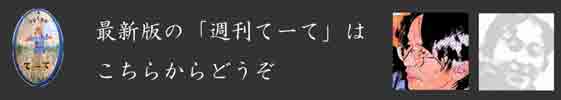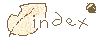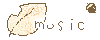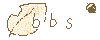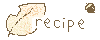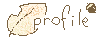「土作り その三」
人間が大地を耕すようになってどのくらいの時間が流れているのかをイメージすることはうまくできないが、働くことが美徳になったのは、やはり精魂込めて作物に接するようになってからではないかと想像できる。土を動かす、あるいは収穫したものを食べられるように調整し、貯蔵のための工夫などの過程で道具というものが発展していったのではないかとも想像できる。数十年前までの道具の発展はゆっくりした速度であったはずだが、動力が普及していっきに発展は加速度を増し、最大の労力であった土を動かすという仕事がトラクターなどの大型機械の農民への普及で労力を大幅に軽減できた。と同時に、戦争が終わって化学の行き場所の一つに農薬という分野が注目を浴びた。化学を生業とする人たちには魅力的な市場であったし、農民にとっては虫を皆殺しに出来る上に草取りからも開放されるとあって、見事に経済界と意見が一致した時代であったと思う。重労働を強いられ出来上がる過程までに臭いを放つ堆肥つくりからの開放は、化学肥料のおかげだったのだろうが、化学肥料を多用し始めると、土はバランスを崩して虫の大発生を誘い、農薬の出番は日常茶飯となった。これらのことによって、土と農民のあいだに距離ができた。それまでの「土は自分自身である」という発想からかけ離れてしまったが、農薬や化学肥料で生産性をあげたのだからそれでよかったのだと、今でも力説するのは農協や官庁ご用達の背広を着た人ばかりだ。
農民は、土に近いほど幸せを感じるものだ。土が自分自身に近いほど幸せを感じる。だから、死んだら土に還るという発想が自然なのだ。今日、玉葱の種を播いたトレーから芽が出始めたので、地床の苗床にトレーを並べて土にトレーを埋める作業をしながら、土に素手で触ることの幸せを感じていた。昨夜、強烈な台風の影響を受けた畑だが、一夜明けて、触ることの出来る土があること、そのこと自体も幸せなことだと感じた。一昨日、農機具屋さんが立ち寄ってくれたが、「とーと畑」の土を見て「だいぶいい土になってきたね」と言ってくれた。人から見ても良くなっていると思われるほどに、土は変化してきているんだ。草をすき込み、堆肥をすき込み、収穫残渣をすき込み、大量の虫の死骸をすき込み、空気を入れて少しずつよくなってきた畑。その畑の土に触って、目的の作物に添うことの出来る喜びは何事にも代えがたい。
農機具の中で、移植機というものがある。農機具としては新しい部類の道具だが、製品としては、もう一つの完成形である。玉葱移植機を導入して数年になるが、移植機もさることながら、移植機を使うまでの苗つくりの過程が何とも職人的なのだ。今日のトレーを大地に埋め込む作業もその一過程で、ここまで丹精込めて苗つくりに時間をかけたなら、もう苗半作いや苗八分作と言ってよいほどだ。最先端の農業機械を作る現場では、機械移植に耐えうる苗に仕上げる研究にも総力を挙げている。道具は道具として、苗は苗として丹精を込める。これが現代の技術であろう。僕たちは、そこを農薬がないことを当たり前として、化学肥料のないことも当たり前として、農の技術を確立していこうと思う。道具を使い、土を自分自身として丹精を込める。このことは今も昔も変わらないことであって欲しいと願う。
2004年9月30日 寺田潤史