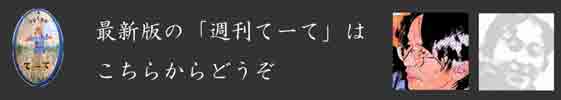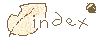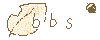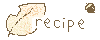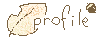「土作り その六」
雨のない数日間は、一瞬にして怒涛の台風に取って代わった。台風の雨の降る一日前にして、ようやくトラクターでかろうじて畑を畝立てすることが出来た。そのままその夜は、真っ暗闇の中、恭さんと黒ビニールマルチを張った。この天候で、何かを植えつけることが出来るとしたら、ビニールの力を借りるしか方法がなくなったのだ。これは深刻な事態だ。
この異常にバランスを崩したように見える狂った気候は、やはりよく言われるところの地球温暖化に原因があるのだろうか?海流の流れにすべてを託すような発言も多く聞かれる。新聞によれば、アメリカで大量に人間の作り出した二酸化炭素をパイプラインで何千キロと離れたカナダまで運び、地中に注入して封印してしまうというプロジェクトが進んでいるそうだ。日本もお金を出している。二酸化炭素が地中で、気体と液体の中間の形状でとどまり、漏れ出してこないというものだ。この記事を読むと、人間は大量の二酸化炭素をこれからも出し続けるぞ、という宣言のように思えてしまう。地中に二酸化炭素を封印すれば、温暖化はやわらぎ、この狂った気候もなくなるというのだろうか?たとえそうなったとしても、地中に封印し続けた二酸化炭素がどんな作用を後世にもたらすか得体の知れないはずなのだが。アメリカの古典的なウォルトディズニーの映画では、どんな誘惑よりも正直に生きることが大事だと繰り返し訴えているが、巨額のプロジェクトで行われる二酸化炭素の封印が、はたして正直に生きるということなのであろうか?
台風は、思いのほか強烈に、しかも予想外のコースをたどった。夕方までは大丈夫であった稲の架けてある稲架が、次の朝には倒れていた。支柱の折れたものもある。台風の直撃を受けたのでもないここですら被害があるのだから、直撃を受けたところの農家の被害は想像を絶するであろう。畑や田んぼの見回りにいって、命を落とされた人も多いようだ。残された家族などの断腸の思いは、何者にも代えられないものであろう。被害は、常に、生き残ったものが背負っていくのである。
年々、深刻さを増すこの気候の変化の中、やはり、僕たちに出来ることは「土とともにある」ということだけだ。稲架が倒されれば、稲束を干しなおすだけのことである。激雨があれば、乾くのを待つほかはない。被害はやはり、僕たちの掌の上にある。畑が乾いた時に、せっせと堆肥をまいて、種を播く。大地の上のほんの数センチからせいぜい二十センチのところに僕たちは生きているのである。僕たちの命とはそういうものなのだ。そしてその土のことは、草に聞けばよい。草取りもするが、草を目の敵にしてはいけない。草はすべてを教えてくれるものだ。大量の雨もいつかは乾く。激しい風もいつかはやむ。正直に生きるということは、そこから収穫できたものをいただいて生きるということだ。わずかな収穫ならばそれはそれで仕方のないことだ。たくさんの収穫があれば、皆でわけることが出来る。それが正直に生きるということだと思う。土つくりというものはそのためにあるといっても良いと思う。
2004年10月21日 寺田潤史