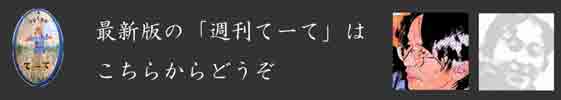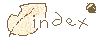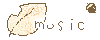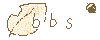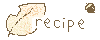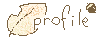「地球の懐に抱かれて」
台風、地震と立て続けに被害が大きく報じられると、人間というものの小ささを思い知らされます。逃げ惑うだけが人間のなすことの唯一である、という事実は、地球というものに住まわせていただいている、という感覚が日常いかに欠落しているか、ということでもあると思います。地球は人間が支配している、と思っている人がほとんどであるともいえます。
今回の地震で、家屋が壊され、余震の続く中、家の中よりは安心であるということで、外であるいは車中で夜を明かす方が多いということを聞くにつれ、人間の作ったものへの信頼はこういうときには薄いのだなということがわかります。東海地震が長年叫ばれているこの地域に住む僕たちなんかでも、小さな地震が来るとまず先に考えるのは、子供たちを家の中からいかに外に出して安全を確保するかということです。うちにはまだ七ヶ月の四女がいますので、毎日の昼ねの時にも、出来うる限りはタンスが万が一倒れてきてもいいようなところへ寝かすようにしています。大きな地震がくればそれまでかもしれませんが。親はどうとでもなるかもしれないけれど子供たちだけは守ってあげたいというのがどこの親でも思うことでしょう。そのことを考えると、他所の災害は人事とはとても思えないのです。
古代より人間は、食料の確保できる住みよいところを探して、集落を形成してきました。争いに負ければ、新しく住む場所を探して移動してきたのでしょう。そしてあらゆる場所に人間の住む場所があります。しかし、地球というものは、常に地殻変動を繰り返し、火山活動、プレートの移動など、その性質を変えていません。厳密に言えば変わっているのかもしれませんが、少なくとも人間の側にあわせて地球のほうで変わってくれるということなどありえません。それに対して、科学というものを備えた人間は、地球の住めるところにはどこにでも住み着いています。地球がくしゃみをすれば、必ずや人間は犠牲になるといっても過言ではない状況です。
こんな時に、被災した人々がビニールハウスで共同生活する模様がテレビで放映されました。軽量なパイプとビニールで出来たビニールハウスが安全だという発想と、現場に生きる人間の多様性が生かされた共同避難生活です。これは強力です。生きる力がみなぎっています。台風の時には、吹き飛ばされて困っている農家の多いビニールハウスですが、地震の時には、強力な施設となっているのです。畑の野菜を持ち寄って炊き出しを行い、トイレを重機で穴を掘って作り、大がまで薪を焚いて湯を沸かしシャワー室に送るなど、現場に生きるものの知恵が生かされていました。日常、地球の懐に抱かれているもののしたたかさを感じないではいられません。自分というものがとても小さい存在であること、天然自然の前に無力であるということを思い知らされる一方で、おそれることなく生きていけばよい、という気持ちにさせられました。僕たちはビニールハウスを使わないできましたが、一棟くらいは建てておいてもいいかな、と感じ始めています。自給自足に近いところに僕たちは立っているのですから。
2004年10月28日 寺田潤史