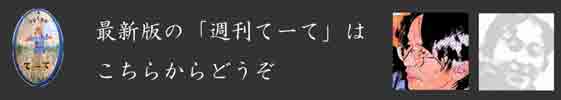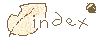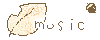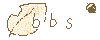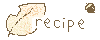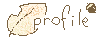「破天候?な二〇〇四年をかえりみて その二」
玉葱の植え付けをし終えたところで、更に劇的に台風もどきの嵐が通り抜けた。被害少なからず、といったところだが何とか修復し、レタスやブロッコリーを植え付けて、湯治休暇に出かける事が出来た。東名高速道路、伊勢湾岸道、東名阪、伊勢自動車道と南下して、国道四十二号線で紀伊半島をぐるりと半周した。目的の奈良県十津川村上湯温泉までの国道沿いには、今年の集中豪雨による痕跡があちらこちらに見られた。多くは、木がごそっと引き抜かれたままに川の氾濫とともに打ち上げられた形だ。粗大ごみが田んぼに打ち上げられたままのものもよく見かけた。
畑の作物、特に自家菜園らしき畑の野菜には、やはり種を播きなおしたであろうことが予想できる成長具合の白菜や大根ばかりが目立った。水につかった、あるいは濁流に呑まれた畑がほとんどであろう。これは日本全国似たり寄ったりなのかもしれない。このことは、本当に多くのことを物語っている。小さな被害や中規模の被害というものが無数にある。それらは、ほとんど表に出てこない被害である。報道機関のありかたもそうであるが、日本の戦後の拡大路線偏重により、大規模な被害でなければ何の補償されないのである。逆を言えば、大規模農家はいろいろの援助があり優遇されていくが、小規模農家は切り捨てる方向にあるということだ。そういうシステムを作り上げてきたのだ。政治家の頭が悪いのか、官僚がもう頭を使いたくないのかどこに原因があるのかよくわからないが、緻密な計算をいとわない義務教育、高等教育の成果は、大雑把な数字の大きいものだけを単純に優遇するように出来ている。そのかわりに、頭の使いどころは隠れた利潤を生むところに注がれているようだ。
僕たちは、この十一月にはじめてお店の出荷を見合わせた。自然食品店である袋井市の野草広場というお店が出来た時から、週に三日の出荷を続けてきた。お店に出荷する野菜がないのである。正確には、野菜が全然ないのではなく、お店の出来る前から宅配で野菜を買っていただいているお客さんの分で精一杯で、お店に野菜を出してしまえば僕たちの生活は成り立たなくなってしまうのだ。いや、実際には、今年の野菜の出来では、機械のローンを払ったところで赤字となっている。多品目野菜であるがゆえにかろうじて野菜が皆無という事態にまでは至らなかったが、常にお店の事を念頭に置いて作付けしてきたのが、出荷がなくなるという事にまでなったこの今年の天候の影響は絶大である。
にもかかわらず、こうして今湯治に来ている。それはなぜか。農民であるので、体の養生がまず先であるからだ。一年中温暖な気候に恵まれていると、一年中多品目の野菜を絶えず作付け絶えず収穫している、ということは何度も書いてきた。週に五日の出荷と配達も一年中だ。先日のように気管支を悪くして寝込んでも、一日寝ているということはほとんど出来ない。しかし、このスタイルは今後も何十年と続くであろう。生きている限りは続く。だからこその湯治だ。自分たちの体と心がリフレッシュされなければ、お世話になっている方々に野菜を届ける事が出来ない。来年の破天候にも対処できるからだの元を作るのだ。
2004年12月10日 寺田潤史