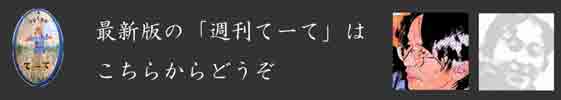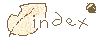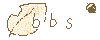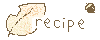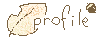「破天候?な二〇〇四年をかえりみて その三」
今年も毎年恒例の湯治休暇に行ってきた。からだの疲れがピークに来てもいたが、心のほうもだいぶ疲れていたような気がする。湯治場という空間から丸一日をかけて車で移動し平常の生活空間に戻ってみてあらためて感じるのは、やはり頭の中が空っぽになってリフレッシュされている空白感の心地よさと頼りなさである。
頭の中の空白感の心地よさとは、常日頃の休み無い労働とライフワークあるいは日常の連続から遮断された心地よさ、と言ったらよいだろうか?湯治場でも、非日常的ではあるが生活するということに変わりなく、子供たちのいるにぎやかさは日曜日の連続のようなものだ。畑という空間が目の前に存在しないという一種の重しのない状態は、それだけで軽やかなものである。それは、畑という具体性の実現を強いられることがないということでもある。湯治場において畑のことを考えることはまったくなく、畑作業ということも含めて生き方がこれでよいかどうかを自問していることが多い。日常生活の中では、具体性を帯びることに追いかけられて生活しているので、目の前のことを如何にこなしていくかを考えることに重点が置かれている。生活に追われることの無い環境でゆっくり思いを巡らすということは、頭の回路を別の信号の流れで動かしているようなものだ。湯治場で空白感を感じることはなく、家に戻ってはじめて空白感の心地よさを感じるのである。
空白感の頼りなさとは、湯治中の一週間という期間において仕事をまったくしていないんじゃないか、という人間社会の強迫観念に追いかけられるような精神状態を併せ持つということだ。日常の連続というものが具体性の塊であるから、その具体性に一つのよりどころを見い出す性癖を持つのが人間の一つの形だ。。その具体性を放棄するのである。社会からの疎外感も合わせてほんの少しだが感じる。それをあえて社会とは別のところに逃避するように湯治場に身を置く。逆に言えばよほどの強い気持ちがなければ湯治なんてできない。頼りなさは、強い気持ちによって押しやられているに過ぎないのだ。
リフレッシュされたことを分析してみても、あまり意味がないかな?リフレッシュされた状態は、毎年同じようなものだ。破天候であってもなくても。この目で見た、三重県から和歌山県東部、奈良県南部の破天候の被害は、例年とは歴然と違う光景だ。川の氾濫を起こした集中豪雨の影響である。根っこごと田んぼの上に放置された数メートルの木を何箇所で見ただろうか?川が蛇行した部分の外側に流木群がたまり、竹やぶはなぎ倒され、橋が流されたところもあった。コンクリートの土台がすっかりつぶされた公園や道路も少なくない。自分の畑の被害とテレビで見た地震や台風の被害が印象的な今年であったが、車窓から見る被害のあちらこちら、川に下りてこの目で見る被害は強烈なものだ。山が変化していく過程を目の当たりにすると、こうやって災害というものが地球の歴史を作ってきた一つの側面であることも教えられる。こうして日常に戻って、また畑で野菜を収穫してみると、やはり僕たちは出来ることをやっていくしかないのだと、いつもと同じことを強く思うのである。
2004年12月16日 寺田潤史