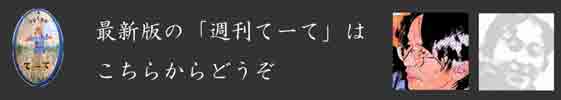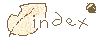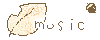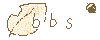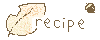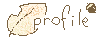「破天候?な二〇〇四年をかえりみて その四」
僕たち家族にとって今年の一番の重要な出来事は、何と言っても瑠李の誕生だ。四人目の女の子だから特段たいした感慨がないのではないかと予想していたが、物心のついてきた三人の姉たちにとって可愛がる対象ができたことが相当にうれしい出来事の様子で、そのことがまるで親に伝染したかのように瑠李といる時間が長くなった。しかし、恭さんの産後の大変さは、更に予想を超えたものであった。
一年中で一番の農繁期は四月である。夏野菜の植え付けや田んぼの準備に加えて、野菜の出荷量が一番多い時なのである。瑠李が三月下旬に生まれたので、母親である恭さんの養生を四月いっぱい費やし、食事や洗濯などの家事と、子供たちの保育所や学校への送り出し、野菜の収穫と出荷、畑作業と、身も心も「躁」の状態で何とか乗り切った。五月になって復帰した恭さんがいきなり大車輪の働きをしたわけではなかったが、五月の下旬には体調を落とし、六月には肺炎を併発した。八月にも体調を崩した。秋になってようやく体調を戻してきたが、このことは無理はさせられない、という強い気持ちを僕に起こさせている。記録的な猛暑によって、予想以上の疲労が僕たちに蓄積していたに違いない。それまで、よくもまあこんなに動けるものだと思っていた僕の体が八月下旬から不調となり、咳が止まらなくなった。そのことと秋の集中豪雨や台風の多発で、畑作業が遅々として進まない状況となった。しかしながら、そんな時であるからこそ、瑠李の存在は僕たちを和ませてくれる大きな要因であった。
三女の穂乃香と瑠李の間が丸四年ほど開いていることと、三人の姉たちが少し手がかからなくなってきたことが、赤ちゃんという存在のいいところを多く目に焼き付けることにつながっている。畑にもおんぶしていく回数が増えている。上の三人は、乳母車をいやがったので、長女の妃袈里が生まれたときに買った乳母車がきれいなままである。乳母車に乗せようとするだけでよく泣いたものだ。ところが、今回は毎日のように利用している。やはり、三人の姉たちが乳母車を押してくれる機会があるので、瑠李も余計に親しみやすいのだろう。風のない日は、畑まで乳母車を押していって、収穫作業の間を過ごす。法蓮草などを収穫して草だけが残った畝に瑠李をおろしてあげると、草をかんでいることもある。寒い日は、薪ストーブで暖まった納屋の中に乳母車を置いて、仕分け作業の間を過ごす。畑と子供の間隔が限りなく近いということは、農に従事するものにとって嬉しいことだ。
今年は、上の三人の姉たちが鶏にえさをやるというシーンも多くあった。ある日、棒を持って鶏を追い掛け回すということをはじめた二女の朱里が、餌をやるという行為によって、鶏をかわいがる風情に趣を変えた。両の掌に餌を盛って、鶏に直接餌を突かせるということを、大人はあまりしない。一人がそうすると、長女も三女も真似をする。親がやらせたことなど大して意味がないが、自分から進んで意思を表示するとき、親は手助けをしてあげるものだと子供たちに教えられた。そこに、仕事の忙しさは介入しないのが僕たちのやり方だ。破れた天候ではあっても、子供たちの成長は止まらないのである。
2004年12月23日 寺田潤史