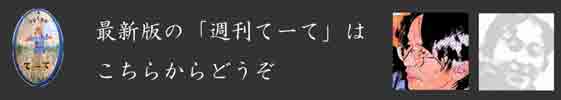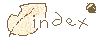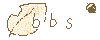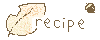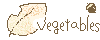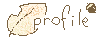「二〇〇五年に向けて その二」
年明け早々に忙しい日々だ。二年前に平飼いの種鶏場から廃鶏を譲り受けてやってきた四才の鶏が卵を産まなくなったので、四十羽新しく廃鶏を譲り受けた。三十八羽の古い鶏と新しい鶏をごちゃ混ぜにしたら、新しいほうの鶏がいじめられて餌を食べられない事態が起きた。そこで、ネットで二分して、古いのと新しいのを完全に分けた。古い鶏は、卵を産まないのに餌はたくさん食べるから、間引いて十羽を加工に出す決意をした。よその農場では当たり前にできることかもしれないが、うちでは議論をとことん尽くして納得のいくところに落としたつもりだ。加工に出す前夜、かごに十羽を入れたのだが、一羽入れるたびに背中がぞっとした。いや、正確には一羽を両の掌で捕まえるたびに「お前は選ばれてしまったんだよ」という非情な思いが背中を通り過ぎたと言うべきだろう。そして、今夜はその鶏の肉を食べている。
平飼いの鶏の肉は、硬い。味が濃い。食べてみると、これはダシがよくとれるとすぐにわかる。どうしてこんなに違うのだろう?ネットでブロイラーという単語を検索してみた。驚いた。通常市販されている鶏の肉は、卵から孵ってたった八週間で加工に出されるというのだ。身動きの自由の効かないような密集状態で、餌は抗生物質などの薬品入りだ。最後の一週間だけ休薬という薬品のない餌が与えられるというのだから、薬品を食べているようなものに近い。それに比べてうちの鶏は、余裕の土の上の空間を飛び回っているのだから、肉が硬くなるのも理解できる。大豆と米ぬかと牡蠣のからの粉末のほかに魚のあらや緑餌を食べ、土を穿り返してミミズなどの小動物を好物としている。そんな鶏を食すということは肉を浪費するのとは違う感覚だ。ほんの少しの肉を食べるという意味が、実感として理解できたような気がする。
鶏のことばかりやっているわけにはいかない。畑の野菜の準備のとっかかりとして、早くも夏野菜の種をおおよそ播き終えた。ナス、ピーマン、シシトウ、トマト類、胡瓜、西瓜などである。これだけ世界的に尋常な気象状態ではないところから見て、今年も何が起こるかわからない。種を播いて播いて播きぬくほかはない。年末に播いた葉ものの苗が大きくなってきたので、次の葉ものも播かなければならない。夏野菜の畝も今月中には仕立てておきたい。今、植わっている玉葱などの草取りや世話もしなければならない。
排水にも万全を期さなければならない。毎年、冬のあいだに木酢液を散布するのだが、これが微生物の働きで排水を良くしてくれる。冬には低温で、微生物の働きが鈍る。木酢液は温度に関係なく作用するようだから、有機農業にとっては強い味方だ。しかし、暑くなると忙しいことも手伝って、ほとんど木酢液をまかなくなる。年末からまた木酢液を散布しだしたが、先日も雨の水分が残るところへ散布した。そして雨がまた降り、微生物は広範に散らばる。これがよい。水分のあるところでないと木酢液の微生物活性の力が発揮できないからだ。これを鬼の形相で継続していかなくちゃ。有機農業というものは、天然自然の力を最大限に生かそうという農業だから、目に見えない土の中を想像し、土の中の微生物を応援して力を借りていかなけりゃ、とっても追いつかない農業だ。
2005年1月13日 寺田潤史