オンラインショップ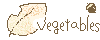
「週刊てーて」ひらく農園から、バックナンバー
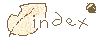
ヒメパセリさんの詩集
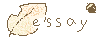
サイトスさんの野菜を使った「レシピ集」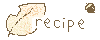
「週刊てーて」ひらく農園から、語りと映像
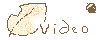
草子の演奏は草子ドットネットへお入りください。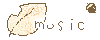
このサイトについて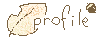
リンク集
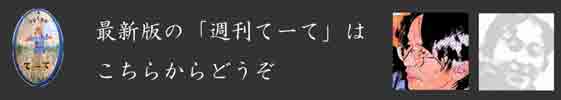
★ 「週刊てーて」+αをブログでどうぞ。 ☆ ひらく農園の野菜を入手できるお店
週刊てーて ひらく農園から
「60歳 自分らしく生きる、とは? その3」
自他共に良い環境を用意すること、それこそが自分らしく生きることの大前提となった。その環境の中に、当然ながら食生活は大きな位置を占める。有機農業という職業柄、味には敏感だ。とはいえ、外食することもめったに無いから、慣行農法での野菜を吟味するということもほとんどない。だから、自分の畑で収穫されたものと、年に2,3度の有機農業仲間の料理で味わう野菜の味しかわからない、というのが本当のところだ。
東京時代の自然食品店での買い物の経験から、有機農業の世界に入って、それらしい自然食品の類もよく食した。しかし、子供5人を無添加自然食品だけで育てることには金銭的に無理があった。ましてや、5番目の長男がサッカーを志していることで、普通の豚肉を積極的に摂るようになった。自然食品店で買い物をすること自体がほとんど今はない。ただ、野菜の味とかけ離れたものには無理があるので、化学調味料で出汁はとらない、などの基本は必須だ。
肝心の野菜だが、30年有機農業をやって思うのは、一つの農法に固執することの弊害を感じることだ。有機農業、すなわち化学肥料や農薬を使わない農業は、農法ではない。心情である。野菜に対する心情、土に対する心情、それらと安定した収穫物のバランス感覚が有機農業と言えるだろう。ところが、何々農法というものを信じて突き進んでしまうと、他者を否定するようになるし、さらに人を巻き込もうとするのである。これはまさに宗教団体と同じことになる。宗教心はとても大事だと思うけれど、宗教団体はまた別の世界なのだ。
野菜の栽培では、先進的な機械化にも積極的に取り組んでみた。それなりの成果は上がるものだが、ある程度の面積と雇い人が必要になってくる。今は、トラクターや草刈り機、種まき器など、最低限の機械だけを使うようになった。畑を耕して種を直接播く方法、種をトレイに播いて苗を育て畑に植え付ける方法、畑に生分解マルチフィルムを張って草を抑える方法、1作終えてそのまま耕さないで苗を植え付ける不耕起というやり方、などなどそれらを臨機応変に組み合わせている。一つに固執してそれに縛られると自由でなくなるし、天候不順が当たり前の気候の中で、最善の策を探すのもまた楽しいのだ。
先週、南瓜の第一弾を収穫した。南瓜のヘタがコルク状になったところで収穫するのだが、あまり畑に置きすぎてもお尻から腐敗することがある。収穫して軒下で追熟、というスタイルだ。南瓜はお日様の力の割合の大きな野菜だ。しかし、ここへきて大雨ばかり。昨日、久しぶりに晴れてくれて、今朝まで雨は降らないでくれた。第2弾をすかさずチェックする。コルク状になったものがたくさんあったので、時間はなかったけれど、すぐに収穫、貯蔵した。多品目の野菜を育てているので、どの野菜もいつも最高の状態というわけにはいかない。できる範囲での最善策に、瞬間的に力を注ぐというやり方を、この30年で身につけてきた。
連れ合いが青シソの収穫をするのにも、大雨の直後では葉の状態が悪くなる。雨が上がって1〜2時間置くことで、シソの樹自体が葉を再生してくれるのだ。そういうことを僕たちは見出しては、収穫に役立ててきた。環境を創出、に近いかな?
2020年7月3日
ご意見、ご感想、お問い合わせは、下記よりどうぞお寄せください。
(すべて農薬、化学肥料を使用していません。ここに記載のないものもあります。)