オンラインショップ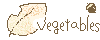
「週刊てーて」ひらく農園から、バックナンバー
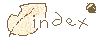
ヒメパセリさんの詩集
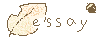
サイトスさんの野菜を使った「レシピ集」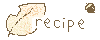
「週刊てーて」ひらく農園から、語りと映像
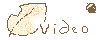
草子の演奏は草子ドットネットへお入りください。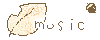
このサイトについて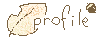
リンク集
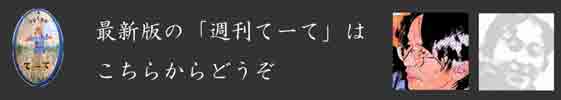
★ 「週刊てーて」+αをブログでどうぞ。 ☆ ひらく農園の野菜を入手できるお店
週刊てーて ひらく農園から
「スポーツ?とは? その3」
僕たちが農というスタイルで生活すること、これは現代の日本においては若干アウトロー的な側面があるかもしれない。歴史的に見れば、あるいは世界的に見れば、極めて普遍的な生き方の部類であるのだけれど…。このスタイルの良いところは、カラダもよく使うが、頭を使って言いたいことを言う、という点にもある。僕で言えば、このような筆という表現だ。そして、そのスタイルの究極の良い部分は、平和主義者である、ということ。このスタイルは、自分から戦争を起こす、ということを生み出し得ない、と考えるのだ。
戦争を起こす人、というのは、大抵は上に立つ人である。プーチンはその経歴で現場に立ってきたのは、スパイという役目だったようだ。そして、彼が上に立って47歳で大統領になり、今は69歳。老人の部類になってきたところで、今回のウクライナ進撃である。米井嘉一さんという同志社大学教授が毎日新聞デジタルで語るところによれば、強迫性神経症の疑いがあるらしい。確かに、多くの専門家がおかしい、と感じている話は耳にする。プーチンの近くに、進言する人の存在がない、ということだろうか?
毎日新聞の記事で、米井嘉一さんは「プーチン氏が怒っているのは、2014年のソチ・オリンピック開催中にウクライナで起きたクーデター『ユーロ・マイダン事件』だ。親ロシア派のヤヌコビッチ大統領が失脚、ロシアへ逃亡した。気分よくオリンピックを開催していたところへ、赤っ恥をかかされたのだ」という話を聞いたことがあるという。さらに「その後に起きたことは、ウクライナ領のクリミア半島のロシアへの編入、ウクライナ東部紛争でした」と続く。8年前と同じような形で、今回の北京オリンピックで、女子フィギュアスケート選手のドーピング疑惑や、国を上げての薬物疑惑のためにロシアが正式な形でオリンピックに出ることができなかったこと、がプーチンの感情に火をつけてしまったのかもしれない、という想像もできると思う。
『ユーロ・マイダン事件』のことは詳しく知らないが、経過を書いたものを読むと、ウクライナの人たちの長い年月に苦しめられた歴史のせいなのか、そう簡単にはロシアに屈しない民族性を感じる。ウクライナは肥沃な土地で、その土地で収穫した食料を、ロシアが持ち去ったという過去の人為的飢饉という歴史もあるようだ。強奪を百年経っても繰り返すのか?
米井嘉一さんは言う。「強迫観念から生まれた不安にかきたてられた行動が『強迫行為』です。自分で『やりすぎ』『無意味』とわかっていてもやめられない行動を指します。プーチン氏の現在を見ていると、そんな状態が思い浮かびます」と。プーチンはかつて、柔道着を着た姿など、スポーツに浅からぬものを感じていたはずだから、オリンピックというものの見方も違うものがあったのかもしれない。直接の原因ではないと思うが、元々持っている強国観念の被害者意識のようなものに、スポーツが屈折して関わっているのかもしれない。いつでも相談できる相手、なにか言ってくれる相手、という存在があればよいのだが、年齢を重ねると、孤立しやすくなるのは人の性なのだろうか?他人事ではないね。
2022年3月4日