オンラインショップ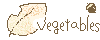
「週刊てーて」ひらく農園から、バックナンバー
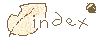
ヒメパセリさんの詩集
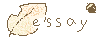
サイトスさんの野菜を使った「レシピ集」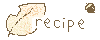
「週刊てーて」ひらく農園から、語りと映像
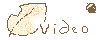
草子の演奏は草子ドットネットへお入りください。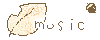
このサイトについて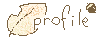
リンク集
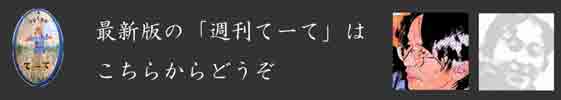
★ 「週刊てーて」+αをブログでどうぞ。 ☆ ひらく農園の野菜を入手できるお店
週刊てーて ひらく農園から
「畑仕事はいい 2022」
争いごとや事件、不祥事、メディアをにぎわすことに事欠かない時代である。だけど、そんなことにばかり気を取られている時間は、もったいないどころか大きな迷惑であるくらいだ。この久しぶりに雨のない日々に加えて、過ごしやすい気候や秋空、畑に出てみると、工場火災の残骸は気持ちいいものではないけれど、気持ちの良い畑の空間は格別である。
今年も、玉ねぎの苗は順調だ。今まで、どんなに台風が来たところで、うちの玉ねぎの苗だけは被害にあったことがない。伝統的な方法と、近代的な方法の合作風の苗の育て方が功を奏していることは間違いないと思う。伝統的な方法というものは、畑に直接玉ねぎの種を播いて育てる方法だが、どうしても大雨や大風には弱い傾向にある。ビニールハウスで育苗している人も多いようだが、ビニールはやはり大風に弱いし、苗が軟弱に育つ傾向もあるだろう。
うちの玉ねぎの苗の育て方は、昔もこの週刊てーてに何度か書いたと思う。おさらいしてみると、まず玉ねぎのコート種子を用意する。天然素材を用いているらしいが、玉ねぎの種を丸い形状に固めたものだ。次に288穴の種播きトレイに、自家製培土を詰める。そして、コート種子を真空播種機で吸い上げてトレイに種を播く。気温にもよるが、4日ほどで発芽してくるので、それを畑の苗床に並べていくのである。
畑の苗床は、水やりできるところならどこでもよい。畝を立てて、水はけは良くしておく。そして、その畝にトレイを並べていくわけだが、その際には畑の土とトレイが密着するようにしなければいけない。なぜかというと、トレイの下から畑の土に根を張るように仕向けるというわけだ。さらに、乾かないように、並べたトレイの上部の縁まで土を盛っていく。こうすることで、トレイが乾きにくくなるし、虫の侵入の確率あるいは侵入後の虫の隠れ場所を減らすことができるのだ。最後に支柱とネットでトンネル状に覆って出来上がりだ。
とはいえ、虫は侵入する。苗床に並べて2週間もすると、その間に降った大雨などで、まだか弱い玉ねぎの苗の根本が頼りなくなる。同時に、ヨトウムシの侵入により食害が始まる。苗が、数か所でなくなっているのを見つけたら、ネットを外して念入りに見て回る。土が動いている場所があるので、そこを鉄の細い棒などでつついてヨトウムシを見つけ潰すのである。そして、苗土に使った培土と同じものを、トレイの上から振り撒いて土入れをする。
年に一度の玉ねぎの育苗だが、このやり方は気に入っている。昔、ヤンマーの研究所を訪ねて教えてもらったやり方を、自分なりに工夫してたどり着いたやり方である。それも、玉ねぎの機械植えという近代的な手法がもとにあったのだが、そのヤンマーも今はそのやり方を伝えているかどうかわからない。僕も今は機械植えをやめてしまって、手植え専門である。この育苗方法だけが残ったようなものか。
できれば一日畑作業をしているのがいいのだけれど、出荷という作業に大きな時間を割くのは致し方ないこと。人を雇わず夫婦二人だけで回る範囲の仕事、それが僕たちの歩幅なのかもしれない。この時期、用事がない限り外には出られない。
2022年10月21日