オンラインショップ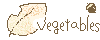
「週刊てーて」ひらく農園から、バックナンバー
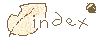
ヒメパセリさんの詩集

サイトスさんの野菜を使った「レシピ集」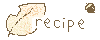
「週刊てーて」ひらく農園から、語りと映像

草子の演奏は草子ドットネットへお入りください。
このサイトについて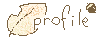
リンク集
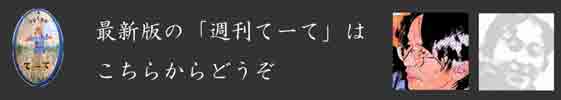
★ 「週刊てーて」+αをブログでどうぞ。 ☆ ひらく農園の野菜を入手できるお店
週刊てーて ひらく農園から
「どこから来たかを永遠に その3」
今日は親父の命日である。もう23年になるのか、と思うけれど、あの時1歳の誕生日も迎えていなかった三女が、この春には24歳になるのだからね。その時に僕は40歳だったわけだし、親父も67歳になったばかりの頃だから、どちらの年齢も若いと感じる。仏壇の前に行けば、親父を思い出さないことはないし、この頃は毎回「おふくろをもう少し生きさせてやってくれよ」「親父のところへ行くのはもう少しあとでもいいでしょう?」と伝えている。
40歳の頃も二周りあとの今も、日々の生活は似たようなものだ。しかし、考えることは違うように思う。表題の「どこから来たか?」というようなことを考える性質は同じなのだけれど、今は考えの前提に「後回しにはできないかも?」といういつまで生きられるかなんて分からない感覚がついて回る。40歳の頃には、漠然とまだ20年は生きる感覚があった。親父が67歳まで生きたという事実が、根拠のない死を恐れない確信のような中に生きていたのだろう。実際のところは、子供たちのあれこれでてんてこ舞いだったのだろうけれど…。
話は飛ぶ。正月に子供たち5人全員が揃って、元旦の夜だったか、連れ合いは台所でお餅の切り分けをやっていた。夜中にどういうわけか子供たちがなかなか寝ないで、皆で話していた時の話だ。長女が「こんな汚い家に彼氏とか旦那を連れてくるわけにはいかない」というようなことを言いだした。明治末期に建てられて、少しは改装もしたけれど、造りはほぼ昔のままのすきま風溢れるた佇まいである。昔の家であるので、ホコリはあっという間に溜まってくるので、密閉性のある現代の住居とは対極にあると言っていいかもしれない。
そこで三女が反論をしたのである。「私達が育った場所だから誇りを持っている」というようなことを言ったのだ。そのあとは、長男が昔から口癖のように言っている「この家はとっとと壊して新しい家を建てて、樹木も全て無くして芝生にしてしまいたい」というような夢の話から、わけのわからない話に発展してしまったのだが、少なくとも、僕には子供たちの記憶にこの古い家が厳然と残っていくだろうと思えて嬉しかった。
物事を考える時、強い思いというものが形成されるには、人それぞれに強い体験の蓄積が必要だと思う。その根拠を柔らかく取り出す時、人は何らかの変化をしていく。柔らかな取り出し口が見つからない時、人は頑なになっていくのかもしれない。三女は、五人の中のちょうど真ん中で、生まれついて強いものを持っていたが、中卒で就職を決め、実際に働きだしてどこかで柔らかい取り出し口を人との関わりの中で見つけたような気がする。そこには、人を観察することを通して、自分らしさを維持する術のようなものがあるのではないか?
植物の種も、永遠にどこから来たかを記憶しているのだろう。人間の遺伝子もそうなのだろう。確かに、今を生きることは必須であり最善である。どのように人間が人間になっていったのか、その間もずっと食べ続けて生きてきたということ、そのようなことに思いを馳せていくと、人は柔らかな取り出し口を見つけられるかもしれない。ロシアにもイスラエルにも、その取り出し口は今のところ見つけられないことが哀しいね。
2024年2月23日