オンラインショップ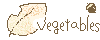
「週刊てーて」ひらく農園から、バックナンバー
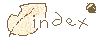
ヒメパセリさんの詩集
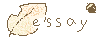
サイトスさんの野菜を使った「レシピ集」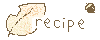
「週刊てーて」ひらく農園から、語りと映像
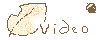
草子の演奏は草子ドットネットへお入りください。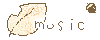
このサイトについて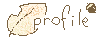
リンク集
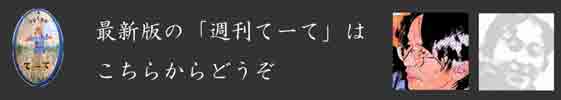
★ 「週刊てーて」+αをブログでどうぞ。 ☆ ひらく農園の野菜を入手できるお店
週刊てーて ひらく農園から
「どこから来たかを永遠に その5」
今年の天候が、年初から奇妙であることは、多くの人が感じていることだろう。そう、僕たちは、天候あるいは風土、日本で言えば四季、そういったものの土台の上に生きている。僕たちの源は、気候の中にある、と言っても言い過ぎではないくらいではないか?その更に先の、つまりもっと過去の進化の過程では、海の中だった、と想像することも悪くはない。海の中で言葉を発して喋った、などとは想像できないけれど。
少なくとも、地上に上がり、二本の足で歩くようになった頃のあたり、そのような時代に言葉が生まれたのかどうなのか?それはわからないが、音楽というものを考えた時、歌を口ずさむというよりは、発声を繋げて鼻歌のようなメロディを発するということがあったかもしれない。どう考えても、音楽というものは、人と人、あるいは自分と自分、のために発生してきたのだろうと推測する。
絵というものを想像すると、もっと実用的な方法、ということも容易に推測できるだろう。言語の前に、伝達手段のための絵、あるいは記号のようなもの。だけど、表現としての絵というものを想像すると、神への畏怖とか憧憬、感謝のようなものを、絵で表したということも想像できる。そう考えると、音楽もまた、遠くの距離での伝達手段や、神との関わりの表現、ということも想像しやすい。
こういったことは、インターネットで検索すれば、きっと多くの情報が得られるであろうけれど、僕が知りたいのは、例えば農耕民が米や野菜を育てる中で、の音楽や絵というものを大事にする個別の想いである。狩猟民族であったとしても、どんな人も、食料を調達し食べて子孫を残してきたことに違いはない。「人間はパンのみで生きるのではない」という言葉を若い頃に知ってから、僕は逆に「パンは絶対的に必要なもの」と考え、その生産現場に自分が入ることでパン以外のものを模索しようと考えた。
現代の日本社会では、原始的な生活などは蚊帳の外、と考える人が多いと思う。ここで言う原始的とは、例えば土を動かす、種を土に播く、雨を受ける、風に打たれる、収穫をする(採取する)、木を切る、火を燃やして暖を取る、というような種類の生活に密着した様々のことである。実際に、僕や連れ合いは、そのようなことが好きなのだ。その中で考えることもまた好きなのである。
もちろん現代的な生活もまた僕たちは普通にしている。この文を書くにもパソコンを使うし帳簿だってデータベースだ。テレビはサッカーやニュースくらいしか見ないけれど、今どきの自動車で配達し快適にも感じる。音楽の録音もパソコンを駆使する。しかし、ギターはこの手で演奏する。エレキギターを使っても、この指で弦を弾く。僕が二九歳で帰農してやろうとしたことは、こういうことである。そのような生活の中で音楽を考え、人のことを考えることがしたかったのだ。そして、それは今も道の途上だ。更に言えば、貨幣経済の中には生きているが、ギリギリでその境界線を漂っているようなものである。
2024年3月8日