オンラインショップ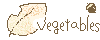
「週刊てーて」ひらく農園から、バックナンバー
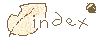
ヒメパセリさんの詩集
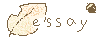
サイトスさんの野菜を使った「レシピ集」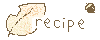
「週刊てーて」ひらく農園から、語りと映像
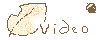
草子の演奏は草子ドットネットへお入りください。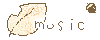
このサイトについて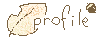
リンク集
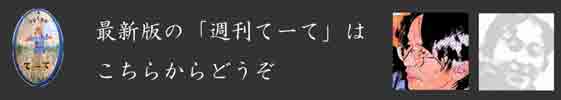
★ 「週刊てーて」+αをブログでどうぞ。 ☆ ひらく農園の野菜を入手できるお店
週刊てーて ひらく農園から
「季節は人が創り出したもの?」
桜の花はまだ残っているけれど、葉桜になって人にため息と安堵をもたらしている。遅い遅いと言っていた桜も、学校の入学式を彩ってくれたであろうし、配達の車窓から桜の花を堪能できた。気がついてみると、季節は季節に追いついたのか、季節通りの中にいる感覚だ。
2月のことだったと思うけれど、二十五度という気温が示す期間があった。植物たちは、そこで春を感じ取ったのだろう。野菜は例年になく端境期を早く迎えることになった。ところがその後に寒波のような寒い日々が何度もやってきて、野菜の端境期は今の今まで続いてきた、というわけだ。雨も多くて、季節通りでないことに僕たちは戸惑ったし、桜を始めとした植物や樹木、虫たちも戸惑っているように見えた。人間がその日に着る洋服の選定に迷うくらいであるから、植物たちも自身のカラダの調節に忙しかったのではないだろうか?
太古から、人は地球上の動植物に合わせて生活をしてきた、と想像する。あくまでも地球の水や風雨、地形、気温などというものに合わせながら、生あるものは進化してきたのだろう。日本のような四季がはっきりしているような島国で、いつから四季というものを感じるようになったのだろうか?僕たちは、学校で四季というものを教わった。はじめに知識ありなのだ。中学生の頃、泉谷しげるの「春夏秋冬」という曲を聴いた。「季節のない街に生まれ…」という出だしは、かえって四季を強く意識したのかな?と今は思う。高校を卒業して、都会に出てからは、四季を意識しないで生活していたような気もする。
帰農して、季節の中にだけ生きるようになった。ビニールハウスを使わないで野菜を育てるということは、季節に沿って仕事をするということになる。もっと言えば、季節を強く意識しても、季節の境目はない、という日々が連続しているのだ。年中行事としての、年末年始やお盆、お祭りなどは、人間の世界に生きているという意味で否応なく意識させられるが、休みなどない世界だ。植物は、大雑把だけどとても正確な季節感だけが体内時計として宿っているのだろう。日の長さや気温の変化などを正確に読む取る技術である。植物に技術はないのかもしれないけれど、長い時間をかけて遺伝子として受け継がれ体得してきたものだろう。
僕たち人間にもそういうものは受け継がれているはずだ。しかし、季節を学校で教えられるようになって、そのような遺伝子レベルで受け継がれてきたことは、いつの間にか捨て去られたのか、格納されてしまったのか? 生あるものは進化してきた、と書いたけれど、むしろ退化しているのではないか?退化しているから、地球上の動植物に合わせて生きてきた僕たちが、地球そのものを痛めつけていることに気付かないか認めないかの存在に成り下がったのだ。
季節というものが創造上のものならば、僕たちにはまだアイディアが残されているのではないか?物わかりの良い人になって経済経済と呪文を唱える人になりなさい、という教育を本当に皆が望んでいるのだろうか?AIだのロボットが人間の代わりをしてくれるだの、それが退化を促進させる最適な方法であることを、本当は知っているのではないかい?知っているのならば、その手や足を動かして、労働するべきではないのかな?
2024年4月12日