オンラインショップ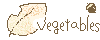
「週刊てーて」ひらく農園から、バックナンバー
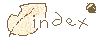
ヒメパセリさんの詩集

サイトスさんの野菜を使った「レシピ集」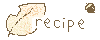
「週刊てーて」ひらく農園から、語りと映像

草子の演奏は草子ドットネットへお入りください。
このサイトについて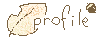
リンク集
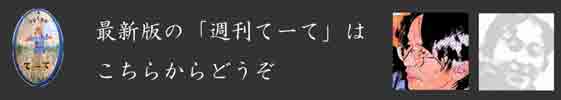
★ 「週刊てーて」+αをブログでどうぞ。 ☆ ひらく農園の野菜を入手できるお店
週刊てーて ひらく農園から
「ひと一人の人生 その2」
二十三年前に親父が他界した時と、今回のおふくろの葬儀後と比べてみると、こちらの年齢が違うせいなのか、感じ方が違う。親父が六十七歳で逝き、おふくろは八十八歳だった。僕の年齢が四十歳と六十三歳では、死への感じ方が違うのは当然か?僕自身があとどれくらい生きられるかが、この頃は切実な年齢である。誰しもが自分自身のことに対して真剣であると同時に、誰しもが親の存在を気に掛けるのだ。親が生きていようが他界していようが同じである。
おふくろが逝ってもう2週間が経つわけだけれど、何ともふわっとした感覚でしか捉えられない。畑でカラダを使って作業をしている時には、そのふわっとした感覚から離れている。二十三年前は、親父がいなくなってもおふくろが元気だったし、おふくろが精神的に大丈夫かどうかを注視していたような記憶がある。そうだ、週刊てーてに何か書いているはずだ、と思い立って自分のサイトのバックナンバーを探してみた。
ありゃりゃ、そうか思い出した。親父が他界した2月には、僕はまだ手書きで週刊てーてを書いていたのだ。いや、あの頃はもう和文タイプライターだったか。バックナンバーの2001年の12月の記事を見てみる。大変な年だった、とある。長女と次女をその年の4月から同時に保育園に通わせた、とあるし、親父の使っていたMacのコンピューターがやってきて、7月くらいにはWindowsのノートパソコンを入れたのだと思い出した。バックナンバーの一番古いものがその年の6月からになっている。その時に、三女はまだ一歳である。
五歳以下の子供が三人いて、新しくパソコン環境を仕事にも導入したのだから、考えている余裕もなかったのかもしれない。さらに、相続で、手動開墾した畑も使えなくなり、新しく畑を切り開く作業にも着手したのだった。そうか、あれからずっと親父はあちら側から僕たちを見ていたのだな、とその長い年月を想う。同時に、おふくろは、その二十三年の大半を前を向いて生活してきたのだな、と。
誰でもそうだけど、自分自身に映ったものからだけで世の中を判断して生きている。おふくろが今年1月に退院してきて、元の生活に戻った時、完全におふくろの瞳はおふくろ自身だけを見るようになった。今日はこれができた、と伝え、それを褒めてほしいのだった。子供時代に戻ったようなものだ。人のことを気に掛ける、そのことが無くなっていったということは、逆にそれまでの長い年月で人のことを気に掛けてきた、ということだろう。
こうやっておふくろがいなくなって、過去を振り返り、あれこれ考えたところで、今はふわっとした感覚のままなのだろう。いや、ずっとこの先の年月で、これを考え続けるのだろう。おふくろや親父のことを考え続けるならば、二人共ずっと僕の近くにいてくれるだろう。だから、この感覚を消し去るのではなくて、ずっと覚えていよう。
通夜に、友達の一人が言った。「お前の文章は本当に意味がわからんな」と。あら、ずっと読んでいてくれるんだ、その意味のわからないものを。そう、自分自身はわけのわからない人間であっても、周りの人がわけの分かる人であればよいね。
2024年5月13日