オンラインショップ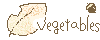
「週刊てーて」ひらく農園から、バックナンバー
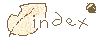
雑事とレシピと掲示板「いどばたけ」
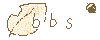
ヒメパセリさんの詩集
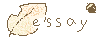
サイトスさんの野菜を使った「レシピ集」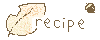
「週刊てーて」ひらく農園から、語りと映像
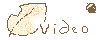
草子の演奏は草子ドットネットへお入りください。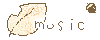
このサイトについて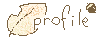
リンク集
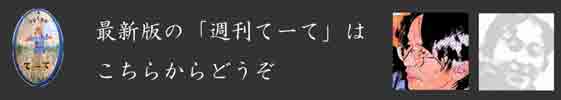
★ 「週刊てーて」+αをブログでどうぞ。
週刊てーて ひらく農園から
 |
|---|
「新しい気候を受け入れて その3」
秋は日に日に深まり、夕暮れはつるべ落としに暮れていく、そんなことを実感する10月の始まりだ。今朝の最低気温は16度台。例年よりも早く、金木犀の香りがどこを歩いても漂ってくる。そういえば、子供の頃はこの時期にこの香りがぷんぷんと漂っていて、それは秋祭りの合図であり、指折り数えたお祭りがすぐそこにあることを知らせていた。近年、だんだんと金木犀の香りの時期が遅くなってきていたので、何年ぶりかのお祭りに合わせたこの時期の香りに、どこか安堵している。
玉葱の種を播いたトレイが、畑に並ぶ。超極早生の裸種子は、芽の出る確率が低い。2年前の種だから仕方がない。2年前には発芽率がよかった。それにくらべて、七宝採種組合のコート種子は、発芽率が尋常でなく高い。コート種子とは、種一粒ごとに天然成分の何物かをくるんで丸くし、機械で種を播きやすくしたものである。機械で苗を植えるための一貫した技術で、高い発芽率を要求されるのだ。今年買ったものも、去年買ったものも、同様に発芽率が高い。10年くらい前だったか、この種の販売元を訪ねたことがあるが、相当に高い技術を守秘していた印象だ。発芽率の高い種を選抜し(ここが特筆すべき技術なのだろう)、一年寝かしてから(これは正確には時間をかけてということなのだろうけれど)、コート種子化し、出荷しているようだ。だから、去年買ったコート種子は、2年前に採種されたものになる。2年前の種でも、発芽率が高いのだから恐れ入る。惚れ惚れするほど、きれいに芽が出ている。大変な天候不順であるにもかかわらず、しっかりと芽を出すのであるから、その採種技術、保存技術、選抜技術は天候に左右されないくらいに高い。このような技術は、日本人の特性を生かした技術と言えるだろう。その恩恵を僕たちも受けているのだ。どんな分野にも、必ず日本人の特性を生かした技術はきっと存在するはずで、その技術の承継と発掘は前をむいて生きる原動力となると信じている。
畑を歩いて、発芽率の良い玉葱の苗床を見ると、背筋が伸びる。畑に直接種を播いても、すべて虫に食べられているラディッシュや小カブを見ていると溜息も出てくるのだが、玉葱の苗床を見ると顔をあげたくなるのだね。今年は、夏が暑かったから、虫も大発生している。それがまだ続く。カメムシも多い。ヨトウムシも多いようだ。ナスは相変わらず実がなってくれているが、カメムシに実を吸われたものは、中が少し黒くなる。ピーマンも同様に、カメムシの被害が多い。新しい気候は、虫の出番の時期をも変える。期間も変える。夏は長く春と秋が短く、冬が長い。そうなると、この短い秋に、虫たちは自分の生命をかけて繁殖をするのだろうか?このことに対処するには、従来の方法では人間の負けとなることが多いから、違った角度のやり方を考えなければいけない。
週末は、お祭りである。家族総出となってしまうので、出荷もお休みである。ある意味では、大きな気分転換にはなるだろう。苗の水やりを自治会から抜け出してきてやるくらいで、あとは畑のことは考えない。豊作豊漁を喜び祈ることが本来のお祭りの意味であろうが、そんなことに思いの至る人は、多くはないのかもしれないね。
2010年10月7日 寺田潤史
 |
|---|
| じゃがいもの芽は出揃った |
 |
|---|
| よくぞきれいに出たもんだ、玉葱の芽。 |
ご意見、ご感想、お問い合わせは、下記よりどうぞお寄せください。
(すべて農薬、化学肥料を使用していません。ここに記載のないものもあります。)
| 1 | 葉大根 | 味わらべ | アブラナ科 | 2010年9月19日播種 | 2010年10月11日から収穫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ししとう | つばきグリーン | ナス科 | 2010年2月1日播種 | 2010年6月21日から収穫 | |
| 3 | ピーマン | 京みどり | ナス科 | 2010年2月1日播種 | 2010年6月21日から収穫 | |
| 4 | バジル | スィートバジル | シソ科 | 2010年3月6日播種 | 2010年5月18日から収穫 | |
| 5 | オクラ | スターライト | アオイ科 | 2010年5月1日播種 | 2010年7月5日から収穫 | |
| 6 | 玉葱 | 七宝早生7号 | ユリ科 | 2009年9月23日播種 | 2010年4月26日から収穫 | |
| 7 | なす | 黒陽 | ナス科 | 2010年2月1日播種 | 2010年6月14日から収穫 | |
| 8 | ニンニク | 上海早生 | ユリ科 | 2010年2月17日播種 | 2010年5月20日から収穫 | |
| 9 | にら | サンダーグリーンベルト | ユリ科 | 2007年2月14日播種 | 2010年2月25日から収穫 | |
| 10 | 葉ねぎ | わかさま黒 | ユリ科 | 2009年10月14日播種 | 2010年3月20日から収穫 |